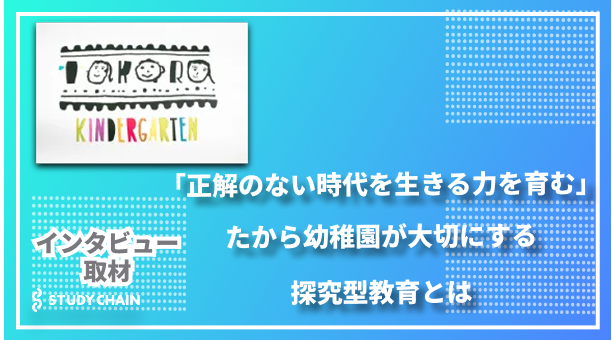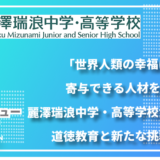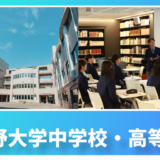杉並区で70年以上の歴史を持つたから幼稚園。
「指導」ではなく「探究」を重視し、子どもたちの興味や好奇心を大切にした独自の教育を実践しています。
AIやデジタル技術が発達する現代だからこそ、自然との触れ合いやグローバルな視点を大切にする、園長の吉澤さゆみ先生にお話を伺いました。
幼稚園概要

ー たから幼稚園について教えてください。
吉澤先生:たから幼稚園では、年少(3歳児)から年長(5歳児)までを対象としており、2歳児以上のプリスクールも運営しています。
教育機関としてのこだわりを持ちながらも、あえて「指導」という言葉は使用していません。
子どもたちは生まれながらに興味や疑問を持ち、それを探究する力を備えているという考えのもと、幼児教育活動を行っています。
現代では、インターネットやAIで簡単に情報を得られる時代となりました。
一方で知識を得てしまった途端に分かったつもりになり、さらなる探究心を失ってしまうことも多くあります・・・
そのため、読み書きや計算、知識などを形だけ教え込むのではなく、『なぜ?』『知りたい!』と子どもたち自身が興味を持って、主体的に物事を考える力を育むことを重視しています。
年間を通して例えば『家族』『昆虫』『ゲーム』『世界の国』など探究テーマを軸にして活動をしていますが、たとえば、こどもの日のこいのぼり製作などは、よくあるように「見本通りにきれいに作ること」を目指すのではなく、「魚ってなんでウロコがあるの?」「みんなにもウロコあるかな?」という問いを起点に、探究の幅を広げていきます。
作ることが“目的”ではなく“出発点”になるのが、当園らしいところです。
母の日は、お母さんへのありがとうカードを作る過程で、カードに書くためのお母さんについてのインタビューをして家族の対話につながっていったりなど、様々な形で探究活動が広がっていきます。
私たちはマルチプルインテリジェンス(MI)と言われる人が持っている8つの知性も意識しながら、それぞのれ学び方の個性に合わせて、身体表現やアート表現、音楽表現、図鑑などで調べたりなど様々なスタイルで一人ひとりの興味の芽を育むことができるような環境づくりを目指しています。
設立の経緯・きっかけ
ー 幼稚園を設立された経緯について教えていただけますか?
吉澤先生:当園は地域からの要請でスタートしました。
設立当時、この地域の地主さんから「これからの社会に幼児教育が大切になる」という声があがり、設立に至りました。
特に初代の園長は与謝野晶子から短歌を学ぶなど、豊かな教養を持つ方でした。
また、設置者も高校教師として教職に造詣が深く、教育に対する確かな理念を持っていました。
特徴やアピールポイント

ー この幼稚園の特徴やアピールポイントについて教えていただけますでしょうか?
1つ目は冒頭でもお話した探究活動です。
子どもたちの興味や疑問を出発点に、深い学びへとつなげていきます。
活動は単なる製作や体験で終わるのではなく、子どもたちの「なぜ?」「どうして?」という気持ちを大切にしながら、先生が教えるというよりも子どもたち同士の対話を通してお友達の視点から様々な方向へと展開していきます。
2つ目はグローバル教育です。
週3回、40分のバイリンガルの素地を育む登録制の英語レッスンを実施しています。
また、園内には5人の英語を話すスタッフが常駐しており、各クラス全員での朝の集まりが英語で行われる日も週に2回あります。
日常的な遊びの中でも、外国人スタッフや英語話者のスタッフと自然に触れ合える環境があります。
アフタースクールでは、通常の預かり保育(14時~16時)に加えて、英語探究型の預かり保育も選択できます。
これは単に英語力を伸ばすためだけではなく、多様性を受け入れる素地を育むことを目的としています。
アメリカやアイルランドなど、様々なバックグラウンドを持つスタッフとの交流を通じて、自然に異文化に触れる機会を提供しています。
3つ目は、豊かな自然環境です。
杉並区内では広い園庭を持つ幼稚園が少ない中、当園では四季折々の自然を感じられる環境を整えています。
デジタルデバイスが普及する現代だからこそ、虫や植物との触れ合い、果物の実りなど、体験を通じた学びを大切にしています。
また、豊富な行事も特徴の一つです。
ただし、全ての行事への参加を強制するのではなく、最初は興味がなくても楽しそうに活動をしている先生や友達が活動しているのを見ているうちに、いつのまにか活動している、という環境づくりを意識しています。
これらは幼児期における選択の機会として重要だと考えています。
学びの環境づくりで意識していること

ー お子さん達と接する際に大切にしていることや、意識していることはありますか?
吉澤先生:まず大切にしているのは、年齢に応じた自立です。
子どもたちの行動や思いに対して、頭ごなしに否定したり大人の価値観を押し付けたりするのではなく、「どうしてそうしたのか」「どういう気持ちだったのか」という対話を重視しています。
けんかやトラブルの際も、双方の話をしっかりと聞くようにしています。
また、子ども同士の対話の場を積極的に設けています。
このような対話を通じて、友だちの意見から新しい考えに気づいたり、「正解は一つではない」ということを自然に学んだりしています。
子どもに問いかけたり、選択の機会を提供することも重要視しています。
もちろん時間やスペースなど制約はあるので、すべてを自由に決められるわけではありませんが、適切な選択肢の中から自分で決める経験を重ねることで、自己肯定感や責任感が育まれると考えています。
もう一つ特徴的なのは、いつも多数決だけで決めないという点です。
これからの民主主義において、単に多数派の意見が通るというのではなく、少数意見も大切にされるべきだと考えています。
例えば、ゲームの際には負けた方に優先権を与えたり、本の選択では少数派の希望も取り入れたりしています。
また、過剰に褒めるのではなく、「(〇〇ちゃんが選んだ)この色、先生も大好きだな」「素敵に塗れたね」など、具体的な共感を心がけています。
これは、他者からの評価を求めて行動するのではなく、自発的な興味や関心から行動する力を育てたいと考えているからです。
今後のビジョン・展望
ー 今後新たに取り組んでみたいことや、強化したいことはありますか?
吉澤先生:近年、海外からの園児や短期滞在の子どもたちが増えてきていることを受け、さらなる国際交流の充実を目指しています。
最近では、マレーシアから幼稚園の先生が訪問してくださり、文化交流を行いました。
子どもたちの興味が非常に高く、このような機会をさらに増やしていきたいと考えています。
具体的には、海外からのショートステイの受け入れや、日本の文化を体験できる外国人向けのサマーキャンププログラムなどを計画しています。
より多様な環境で、子どもたちが様々な文化や価値観に触れる機会を作っていきたいと考えています。
また、最近幼児期のデジタルデバイスの過剰な利用と子どもたちの主体性や探究心の低下などの関連性について気になっており、その分野でも幼児教育の現場からの情報発信をしていきたいと考えています。
入園をお考えの方へのメッセージ
ー 最後に、幼稚園に入園をお考えの方にメッセージをお願いできますでしょうか?
吉澤先生:現代は、“これが正解”と言い切れない時代です。
だからこそ私たちは、子どもたちが自分の感じたことや疑問を出発点に、自分の軸で考え、生きていく力を育てたいと願っています。
一見手厚く見える「先生が先回りして教える」「”できるようになる”という結果のきれいさを重視する」そのような関わり方ではなく、私たちが目指すのは、“見守る力”のある大人がそばにいる環境。
完成されたものを与えすぎず、言葉で説明しすぎず、子ども自身のペースで考える余白を残すことを大切にしています。
「目はかけるけれど、過剰に手はかけない」「ほめすぎないけれど、共感し、寄り添う」。そんな私たちのまなざしの中で、子どもたちは少しずつ自分の力を信じられるようになっていきます。
探究的な学び、多様性を自然に受け入れる環境、自己決定の積み重ね…。こうした取り組みは、都心部では少しずつ広がりつつありますが、杉並区ではまだ多くはありません。
その中で「こういう幼稚園もあるんだ」と感じてくださる方と出会えることは、私たちにとって大きな喜びです。
「この子には、どんな環境が合っているんだろう?」と考え始めたとき、もしお子さんの“なんで?”や“やってみたい”を大切にしたいと感じていらっしゃるなら、一度、たから幼稚園の空気を感じに来てください。きっと何か、見えてくるものがあると思います。