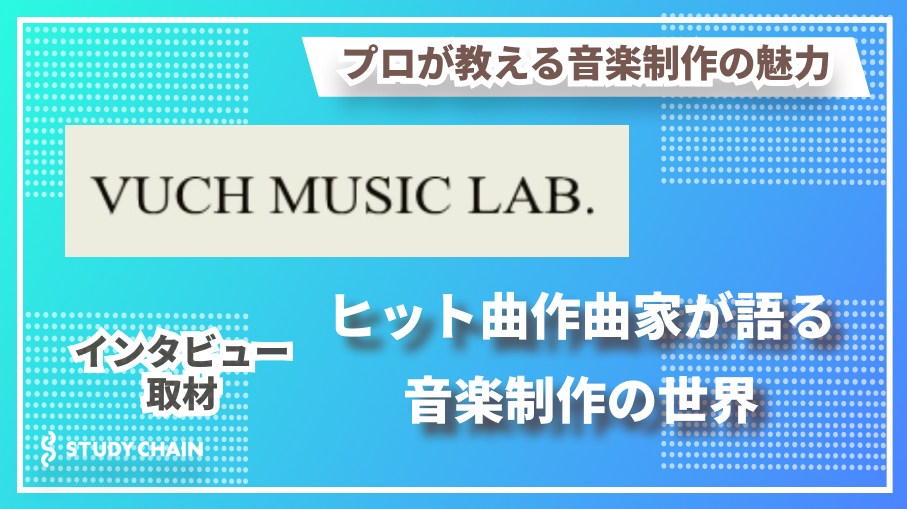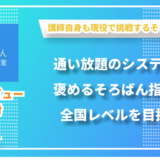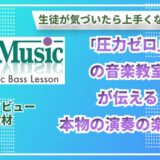香川県で音楽制作に特化した教室『VUCH MUSIC LAB.(ブッチミュージックラボ.)』を運営する溝渕大智氏は、一青窈さんの「もらい泣き」など数々のヒット曲の作曲を手がけてきたソングライターです。東京での音楽制作の経験を活かし、地元・香川で次世代へ音楽づくりの楽しさを伝える活動を続けています。
音楽制作と言えば難しいイメージを持つ人も多いと思いますが、溝渕氏は「極論、鼻歌ができれば曲は作れる」と語ります。マンツーマン指導を基本とし、プロの現場で使う本格的な機材を生徒に開放する独自のスタイルで、初心者から上級者まで幅広く対応。作曲からDTM(デスクトップミュージック)、ギター演奏まで、音楽のあらゆる側面をカバーする指導が評判を呼んでいます。
今回は、そんな溝渕氏に音楽制作の魅力や教室運営にかける思い、さらには「誰にも迷惑をかけずに創造性を発揮できる」という音楽の素晴らしさについて語っていただきました。プロの視点から見た作曲と編曲の関係性など、音楽ファンにとっても興味深い話が満載のインタビューをお届けいたします。

高松市出身。作・編曲家、ギタリスト。一青窈の楽曲や音楽活動へ参加し、デビューシングル「もらい泣き」では数々の賞を受ける。またTV-CM、映画、ドラマ、イベント音楽など多岐に渡り数多くを手掛ける。メロディーの良さと斬新なアイデア、アレンジ技術には定評がある。幅広い音楽ジャンルに精通。主としてギタリストであるがウクレレやバンジョーなどの各種民族楽器や鍵盤楽器、おもちゃ楽器も操るマルチプレーヤーでもある。また変則チューニングも好んで使い既成概念にとらわれない独自の演奏法や作曲法を武器にする。近年の代表作品はクレヨンしんちゃんスピンオフ作品「SUPER SHIRO」エンディングテーマ曲(作・編曲)、ベイブレードバースト超王オープニングテーマ曲(編曲)がある。ADK Wonder Records提携ミュージシャン。
プロの楽曲制作者が開く「音楽づくり」の扉

ー 溝渕様、本日はどうぞよろしくお願いいたします!『VUCH MUSIC LAB.(ブッチミュージックラボ.)』はどのような教室なのか、対象となる方や指導内容について教えていただけますか?
溝渕大智代表(以下、敬称略):『VUCH MUSIC LAB.』は器楽(ギターなど)も指導していますが、主に音楽を作ることに特化しています。音楽制作全般、作曲から編曲、コンピューターを使った楽器のプログラミングや編集作業まで、幅広く対応できる教室です。
対象年齢は、ウクレレやギターについては小学1年生から中学3年生までのコースがありますが、それ以外は年齢制限を設けておらず、現在は80代の方まで通われています。特に30代から50代の方が多く、小学生も増えてきました。完全マンツーマン指導で価格も手頃なため、幅広い年齢層の方にご利用いただいています。
ー 作曲や編曲って難しいイメージがありますが、初心者でもできるようになるものなのでしょうか?
溝渕:クラシック音楽のように厳格なルールがあるものは確かに難しいですが、一般的に皆さんが聴いているポピュラー音楽であれば、私は「鼻歌ができればOK」だと考えています。
鼻歌ができるということは、メロディーを作る素地があるということです。それを鍵盤に置き換え、正確な音符に変換していく。そこからは少し技術が必要になりますが、「コード進行」を一緒に考えながら、「この和音だとこういう響きになるね」「こうすると暗い感じになるね」といった形で少しずつ進めていくレッスンを行っています。初心者の方でも十分に始められる内容です。
ヒット曲メーカーの誕生秘話とスクール設立への道

ー 溝渕様が『VUCH MUSIC LAB.』を始められた経緯やきっかけを教えてください。
溝渕:高校卒業後、東京で音楽事務所に所属し、様々な音楽制作の仕事を経験しました。当時は曲を作ってクライアントに納品することが主な仕事でしたが、2005年頃から納品形態がインターネットを通じたものに変わってきたんです。
それまではテープや音楽専用のデジタルメディアでの納品が主流でしたが、それらがほぼ不要になり、「これなら地元に戻っても仕事を続けられる」と考えました。今で言うリモートワークですね。
2005年頃からそういった環境が整い始めたのもあり、2007年頃に地元香川に戻りました。私自身、先輩方からコンピューターの使い方や作曲技術を教わってきましたが、これをスクール化できないかと考えたのです。
当時は楽器演奏のレッスンは多くありましたが、音楽制作そのものを教える場所は少なかった。自分が学んできたことを次の世代に伝えられるビジネスにしたいと思ったのが始まりです。
本物の音楽スタジオで学ぶ贅沢な環境

ー 作曲を教えている教室は他にもあるかもしれませんが、『VUCH MUSIC LAB.』ならではの強みはどこにあるとお考えですか?
溝渕:弊スタジオの最大の特徴は、私が普段実際に作業している環境をそのまま開放している点です。言い換えれば「プロの道具が全て揃っている」ということです。
専門学校や音楽大学では生徒用のシステムが用意されていますが、それだけでは対応しきれない珍しいソフトウェアや特殊な楽器などを実際に使い、体験できる点が他と大きく異なります。プロが実際に使用している環境で学べるため、本物の音楽制作の雰囲気を感じながらスキルを磨くことができます。
ー プロが実際にリリース作品のために使用している高レベルの機材が使えるということですね。
溝渕:その通りです。必要な機材が一通り揃っているので、実際のプロの現場がどういうものかを体感していただけます。これが他の教室とは違う最大の特徴だと思います。
一人ひとりの個性を引き出すマンツーマン指導の哲学

ー 生徒さんに指導する際に、意識していることや方針があれば教えてください。
溝渕:開講して10年以上になりますが、基本的にマンツーマン指導を一貫して続けています。
このスクールを完全マンツーマンにしている最大の理由は、音楽制作はグループでは効果的に教えるのが難しいからです。5人いれば全員好きな音楽も違いますし年齢も異なります。テキストベースの一律指導では音楽創作のような個性的な活動は教えにくいんです。楽器演奏ならグループレッスンも可能ですが、創作はマンツーマンでないと伝わらない部分が多いと考えています。
マンツーマン指導では、コミュニケーションが重要になります。生徒さんによって表現力やコミュニケーションスタイルは様々です。私が大切にしているのは、生徒さんが何を考え、何をやりたいのかをしっかり汲み取ること。特に中高生などは自分の思いを上手く言葉にできないこともあります。
私は「必ずこれをやってください」と押し付けるのではなく、生徒さん自身が今日やりたいことや興味を持っていることを中心に、能動的に取り組めるようサポートしています。
創り、奏で、編む—3つのコースで広がる音楽の可能性
ー 提供されているコースや内容について簡単に教えていただけますか?
溝渕:弊教室では主に3つのコースを用意しています。

まず「ギターコース」では、私自身がギタリストとしてのバックグラウンドを活かし、基本的なテキスト学習から生徒さんが弾きたい曲への挑戦、お子さん向けの簡単なメロディー練習まで、レベルに合わせた指導を行っています。

次に「作曲コース」では、和音(コード)を弾きながら鼻歌でメロディーを生み出し、曲の骨組みを構成できるようになることを目指します。音楽の本質はメロディと和音にあります。曲から様々な要素(ドラム、ギター、ベースなど)を取り除いたとき、最後に残るこの「屋台骨」の部分をまず作れるようになることが重要なのです。

そして「DTMコース」は、コンピューターを使った音楽制作の技術を学びます。このコースでは音に関するあらゆる要素を扱えるようになり、アレンジから細部の調整まで総合的なスキルを身につけられます。例えば、作曲コースである程度曲が作れるようになった後、ドラムやベースをプログラミングで加えたいという場合に必要になる技術を学びます。
また、作曲自体には興味がなくても、コンピューターを使った音楽編集や加工技術を学びたい方もいます。ミックスやマスタリングといった、音楽素材をバランス良く調整する作業に特化した学びも提供しています。
ただし、『VUCH MUSIC LAB.』の最大の特徴は柔軟性です。マンツーマン指導だからこそ、「今日はこれをやってみたい」という生徒さんの希望に臨機応変に対応できます。コース分けは分かりやすさのためであって、実際には縛りを設けず、その日の興味や関心に合わせた指導を心がけています。
子供向けの曲からヘビメタまで—ジャンルを超える職業作家の底力
ー 様々な音楽ジャンルへの対応はどうされているのですか?
溝渕:私が「職業作家」として長年活動してきた経験が活きています。一般的な作曲家はある特定のジャンルに特化していることが多いのですが、職業作家は様々なジャンルに対応する必要があります。
広告業界での仕事も長くやってきたため、「今日は子供向けの曲、明日はヘビーメタル」というように、幅広いジャンルの制作を求められてきました。それぞれのジャンルの専門家には及ばないかもしれませんが、多様なスタイルに対応できる能力を培ってきました。
この経験が教室運営でも大きな強みになっています。様々な好みやジャンルの音楽を希望する生徒さんに対して、一定レベル以上の指導ができるのです。
編曲と作曲、技術的な難易度の真実
ー 素人目には作曲の方が地位が高いイメージがありますが、実際には編曲と作曲、どちらが難しいものなのでしょうか?
溝渕:良い質問ですね!歴史的に見ると、クラシック音楽の時代では作曲家と編曲家の明確な区別はあまりなく、作曲家が全ての音の配置に責任を持っていました。モーツァルトやバッハの「編曲」という言葉はあまり聞かないですよね。
近代に入ると、既存のメロディーを活かして和音を変えたり、リズムを変更したり、楽器編成を変えたりする「編曲(アレンジ)」という専門性が生まれてきました。比喩的に言えば、同じ人(メロディー)に異なる洋服を着せて新しい印象に変える作業です。
権利面では、JASRACなどに登録されるのは主に作詞家と作曲家で、編曲家は報酬面であまり恵まれない立場にあることが、正直多いです。しかし、技術的な難易度で言えば、編曲の方が難しいのです。
作曲は、極端に言えば「良いメロディーが思いつくかどうか」という部分が大きいですが、それを実際に形にして人に届けるためには、編曲の技術が不可欠です。素晴らしいメロディーがあっても、それを曲として完成させるための技術がなければ、聴き手に伝わりませんからね。
デジタル時代の音楽教育 — 次世代へのバトン
ー 今後、強化していきたい点や新たに取り組みたいことはありますか?
溝渕:現在、音楽制作の仕事をしながら学校での指導や30人以上の生徒さんを見ているので、かなり多忙な状態ではあります。
ただ、最近特に気になっているのは、学校の部活動の「地域移行」です。中学校は近い将来、部活動を地域社会に委ねる方針が進められています。文部科学省の推奨で全国的に始まっているこの流れの中で、(部活動による)音楽に触れる機会が減ってしまう子どもたちが出てくる可能性があります。
そういった子どもたちに向けて、何かアプローチができないかと考えています。部活ほど本格的でなくても、例えば同好会のような形でアコースティックギターを触れる機会など、音楽と出会うきっかけを提供できればと思っています。次世代の音楽愛好家を育てる活動にも力を入れていきたいです。
「失敗を恐れず創造する喜び」 — 音楽が与えてくれるもの

ー 最後に、『VUCH MUSIC LAB.』に興味のある方へメッセージをお願いします!
溝渕:音楽にはルールやマナーがありますが、それ以上に私が大切にしているのは「アイデア」です。通常の環境では試せないような発想、「これは普通だったら受け入れられないかも」というようなアイデアを形にする喜びが音楽にはあります。
会社や学校では失敗のリスクや周囲への影響を考えると、思い切った挑戦がしにくいものです。しかし音楽は何をやっても誰にも迷惑をかけません。自分のアイデアを自由に試して、その結果を自分自身で感じ取ることができる。これが音楽の素晴らしい点だと思っています。
私は必ずしもプロの音楽家を養成するというわけではなく、試行錯誤を繰り返しながら自分の表現を見つけていく過程を大切にしています。誰にも迷惑をかけずに創造性を発揮できる‟音楽”という環境は、人生を豊かにしてくれるものです。私自身もそうやって音楽に支えられてきた経験があるからこそ、その素晴らしさを伝えていきたいと思っています。