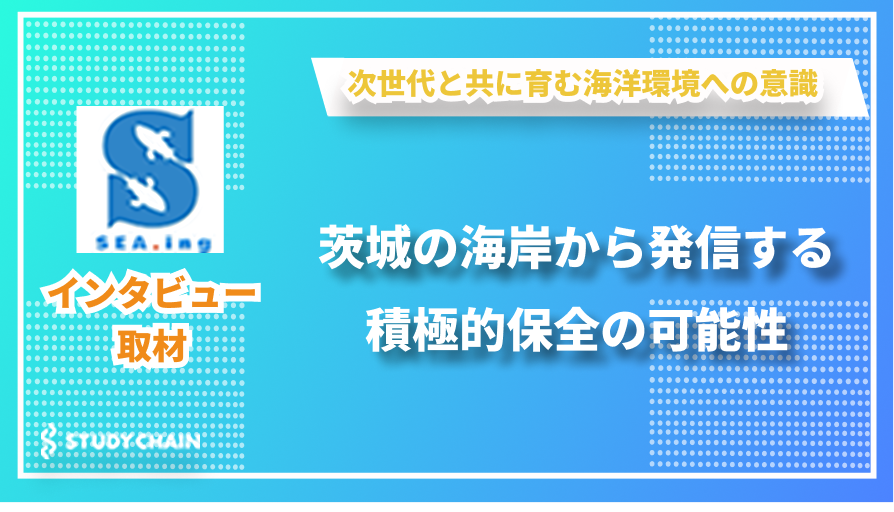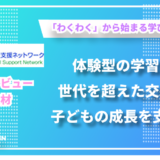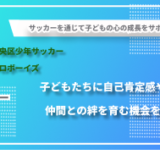茨城県の約200kmに及ぶ海岸線で、月1回のビーチクリーン活動を実施する「特定非営利活動法人SEA.ing」。楽しみながら環境保全への意識を育む「積極的保全」という独自のアプローチで、地域の海洋環境の未来を守る活動に取り組んでいます。
また、中高生を対象とした教育活動にも力を入れ、次世代の環境意識の醸成にも貢献しています。
同法人の取り組みや今後の展望について、大橋さんにお話を伺いました。
活動のきっかけは大学でのスキューバダイビング体験から

ー設立の経緯と、団体の概要について教えてください。
大橋:私は現在大学院生なのですが、大学でスキューバダイビングを始めたことが活動のきっかけでした。
ダイバーやサーファーなど海でレジャーを楽しむ方々は、一般の方に比べて海を守りたいという意識が強いことを肌で感じ、自分も何か活動をしてみたいと考えるようになりました。
2023年4月に法人を設立し、茨城県在住の方を中心に、ビーチクリーン活動や中高生向けの教育事業を展開しています。
茨城県の海岸は200km近い長さがあり、海流の影響で漂着物が多い地域です。都市部から離れており、海洋保全活動の機会が限られている中で、いかに活動に魅力を付けて参加を促進できるかを考えながら取り組んでいます。
レジャー感覚で楽しめる環境保全活動を目指して
ー具体的な活動内容について教えてください。
大橋:主な活動は、ビーチクリーンと講演事業の2本柱です。ビーチクリーンでは単にゴミを回収するだけでなく、スイカ割りやビーチコーミングなど、様々なアクティビティを組み合わせレジャーとして楽しめる工夫をしています。
毎月開催している定例のビーチクリーンには、地域の中高生から大学生から高齢者まで幅広い年齢層の方々が参加しています。活動場所は茨城県内の2か所を中心に、市役所とも連携しながら最適な場所を選定しています。
講演事業では、特に中高生を対象に、海洋環境の現状について科学的な知見に基づいた情報発信を行なっています。
例えば、マイクロプラスチック問題については、現時点での研究成果や今後予想される影響など、事実に基づいた情報を伝え、環境について考える機会を提供しています。
SEA.ingならではの特徴的な取り組み
ー貴法人ならではの独自の取り組みについて教えてください。
大橋:私たちの特徴は、誰でも気軽に参加できる雰囲気づくりを心がけていることです。特別な準備や道具がなくても参加できる環境を整えています。また、活動地域の特性上、回収できるゴミの量は国内でもトップレベルです。
このため参加者は、環境問題の深刻さを体感的に理解することができます。ただし、決して重苦しい雰囲気にならないよう注意を払っています。気軽に参加でき、かつ実感を伴う経験ができる点が、私たちの活動の特徴だと考えています。
他団体との連携を通じた活動の拡大へ
ー今後の展望についてお聞かせください。
大橋:設立から約2年が経ち、茨城県の海岸清掃活動については一定の実績を積み重ねてきました。活動を続ける中で、少しずつ地域での認知度も高まってきていると感じています。
しかし、月に数回の活動だけでは限界があると感じているため、他の団体やボランティアの方々との連携を強化していきたいと考えています。
NPO法人という立場を活かし、助成金の活用や行政との連携を図りながら、様々な団体を巻き込んでこの環境問題に取り組んでいきたいと思います。
「積極的保全」の理念で海との距離を縮める
ー最後に、読者へのメッセージをお願いします。
大橋:私たちが大切にしているのは「積極的保全」という考え方です。海を守りたい、汚したくないというネガティブな感情からではなく、海を楽しみ、より身近に感じることで生まれる意識を大切にしています。
特に若い世代に対しては、環境問題を一方的に教え込むのではなく、活動を通じて自然と芽生える感覚を大切にしています。
「ゴミが多いのは嫌だな」「これが海に流れてしまうのは困るな」といった素直な感覚こそが、環境保全の原動力になると考えています。
ぜひ皆さんも、私たちの活動に限らず、様々な団体の活動に参加したり、自身で海に足を運んだりして、海との距離を縮めていただければと思います。
環境問題は大きな課題ですが、一人ひとりの小さな意識の変化から、少しずつ解決に向かっていけると信じています。