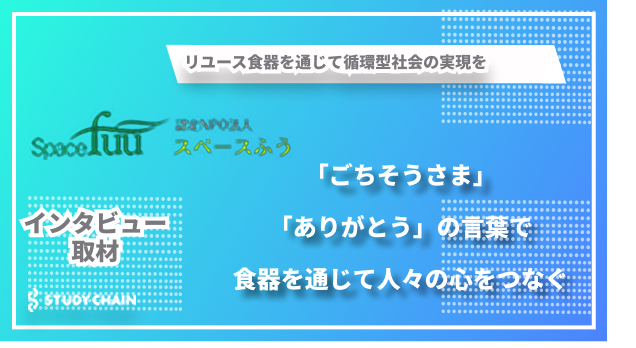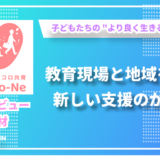20年以上前、未経験の女性たちによって活動をスタートさせた環境活動団体「スペースふう」。
現在では19万個ものリリース食器を保有し、全国のイベントや祭りにリユース食器をレンタルする事業を展開しています。
使い捨て容器から脱却し、人と人とのつながりを生む新しい価値の創造に挑戦し続ける彼女たちの思いと、その実践的な取り組みについて、「スペースふう」の長池伸子さんにお話を伺いました。
循環型社会の実現を目指して

- どういった方を対象にどのような活動をされていらっしゃいますか?
長池さん:私たちは「リユース食器を通して循環型社会の実現を目指す」という基本理念のもと、使い捨てのごみが出るお祭りなどのイベントで、リユース食器を使っていただき、ごみを削減することをメイン事業としています。
各種イベントや結婚式、会議などさまざまな活動でリユース食器をご利用いただいています。
女性たちの想いから始まった環境活動
- このような活動をされるに至ったきっかけや背景についてお伺いできますでしょうか?
長池さん:理事長の永井寛子が20年以上前に、リサイクルショップ仲間の女性たちと一緒に、服や食器を地域で循環させていく活動をしていました。
そんな中、甲府で環境活動家の方の講演を聴き、ドイツではお祭りでリユース食器を使用してごみを出さない仕組みがあることを知り、衝撃を受けました。
「ドイツでできるなら日本でもできるはず」という想いから、1年近くかけて、当時の日本にはなかったリユース食器のレンタル事業の可能性を模索しながら立ち上げました。
その根底にあるのは、子育て世代の女性たちが立ち上げたということもあり、子供たちに残す未来、残す環境をごみでいっぱいにはしたくないという願いでした。
「無い」からこそ生まれた可能性

- 活動の強みやアピールされたいポイントについてお伺いできますか?
長池さん:理事長がよく話しているのですが、立ち上げの時に女性たちが集まってやったのは、「知識も無い、お金も無い、そして経験も無い」という3つの「無い」からのスタートでした。
一般的な事業では、ある程度の経験値や準備が整ってからというのが普通です。
しかし、私たちはそれを飛ばして「やるぞ」という強い想いで始めました。
むしろその「無い」ということが強みとなり、周りの協力者の方々がどんどん関わってくださり、教えていただいたり、つないでいただいたりすることで、スペースふうは成長してきました。
組織の特徴:「属人的」であることの価値
- スペースふうの活動に関わってみて、どのような特徴を感じましたか?
長池さん:決まった枠が出来上がっているわけではなく、分からないながらも「やらなければ」という想いで進めてきました。
これは今まで自分が生きてきた中での価値観とは逆でしたが、それがむしろ魅力となっています。
スタッフで知恵を出しながら事業を育てている実感があり、既存のルールやステップにとらわれない進め方をしています。
一般的な事業では「属人的であってはいけない」とよく言われますが、スペースふうはまさに属人的な良さを活かしています。
「この人がいるからこうできる」「この人との組み合わせだからこそ」という強みが、スペースふうならではの進め方を可能にしています。
課題を成長の糧に
- 活動される中で難しいと感じることはありますか?
長池さん:正直に申し上げると、すべてが難しいと感じています。
ただし、その難しさはネガティブなものではありません。
難しいからこそ、みんなが意見を出し合ったり、感情を表現したり、時には引っ込めたりしながら、日々成長させていただいているような気がします。
全国に広がるリユース食器の実践的な仕組み

- 具体的な業務の流れについてお聞かせください。
長池さん:現在、約19万個の食器を保有しており、お客様からの注文に応じて必要な種類と数の食器を準備し、コンテナに入れて出荷します。
イベント会場では、使用済み食器を回収し、残飯などを処理していただいた後、専用の袋に入れてからお届けした時と同じコンテナに入れて返送していただきます。
返却された食器は、数を確認した後、高圧洗浄機で洗浄し、消毒・乾燥、最後に検品を行います。
検品は、一つひとつ目視で確認し、次のイベント用にパッキングするという流れです。
主催者の負担を減らすため、現地での洗浄は不要とし、汚れたまま返送できる仕組みを構築しています。
食器の返却システムと工夫
- 返却の仕組みについて、具体的にどのような工夫をされていますか?
長池さん:イベントによって異なりますが、デポジット制を採用しているところもあります。
例えば、ビールが600円の場合、カップの保証金として100円を上乗せして700円で販売し、回収所に返却した際に100円が返金される仕組みです。
また、デポジット制を採用していない場合でも、会場のアナウンスや、出口に回収所を設置するなど、返却しやすい動線づくりを工夫しているイベントが多いようです。
特に子供たちは環境教育で学んでいることもあり、家族連れの方々は自然に返却する習慣が根付いています。
リユース食器が紡ぐ人と人とのつながり
- 活動される中で大切にされていることや特別意識されていることは何かありますか?
長池さん:リユース食器は環境面での効果が注目されがちですが、それだけではありません。
お祭りは人が集う場所であり、その在り方は人の暮らしや町づくりなど、様々なものに紐づいています。
物を大事にすることは、人を大事にすることにもつながります。

例えば、使い捨て容器だと食べ終わったら「ポイ」で終わってしまいますが、リユース食器は「返す」という行為を通じて、次の人への感謝の言葉が生まれます。
「ごちそうさま」「ありがとう」という言葉が、食器を通じて人々の間を循環していくのです。
未来へのビジョン
- 今後の展望や将来的なビジョンについてお聞かせください。
長池さん:今後の展望についてですが、世界規模で使い捨てプラスチックごみが深刻な悪影響を及ぼしている今、スペースふうのリユース食器の活動はその解決策として今まで以上に求められています。
この取り組みが持続可能であるためにも、運営体制を強化していきたいと考えています。
そのためにもメンバー一人ひとりの視点や想いを大切にしながら、1ミリずつでも前に進んでいきたいと考えています。
- 最後に、読者の方へメッセージをお願いします。
長池さん:身近なお祭りやイベントでリユース食器を使用している場面に遭遇した際は、大切に使っていただき、決められた場所に返却をお願いします。
その一つひとつの行動が次の大切なイベントにつながっていきます。
また、誰かが使った食器が綺麗になって自分の手元に届いているということを感じていただけたら嬉しく思います。
そして、返却の際には、美味しかった感想とともに「ありがとう」の言葉を添えていただければ、その気持ちを出店者さんやイベント主催者さんへつなげていきます。