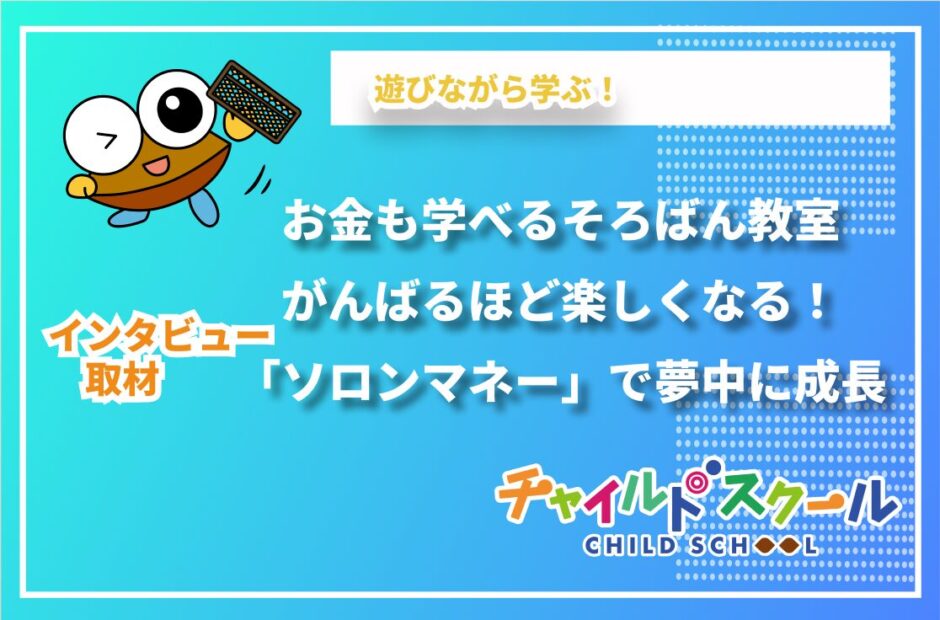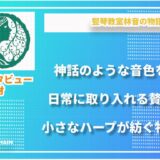──チャイルドスクールが目指す“学びの遊園地”
子どもたちが自発的に学び、成長していく環境をどうつくるのか。
奈良を中心に展開する「チャイルドスクール」は、そんな問いに真剣に向き合いながら、そろばん学習の可能性を拡張し続けています。
今回は、教室の魅力と独自の取り組みについて、チャイルドスクール代表の乾さんに、お話を伺いました。
教室に来なくても学べる、ハイブリッド型のそろばん学習
チャイルドスクールは、奈良・京都・和歌山に7教室を展開しており、「固定月謝・学び放題」のスタイルを採用しています。生徒には全員タブレットを配布し、教室でも家庭でも同じように学べる仕組みを整えています。
たとえば、忙しいご家庭や遠方にお住まいの方には、学習単元の動画をオンデマンドで提供し、自宅での学習も可能に。新しい単元に進むときだけ教室で説明を受け、それ以外は自宅で取り組むこともできます。反対に、家庭学習が難しい場合は、教室でじっくり取り組むこともできます。
こうした柔軟なスタイルは、通塾が難しい家庭や、他の習い事と両立したいご家庭にとっても大きな魅力です。
年齢や環境に応じた“学びの自由”を提供
通塾生は4歳から23歳までと幅広いですが、メインとなるのは幼稚園年長から小学校低学年の子どもたち。学年が上がると学習塾などとの併用が難しくなる場合もあるため、そろばんにしっかり取り組める幼少期のタイミングを大切にしています。
また、固定時間制ではなく「いつ来ても、いつ帰っても良い」という自由な出入りが可能なスタイルを導入。1日15分だけ集中して帰る子もいれば、2時間みっちり学ぶ子もいます。
子どもが「今日は頑張れる」と思ったタイミングに合わせて学習できる環境が整っているのも、この教室ならではの魅力です。
教室づくりの原点は「そろばん嫌いだった自分」
そろばん教室を立ち上げたきっかけは、「自分がそろばん嫌いだったこと」でした。
小学生の頃、授業の合間に遊んで叱られていたという経験から、「そんな自分でも夢中になれる教室をつくりたい」と考えたのが始まりでした。「勉強が苦手だった自分だからこそ、子どもたちの“苦手”に寄り添える」と。
子ども目線の楽しさを大切にし、学びの楽しさを知ってもらえる場所をつくる。それが、チャイルドスクールの原点です。
ゲーム感覚で学ぶ、独自の報酬制度「そろんマネー」
教室内では「そろんマネー」と呼ばれる仮想通貨が使われており、学習を頑張ることで報酬が貯まり、クレーンゲームやガチャガチャ、塾内ショップでの“買い物”ができるという仕組みになっています。
単なる遊びではなく、「お釣りはいくら?」「50そろんを使って30そろんの品を買ったら…」など、生きた計算力やお金の管理スキルも自然と身についていくよう設計されています。
金銭感覚と数字感覚の両方を育てるこの仕組みは、多くの子どもたちのモチベーションにもつながっています。
勉強が苦手な子にこそ、好きになる“きっかけ”を
「勉強が得意な子は、さらなるスキルアップを。苦手な子に対しては、好きになる“きっかけ”をつくる。それが私たちの役割です」。
この教室では、厳しく叱って教えることは一切ありません。押し付けの環境下からは個性は育たないとの想いから、子どもの目線に立ち、どんなことに困っているかを丁寧に聞き出すようにしています。
だからこそ、自分で計画を立てて取り組む「じぶん授業」という指導スタイルを取り入れ、子どもが自分で目標を決め、進行表に従って学習を進めていくようになっています。
右脳を育てる、幼少期の暗算トレーニング
そろばん教育の本質は、単なる計算力にとどまりません。特に「そろばん式暗算」は、頭の中でそろばんの玉をイメージして計算する“図形処理”です。これは右脳の活性化に非常に効果があるとされています。
この力を最大限に育てられる時期は、年長から小学校2年生くらいまでと言われています。だからこそ、小さいうちからそろばんに触れてほしいと願っています。
数字が得意な子には特に向いている習い事であり、頭の柔軟性が高い時期にこの力を育てることが、今後の学習全般に好影響を与えるのです。
小さな子どもでも理解できる、段階的な指導方針
チャイルドスクールでは、いきなり掛け算・割り算には進みません。まずは1桁→2桁→3桁と、段階的に足し算・引き算をマスターしてから、掛け算・割り算へと進みます。
これは「理解できないまま進むと、学びが機械的になってしまう」という考えからであり、3桁までの加減算をしっかりと理解させることで、買い物や日常生活の中でも活用できる力を養っています。
一生モノのスキルを、そろばんで手に入れてほしい
「そろばん(特にそろばん式あんざん)は一生忘れないスキル。集中力も養われるし、他の学習にも波及します」。
チャイルドスクールでは、読み書き計算の“基礎”を大切にしながら、子どもたちが学ぶ楽しさを実感できるような指導を心がけています。
学ぶことの楽しさに気づけた子どもは、次の挑戦にも自信を持って臨めるはずです。