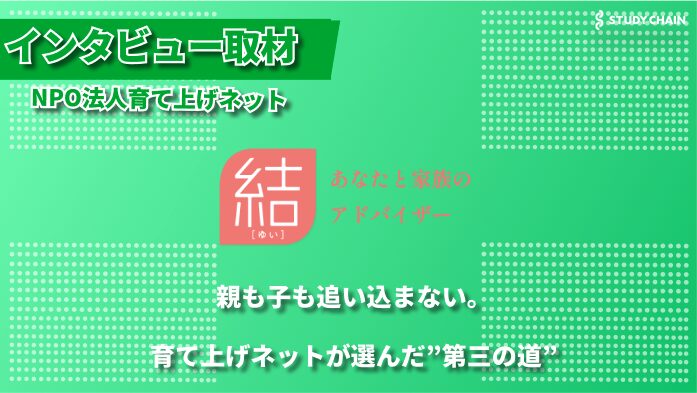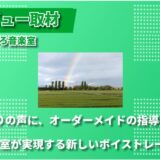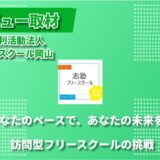「子どもがひきこもっているから」「学校に行けないから」―。子育ての悩みを抱える親御さんにとって、最も辛いのは「どうしたらいいのかわからない」という不安かもしれません。NPO法人育て上げネットは、そんな家族に寄り添い続けて15年。本人が来所しなくても変化を生み出せる独自の支援方法で、多くの家族に希望をもたらしています。今回は、家族支援事業責任者の蟇田さんに、支援の特徴や実際の変化の様子についてインタビューしました!

20年の歴史を持つ若者支援団体
ー育て上げネットの設立経緯と事業内容について教えてください。
蟇田さん:NPO法人育て上げネットは、2004年5月に設立された若者支援団体です。設立のきっかけは、理事長の工藤が20代の頃、アメリカ留学中に「若い世代を労働の観点から支えるビジネスのマーケットが日本にもできるよ」との指摘を受けたことでした。この示唆や欧米の視察を通じて、若者支援の活動を日本でやることを決意しました。
当初は15歳から39歳までの無業の若者を対象としていましたが、活動を続けるうち子どもの貧困の問題や就職氷河期世代の課題が顕在化して、現在は学齢期の子どもたちから49歳まで対象は拡がっています。支援内容は、就労や復学といった社会との接点づくりだけでなく、その後も継続的な伴走支援を行い、一人一人が自分らしく生きていける人生を応援しています。
事業は大きく分けて3つの支援が行われています。社会的孤立状態にある若者の就労を支援する「若者就労支援事業」、小中高生の学びと将来を支援する「学習支援事業」、そして家族を支援する「家族支援事業」です。
対面での支援拠点は東京、神奈川、大阪にありますが、ビデオ通話を活用することで全国からの相談に対応しています。
システムズアプローチによる家族支援の始まり
ー家族支援事業を始められた経緯を教えていただけますか。
蟇田さん:若者の就労支援やひきこもり支援を行う中で、私たちは重要な課題に直面しました。それは、本人が孤立した若者のご家族が、医者やカウンセラーを訪ねると「本人を連れてきて」といわれてしまい途方に暮れているということです。
この経験から、若者の社会進出を支援するためには、家族間の関係性を変えていく必要があると実感し、15年前から家族相談、特に母親への相談支援を開始しました。
当初は対面での相談のみでしたが、支援の可能性を広げるため、2015年頃からはオンライン支援を導入しています。その後、コロナ禍を経て支援のオンライン化が一気に進み、現在では全体の約7割がオンライン支援、3割が対面支援となっています。年間では1,200件の相談に対応し、約900組の家族と関わっています。支援対象も幅広く、小学生低学年の不登校から、いわゆる8050問題を抱える家族の相談にも応じています。
15年間の実践を通じて、家族支援の重要性はますます高まっています。特に近年は、不登校やひきこもりの問題は多様化・複雑化しており、家族全体を支援する私たちのアプローチの必要性が一層増しています。支援を必要とする家族に確実に届けられるよう、対面・オンライン双方の利点を活かしながら、支援の質の向上に努めています。
多様なニーズに応える家族支援プログラム
ーどのような支援プログラムがありますか。
蟇田さん:NPO法人育て上げネットでは、各家庭の状況やニーズに合わせて選択できる複数の支援プログラムを用意しています。基本となるのは「結プレミアム」プログラムです。これは月1回の個別相談と、グループワークをセットにしたサービスで、月額11,000円で利用できます。グループワークは毎月開催され、対面とオンラインのハイブリッド形式で実施。同じような悩みを持つ親同士が交流できる貴重な機会となっています。
グループでの活動に抵抗がある方には、オンラインでの個別相談「結レギュラー」も用意しています。通常1回8,800円の相談を、お得な料金で利用できる回数券制度を設けています。また、勉強熱心で課題解決を効率的に進めたい方向けに「結ショート」という短期集中型プログラムも提供しています。
このプログラムは3回で1つの解決のための方針を定めるもので、初回で課題を抽出して対応策を検討し、2回目で実践の振り返りと改善点の確認を行い、3回目で継続的な取り組みに向けた助言を行います。
経済的な事情を考慮し、無料相談枠も設けています。また、ご寄付などを活用して、困窮世帯向けの支援も実施。経済的な理由で支援を受けられない家庭が出ないよう配慮しています。
育て上げネットの家族相談が持つ独自の特徴
ー育て上げネットの家族相談の特徴を教えてください。
蟇田さん:私たちの家族相談には、他の相談機関とは異なる特徴があります。最も大きな特徴は、「本人不在でも支援を開始できる」という点です。一般的な相談窓口では、本人が来談しないと支援が進められないケースが多いのですが、私たちは家族療法の「システムズアプローチ」を用いることで、相談に来られた方の関わり方を変えることで本人の行動変容を促すことができます。
これは、家族という「システム」の中で、一人の変化が全体に波及していくという考え方に基づいています。実際に本人と一度も会わなくても、復学を望む子どもが学校に通えるようになったり、ひきこもりの若者が就職したりといった具体的な変化を生み出せています。
私たちのアプローチのもう一つの特徴は、小さな変化を大切にする視点です。問題を抱えた家族は往々にして、すぐに大きな変化を求めがちです。しかし、実際の回復は「らせん階段を上るように」少しずつ進んでいきます。例えば、最初は子どもが声かけに反応するまでの時間が短くなり、次第に家族との食事の頻度が増えていきます。
そして徐々に会話の量が増え、表情が明るくなり、外出の頻度が増えていくといった具合です。これらの変化は、一見些細に見えるかもしれませんが、私たちはこうした小さな進歩一つ一つを重要な回復のステップとして捉えています。
家族支援において重要なのは、相談者自身のケアです。特に真面目な親御さんほど、現状を自分の責任だと考えて追い込んでしまう傾向があります。そのため、私たちは子どもの問題だけでなく、配偶者との関係や義理の親族との関係、実家の両親との関係など、家族を取り巻く様々な人間関係の悩みにも耳を傾けています。
多くの親御さんが「相談に行くと叱られるのではないか」「これまでの子育てを否定されるのではないか」という不安を抱えて来られます。むしろ、これまでの苦労や努力を十分に認め、ねぎらうことから始めます。相談の場では、これまでの努力を認め、ねぎらいながら、親御さんの気持ちに寄り添います。批判や否定をせず、一緒に解決策を考え、家族の強みを見つけ、それを活かしていく方向で支援を進めています。
小さな変化の積み重ねが生む家族の変容
ー具体的な支援の効果について教えてください。
蟇田さん:家族相談を利用される方々から多く聞かれる変化として、家庭内のコミュニケーションの改善があります。問題を抱えた家庭では、会話が少なくなったり、怒りの口調が増えたり、イライラが蔓延するという悪循環に陥りがちです。
しかし、声かけの方法を少し変えるだけで、大きな変化が生まれることがあります。例えば、それまで全く会話のなかった家庭でも、継続的な挨拶や感謝の気持ちを伝えることで、子どもから予想外の反応が返ってくるようになったという声を多くいただいています。
今後の展望と支援を検討される方へ
ーこれからの取り組みについて教えてください。
蟇田さん:コロナ禍以降、支援ニーズにも変化が見られ、特に不登校に関する相談が増加しています。オンライン授業への移行に伴い動けなくなってしまった大学生や、学校に通えなくなった児童・生徒の相談が目立つようになりました。これを受けて、約2年前から学校支援にも注力し、小学校、中学校、高等学校それぞれの年代に応じた関わり方を考慮しながら、支援内容を充実させています。
特に力を入れているのが、「第三の居場所」としての親子カフェの展開です。不登校の子どもを持つ親御さんから、「家でもなく学校でもない居場所が欲しい」という声が多く寄せられていることを受けて、新しい取り組みを学校などと連携して実施しています。
今後は、この親子カフェの取り組みを他の学校や地域にも広げていきたいと考えています。学校内での実施はもちろん、学校外の場所でも不登校の子どもたちとその家族が安心して過ごせる居場所づくりを目指しています。この取り組みを進めるにあたり、場所の提供や資金面での支援、さらには社員参加型の社会貢献活動として協力してくださる企業とのパートナーシップも積極的に検討しています。
最後に – 支援を検討されている方へのメッセージ
ー支援を検討されている方へメッセージをお願いします。
蟇田さん:子どもさんのことで問題を抱えているご家庭では、ちょっとしたボタンの掛け違いから悪循環に陥っていることが多いのです。家庭内で会話が減り、イライラが募り、モヤモヤや怒り、憤りが渦巻いている状態は珍しくありません。特に真面目な親御さんほど、この状況を自分のせいだと責めてしまい、自分を追い込んでしまう傾向があります。
しかし、そうした不安やモヤモヤを抱えることは、どのご家庭でもある当たり前のことなのです。それは重たい荷物を一人で背負っているようなもので、その状態で子どもをなんとかしようとしても、なかなか上手くいきません。まずは、そうした重荷から解放されることが大切です。
私たちの相談室では、子どものことだけでなく、「夫が分かってくれない」「義理の父母がうるさい」「実家の両親との関係」など、様々な悩みをお聞きしています。相談に来られる方の多くは、これまでにも色々な方法を試され、本当に頑張ってこられた方々です。私たちはその努力を否定したり、叱ったりすることはありません。むしろ、これまでの取り組みの中で良かったことを見つけ、一緒に新しい関わり方を考えていきます。
オンラインでも対面でも、まずはその重たい気持ちを話していただければと思います。そうすることで少し心が軽くなり、家に戻った時に新しい視点で状況を見られるようになります。親御さんが元気を取り戻すことで、不思議なことに、それまでひきこもっていた子どもが少しずつ変化し始めることもよくあります。
確かに、相談に行くことへの不安や躊躇いがあるかもしれません。しかし、今この記事を読んでいらっしゃるということは、きっと何かしらの変化を求めていらっしゃるのだと思います。どんな小さなことでも構いません。私たちは、あなたとご家族の新しい一歩を応援させていただきたいと考えています。いつでもお気軽にご連絡ください。
また、私たちはこの取り組みにご賛同いただける企業の皆様、場所の提供や資金面でのご支援、あるいは社員の方々と一緒に取り組める社会貢献活動として、ご協力いただける可能性がございましたら、ぜひお声がけいただければ幸いです。子どもたちの未来のために、皆様のお力をお借りできればと願っています。