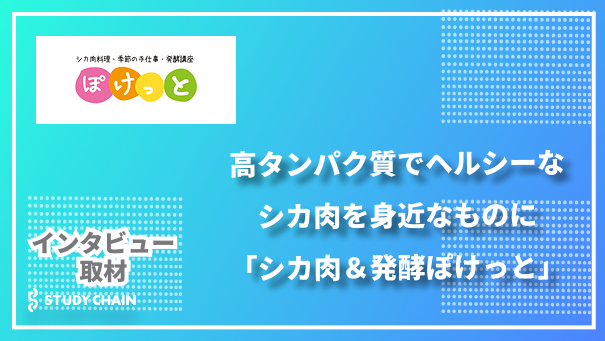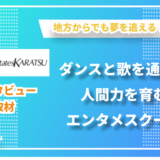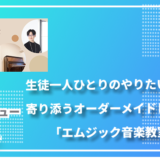縄文時代から日本人と共にあったシカ肉は高タンパク質で脂肪が少なく、健康志向の方に注目されている食材。
シカ肉の魅力を広めるべく料理教室を開催し、家庭で気軽に楽しめるシカ肉料理を提案する「シカ肉&発酵ぽけっと」の平岡祐子さんに活動や想いについてお話を伺いました。
シカ肉料理教室の誕生

ーどういった方を対象にどのような活動をされていますか?
平岡さん:一般の主婦の方向けにシカ肉の料理教室を開催しています。
ーこの教室を始められたきっかけや背景について教えていただけますか?
平岡さん:私はシカ肉がすごく好きだったのですが、周りで食べたことがない人が圧倒的に多かったというのと、シカ肉が美味しいとか、美味しくない以前に食べてもいいのかどうかという食肉としての認知がされていないことにショックを受けました。
鹿肉は食べてもいいし、むしろ食べた方が体にもいいしとても美味しいんだよ、ということを広めようと思い立ち、2019年に料理教室をスタートしました。
今は食肉処理業と販売業の免許を取得した施設で自ら捕獲、解体、精肉をして、料理教室を開催しています。
教室で学んだあと、その場でシカ肉を購入できるので、帰宅後すぐ実践し、身につきやすいと好評です。
ー先生ご自身がシカ肉に親しむきっかけは何だったのですか?
平岡さん:私の祖父が猟師で、幼い頃からシカ肉を日常的に食べていたので、その美味しさはずっと知っていました。
家庭で楽しめるシカ肉料理の魅力
ー教室としてのアピールポイントはどういったところでしょうか?
平岡さん:シカ肉料理というとフレンチだったりとか、すごく敷居が高いイメージがあると思いますが、私の料理教室は家庭料理。なじみのある食材や調味料で誰でも簡単に調理できます。
そして、「冷めても美味しい」というのが一番のポイントです。
レストランで食べる料理というのは「あたたかいうちに食べる」料理ですが、子育て中であったりとか、忙しいお母さんでは取り入れにくくなってしまいます。
冷めてる料理でも美味しい、そして冷めても硬くならない、時間がたっても味が落ちないというのが、うれしいポイントです。
また、オーブンや圧力鍋などの特別な調理器具も使わず、包丁とまな板と菜箸くらいのもので出来るよう、なるべく敷居を下げています。
冷めても美味しい料理にすることで、翌日にアレンジが効いたり、お弁当に入れることが出来たり、日常に取り入れやすいよう工夫もしています。
ジビエ、シカ肉というだけでもすごいハードルが高いのに、フレンチなどにしてしまうとどうしても取り入れにくいと思うので、すごくハードルを下げた調理法というのも料理教室の特徴です。
シカ肉の特徴

ーシカ肉の特徴について教えてください。
平岡さん:シカ肉の特徴はタンパク質が取れるのに、脂がほとんどないという点です。
牛肉であったり、大豆であったり、タンパク質を取ろうとすると脂が付いてくるものです。
その点に関してシカ肉は脂がほとんど無いので、良質な脂を別で取ってタンパク質だけを取ることができるというのが特徴です。
アスリートの方やダイエット中の方におすすめされています。
あとは鉄分が多いという特徴があり、貧血や冷え性などの女性にもおすすめです。
シカ肉料理教室に集まる生徒さん
ーシカ肉は高タンパク質でヘルシーというイメージがありますが、教室に通われている生徒さんはどういった世代の方が多いのですか?
平岡さん:シカ肉はタンパク質が非常に高いので、アスリートの方ですとか、ダイエット中の方、体を鍛えていらっしゃる方も多いです。
他にも、子供さんがスポーツをされているようなお母さんであったり、産前産後のお母さんであったり、牛肉アレルギーなどアレルギーをお持ちの方、オーガニック志向の方というのも多く来られています。
レッスンで大切にしていること

ーレッスンされる際に、大切にしていることや意識していることはありますか?
平岡さん:どうしてもお肉というひとくくりで考えると、牛肉や豚肉などと同じように考えてしまいますが、シカというのは
家畜と違い個体差があるものでして、年齢や性別、食べているものの趣味趣向、性格、顔つきまでもがが1頭1頭違うものです。
今このお肉を食べてみて、もう一度同じお肉を食べたいと思っても、もう二度と食べることができないのがシカ肉です。
もう同じお肉に出会うことはまずないので、「一期一会のお肉」という大切さをお伝えするようにしています。
提供しているコースとプラン
ー実際に提供されていらっしゃるコースやプランについて教えていただけますか?
平岡さん:1年に1回「まるごとシカ講座」というのをやっておりまして、5月から11月まで(8月はお休み)の月に1度の6回のコースになっています。
まず鹿の半身のカッティングをする講座が第1回目にあります。
生き物のカタチから、後ろ足の外もも肉、内もも肉・・・というように、一つ一つの部位の名前と形を確認しながら、骨から外していき、見慣れたブロック肉へカッティングします
食べ比べを行って、同じ個体から取ったお肉でも部位によって味が全然違うということを実感していただきます。
そして、それぞれの部位の特徴に合わせたお料理を学ぶコースが、2回目からスタートします。
低温調理法という火入れの方法を勉強しながらタンパク質の変異をお伝えしたり、揚げもの、煮もの、など
安全に火入れをしながら部位ごとに適した料理を習得していくコースを年に1回開催しています。
他にも、リクエストがあれば料理教室は2名から、開催日程以外でも受け付けています。
「まるごとシカ講座」に単発でご参加いただくことも可能になっています。
今後の展望

ー今後強化したいと考えていることや新たに取り組んでみたいことはありますか?
平岡さん:今は料理教室や鹿肉の販売など、食べることにフォーカスをしていますが、鹿を仕留めると、角であったり、骨であったり、皮であったりという部分もどうしても出てきてしまいます。
そちらをワークショップ形式で、シカの角や骨を使ったクラフト小物を皆さんと作っていくような教室であったり、体験会などを開催していこうと思っています。
今、レザーワークショップは開催していて、レザー小物を作る教室は好評です
読者へのメッセージ
ー最後に、教室に興味を持たれた方にメッセージをお願いできますか?
祐子:シカ肉というのは、馴染みがないお肉と思われがちですが、縄文時代から日本人が食べてきたお肉なんです。
日本人の身体にも、きっと合っているお肉だと思いますので、ぜひお料理教室を一度体験してみてください。