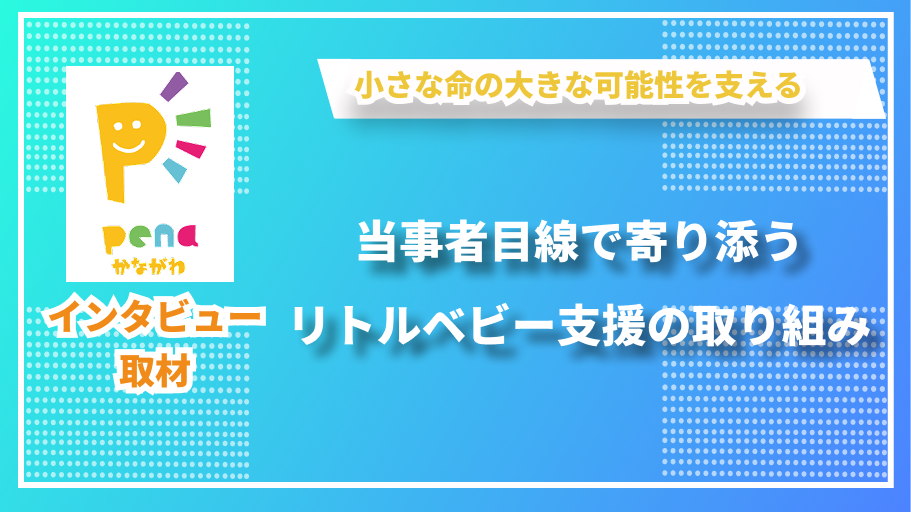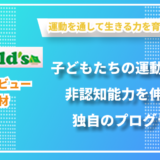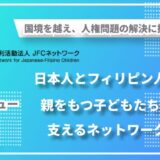神奈川県で、低出生体重児(リトルベビー)とその家族を支援する「NPO法人pena」。ご自身もリトルベビーの母である理事長の坂上さんに、団体設立の経緯や具体的な支援活動、そして目指す社会像についてお話を伺いました。
自身の経験から見えた支援の必要性

ー設立のきっかけについて教えてください。
坂上:私は2018年に第1子の女の子を、妊娠24週4日で370gという体重で出産しました。一般的な出産が妊娠40週前後、体重3000グラム前後であることを考えると、かなり早い段階での出産でした。
その経験の中で、母子手帳に1000g未満の記録を書く欄がないことや、発達の確認項目に全て「いいえ」と答えざるを得ないことなど、様々な場面で娘を否定しているような気持ちになりました。
また、早産になってしまったことへの自責の念も強く、ネガティブな感情を抱えながらの育児となりました。
娘が4歳くらいになった頃、全国で広がり始めていた「リトルベビーハンドブック」の神奈川県版を作りたいと考えました。
同じように悲しい思いをするママを一人でも減らしたい、そして娘に対する思いを綴った記録を残したいという願いから、2021年に「神奈川リトルベビーサークルpena」を立ち上げ、2024年4月にNPO法人化しました。
3つの柱で進める支援活動
ー具体的な活動内容について教えてください。
坂上:私たちの活動は、「当事者支援」「普及啓発」「行政への働きかけ」という3つの柱で展開しています。
当事者支援では、一般的な子育ての場では居場所を見つけにくい方々のために、オンラインや対面での交流会、グループLINEでの情報交換、勉強会などを実施しています。
育児書にもリトルベビーの子育てについての情報が少なく、悩みを相談できる相手が見つかりにくい現状があります。そのため、当事者同士が安心して交流できる場を提供することに力を入れています。
普及啓発活動としては、10人に1人が低出生体重児として生まれているという事実や、当事者が抱える困難について地域社会に理解を広げる取り組みを行っています。
何気ない言葉で傷つく当事者の気持ちを理解してもらい、小さく生まれても元気に頑張っている子どもたちを応援してもらえるよう、写真展の開催や学校での講演、SNSでの情報発信などを通じて、リトルベビーとその家族への理解促進に努めています。
行政への働きかけでは、2024年10月に神奈川県と連携協定を結び、搾乳環境の整備など具体的な支援策の実現に向けて活動しています。
例えば、外出先での搾乳場所の確保が大きな課題のひとつです。入院中の赤ちゃんに母乳を届けるためには、3時間おきの搾乳が必要です。
しかし、母親1人で授乳室を利用することに対して理解が得られず、中には不審な目で見られたり、トイレでの搾乳を余儀なくされるケースも少なくありません。
この課題に対し、搾乳可能な場所を示すシンボルマークとステッカーの配布を開始しました。この取り組みは国土交通省からも注目され、バリアフリーガイドラインへの反映が検討されるなど、社会全体を変える大きな一歩となっています。
法人化による新たな可能性
ー貴団体ならではの特徴について教えてください。
坂上:全国各地にリトルベビーサークルはありますが、法人化したのは私たちが初めてです。これにより、行政や企業とのパートナーシップを構築し、より実効性のある支援を実現できるようになりました。
神奈川県との連携協定締結や制度への反映など、サークル単位では難しかった取り組みが可能になってきています。
今後は相談支援事業を開始し、一人ひとりにより寄り添った支援を展開していく予定です。孤独に悩む当事者に「一人じゃないよ」というメッセージを届け、必要な時にいつでも頼れる存在でありたいと考えています。
多様性を認め合える社会づくりを目指して
ー活動において大切にしていることを教えてください。
坂上:リトルベビーという共通点はあっても、それぞれの経験や状況は千差万別です。特別な支援を必要としない方もいれば、様々な医療的ケアが必要な方もいます。
そのため、一人ひとりの声に耳を傾け、その方のニーズに合った支援を心がけています。
当事者同士のサポートは、必ずしも答えを見つけることが目的ではありません。時には一緒に悩み、共感し合い、それぞれの経験を共有することで、互いに支え合える関係を築いていきたいと考えています。
私たちの団体名「pena」には、絵の具という意味があります。それぞれの色が独立しながらも、混ざり合うことで新しい色を生み出すように、一人ひとりの個性を大切にしながら、共に支え合える社会を作っていきたいと考えています。
活動を応援くださるサポーター(賛助会員)を募集していますので、詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。
ー最後に、読者の方に向けたメッセージをお願いします。
坂上:小さく生まれて育っている赤ちゃんは10人に1人で、実は皆さんの身近にもいるかもしれません。それぞれのご家庭に、出産や子育ての物語があります。
地域の皆さんには、一人ひとりの個性を受け入れ、共に笑顔で過ごせる社会づくりにご協力いただければ幸いです。