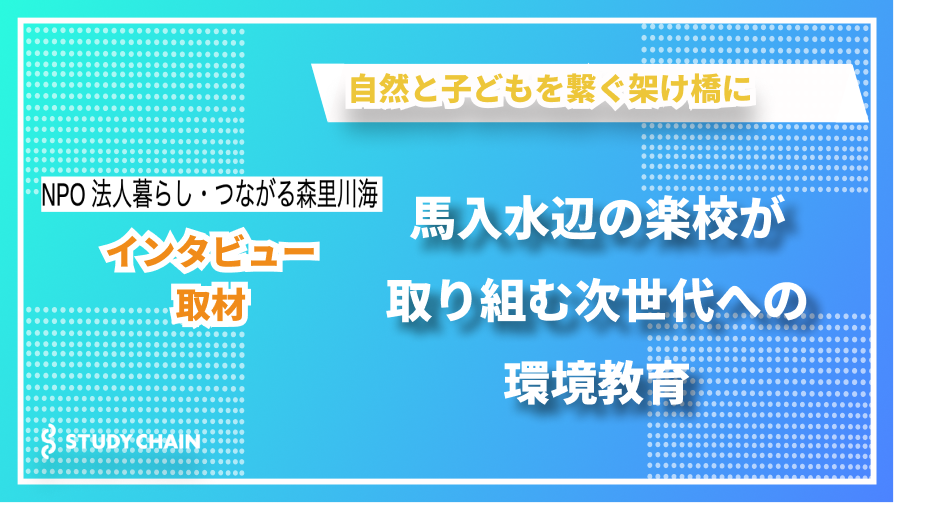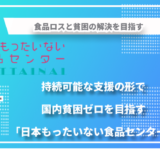相模川下流域の「馬入水辺の楽校」を拠点に、環境保全活動と自然体験学習を25年以上実施する、NPO法人暮らし・つながる森里川海。子どもたちの自然離れが進む中、五感を通じた体験学習を提供し、地域の環境教育の拠点として活動を続けています。
同法人の活動内容や今後の展望について、臼井さんにお話を伺いました。
不法投棄の場所から自然体験の場へ

ー団体の概要と活動内容についてお聞かせください。
臼井:活動の拠点は、相模川下流域の馬入川にある「馬入水辺の楽校」です。この場所を中心に、環境保全活動や環境教育を行っています。
2001年4月の設立以前は、この場所の大部分が駐車場や不法投棄の場所でした。1998年頃から行政と市民団体で協議会を作り、自然とのふれあいの場づくりをスタートし、2001年4月に馬入水辺の楽校をオープンしました。
子どもたちの自然離れに向き合う
臼井:自然と触れ合える場を作れば子どもたちが自然と遊びに来るだろうと考えていましたが、実際にはそうはならず、なぜ子どもたちが遊び場に来ないのかを考えました。
調査によると、日の出や日の入りを一度も見たことがない、昆虫採集を一度もしたことがない子どもたちが多くいることが分かりました。
何とかしなければと考え、環境学習活動により力を入れ、生き物調べや川の自然楽校などのイベントを開催しました。現在では年間80回ほどのイベントを実施し、多い時で年間3000人ほどの市民が参加してくれるようになりました。
五感を育む体験を重視
ー馬入水辺の楽校ではどのような活動を行っているのでしょうか。
臼井:活動の特徴は、単に見るだけでなく五感を通じた体験を重視していることです。
川での活動では年2回ほどライフジャケットを使用した水難事故防止訓練を実施しています。現代の子どもたちは川で遊んだ経験がほとんどないため、安全に自然と触れ合える機会を提供しています。
生き物の生息環境を整備する活動として、ビオトープやバタフライガーデンづくりなども行っています。子どもたちは実際に生き物の住処を作ることで、自然環境への理解を深めています。
農業体験では、農薬や化学肥料を使用しない安全な農作物づくりを通じて、食の安全や環境について学ぶ機会を提供しています。
里山の落ち葉を集め、昔ながらの農法である踏み込み温床を作ったり、芋掘りと火起こし体験では収穫から火の起こし方、さつまいもの焼き方、火の消し方までを教えています。
運動の輪を流域へ広げる環境教育活動
ー他の団体にない特徴や独自の取り組みについて教えてください。
臼井:私たちは流域全体での環境教育活動を目指しています。海では海岸清掃やビーチコーミングや相模湾の自然を肌で感じるネイチャーウォッチングクルーズを行い、上流では山梨県の子どもたちと交流する桂川・相模川上下流交流会なども実施しています。
馬入水辺の楽校をフィールドミュージアムとして発展させ、年間を通して環境学習や自然体験ができる場所にしたいと考えています。
この地域には環境教育活動や自然体験ができる場所が少ないため、長期的な視点で運営できる仕組みづくりを目指しています。企業や行政、市民団体が連携して支える、持続可能な運営モデルを構築したいと考えています。
安全管理と次世代育成の課題
臼井:活動を通じて最も重視しているのは安全管理です。川に入る際は全員がライフジャケットを着用し、保護者にも安全管理のサポートをお願いしています。
危険な場所や生き物についての説明も丁寧に行い、安全に自然と触れ合える環境づくりに努めています。
一方で、現在の課題は人材育成です。小学生の参加は多いものの、中学生以上の参加が少なく、また、運営を担う若い世代が不足しています。これは多くのNPO団体が抱える共通の課題でもあります。
そこで、会員参加型・会員主導型の運営に移行を進めており、例えばバタフライガーデンの企画運営を参加者に任せるなど、次世代への引き継ぎを意識した取り組みを行っています。
また、有償ボランティアの導入なども検討し、時代に合わせた運営形態を模索しています。
深刻化する環境問題への関心を育む
ー最後に、記事をご覧になる方へメッセージをお願いします。
臼井:長年の野鳥観察や農業の経験から、身の回りの自然環境が急速に失われていることを実感しています。
かつて普通に見られたスズメやツバメ、ニホンミツバチなどが激減し、田んぼに普通にいたトノサマガエル(トウキョウダルマガエル)はほとんど見られなくなりました。
しかし、多くの人々は自然との距離が遠くなり、この状況を実感できていません。鳥のさえずりが聞こえていても気づかず、ツバメが飛んでいても目に入らないほど、自然との関係が希薄になっています。
私たちは難しいことは言わず、まずは自然の素晴らしさを体感してもらうことを大切にしています。子どもたちが自然と触れ合い、楽しみながら学べる場を作り続けることで、環境問題への関心を育てていきたいと考えています。
最も嬉しいのは、街で会った子どもたちが声をかけてくれることです。それは私たちの活動が子どもたちの心に残っている証であり、これからも活動を続けていく励みとなっています。