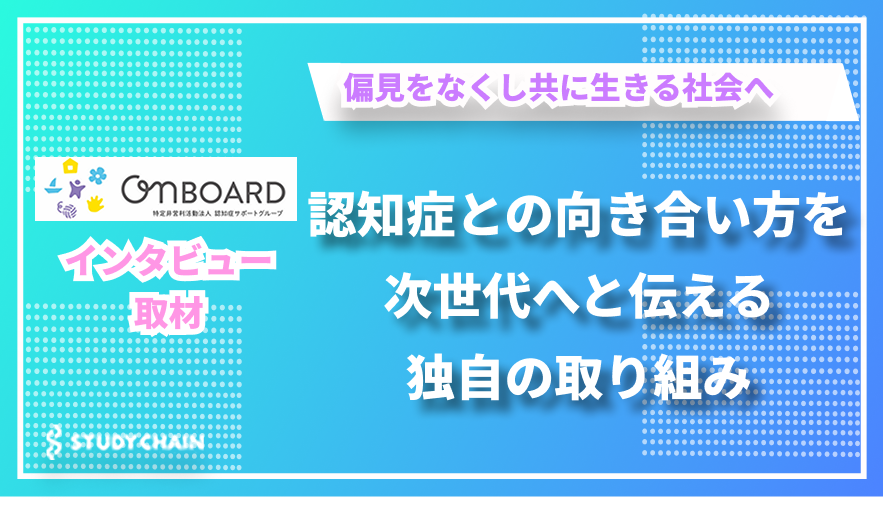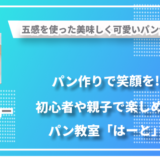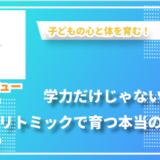認知症に対する正しい理解を広めるため、小中高生向けの教育プログラム「認知症フレンドリーキッズ事業」と、手作りのマフを通じた地域づくり「認知症マフ」の取り組みを実施する、特定非営利活動法人認知症サポートグループONBOARD。
理事長の山本さんに、活動への想いや今後の展望についてお話を伺いました。
認知症の人と共に暮らせる社会の実現を目指して

ー団体の概要について教えてください。
山本:認知症サポートグループという名前の通り、認知症になってもこれまで通りの生活を送れる社会の実現を理念として掲げています。
2024年1月に施行された認知症基本法は、認知症の方への差別や偏見をなくし、共に支え合って活躍できる社会を作ることを目指しています。
私たちも同じ理念のもと、認知症という状態を広く理解してもらい、認知症になることは人生の終わりではないということを伝える活動を行っています。
重要なのは、認知症と診断されたからといって、その瞬間から生活が一変するわけではないということです。前日まで友人と楽しく過ごしていた方が、診断を受けたからといって突然寝たきりになるわけではありません。
同じ生活を続けながら、必要に応じてサポートを受けることで、充実した日々を送ることができるのです。
独自の二本柱で展開する啓発活動
ー活動の内容について詳しく教えてください。
山本:主な事業は2つあります。1つは「認知症フレンドリーキッズ事業」です。これは、偏見のない子どもの時期に認知症について正しく理解してもらうための教育プログラムです。
前半では認知症の基礎知識を学び、後半では具体的な事例をもとにグループワークを行い、例えば小売店なら店舗のデザインや接客方法などの解決案を考えて発表します。小学生から高校生まで対応可能で、福祉系高校での採用も目指しています。
もう1つは「認知症マフ」事業です。手を通す防寒具であるマフを作り、認知症の方に届ける活動です。単にニット製品を作るだけでなく、マフを通じて地域のネットワークづくりを行い、認知症への理解を深める取り組みとなっています。
作成したマフは、高齢者施設や病院に寄贈され、認知症の方の心の安らぎにつながっています。
認知症マフの参加者は、編み物に関心のある方が約半数、残り半数は社会貢献やボランティア活動に興味がある方です。社会貢献したいという気持ちはあっても、具体的に何をすればよいか分からない方にとって、明確なテーマ設定になっています。
ー団体設立の経緯について教えてください。
山本:2014年から朝日新聞厚生文化事業団の大阪事務所長として、認知症の啓発に携わったことが活動のきっかけでした。2016から2017年にかけて、認知症マフの普及活動と認知症フレンドリーキッズ事業を本格的に展開しました。
認知症マフについては、2016年のイギリスでの認知症施策視察時にトゥィドルマフと出会い、活動の中に導入しました。その後、NHKのEテレにも出演経験のあるニット作家が理事として参画するなど、体制を強化してきました。
2022年の定年退職後、これらの活動の可能性をさらに追求するため、ONBOARDを設立して継続しています。
他にない独自の取り組みで認知症への理解を促進
ー貴団体ならではの取り組みについて教えてください。
山本:小学生向けの認知症啓発活動は、ほとんど例がありません。
厚生労働省が推進する認知症サポーター養成講座も最近では子ども向けの事業を始めていますが、そちらが認知症の方との接し方を教える対処療法的なアプローチなのに対し、私たちは差別と偏見をなくし地域共生社会を築くことを重視しています。
認知症基本法が目指す「認知症の方と共に暮らす社会」の実現により沿った内容だと自負しています。
子どもたちの興味を引き出す工夫
ー活動を行う際に特に意識していることはありますか?
山本:子どもたちに興味を持ってもらうことを第一に考えています。例えば、地域の人口や高齢化率のデータを使って、認知症の人の数を一緒に計算するなど、インタラクティブな内容を心がけています。
講座として一方的に話すのではなく、子どもたちに考えてもらい、感想や答えを引き出すような仕掛けを常に意識しています。
具体的には、その地域の実情に合わせた数字を使用し、「高齢者の7人に1人が認知症と言われているが、この地域では何人くらいの方が認知症なのだろう」といった具体的な問いかけを行います。
このように、身近な問題として認識してもらうことで、より深い理解につながっています。
より広い層への啓発活動を目指して
ー今後、さらに強化していきたい部分について教えてください。
山本:小学生向けの活動を最優先としながらも、福祉系高校の生徒たちへの展開も考えています。
実際の介護現場では「認知症だから」という偏見が残念ながら存在します。将来の介護職を担う高校生には、より深い認知症への理解を持ってほしいと考えています。
また、大人向けの啓発活動も重要です。「認知症になりたくない」「不摂生が原因で認知症になる」といった誤った認識を持つ方も多く、正しい理解を広めていく必要があります。
加齢に伴って発症する可能性のある認知症について、予防できないものを予防しようとする誤った考えが広まっていることも課題です。
ー最後に、読者へのメッセージをお願いします。
山本:認知症は人生の終わりではありません。認知症になっても、これまで通りの生活を自分の住みたい町で続けていくことができる社会の実現を目指して、これからも活動を広げていきたいと考えています。