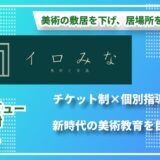LGBTQの人々が安心して過ごせる場所を作り、一人一人が自分らしく生きられる社会を目指して活動する認定NPO法人虹色ダイバーシティ。2013年の法人化以来、調査研究やアドボカシー活動を通じて、着実に支援の輪を広げています。今回は、様々な活動や取り組みについて同団体の長野さんにインタビューしました!

LGBTQに関する活動を中心に、多様な取り組みを展開
ー御団体の活動内容について教えていただけますでしょうか?
長野さん:私たちの活動はLGBTQ(性的マイノリティー)への支援活動が中心です。団体のミッションとして「Bridging the gaps for diversity and inclusion」を掲げており、性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)による格差のない社会を作ることを目指しています。
主な活動は、「認定NPO法人虹色ダイバーシティ」としての活動と、常設LGBTQセンター「プライドセンター大阪」の運営の2つに大きく分かれます。虹色ダイバーシティとしては、企業向けのLGBTQ研修やコンサルティング、調査研究、アドボカシー活動などを行っています。
特に調査研究では、毎年当事者の声を集めた「niji VOICE」という大規模なアンケート調査を実施し、その結果を「NIJI BRIDGE」というサイトで公開しています。また、全国のパートナーシップ制度の共同調査も行っており、2024年6月28日時点で459自治体、人口カバー率85.1%に達しています。
常設のLGBTQセンターとして、安心できる居場所を提供
ープライドセンター大阪について教えて下さい。
長野さん:常設LGBTQセンター「プライドセンター大阪」は、2022年4月に大阪・天満橋にオープンし、40人程度が集まれるスペースで週4日開館しており、LGBTQを含むどなたでも無料で利用できる場所となっています。
センター内には750冊以上の書籍や漫画を備え、カードゲームやボードゲームなども用意しています。また、スタッフとの会話や、LGBTQに関するイベント情報の提供、個別相談なども実施。相談は対面とオンラインの両方で受け付けており、公認心理士や臨床心理士などの専門家が45分程度、無料で対応しています。
代表の経験から始まった職場におけるLGBTQの課題解決
ー設立のきっかけについて教えていただけますでしょうか?
長野さん:2013年の法人化当初は、主に「職場とLGBTQ」というテーマで活動を始めたのですが、その背景には代表の村木がレズビアンの当事者として、職場での居心地の悪さを経験し、転職を繰り返した経験と聞いています。
その後、イギリスのNPOなどを研究する中で、LGBTQ当事者が職場で抱える困難は日本でも海外でも共通していることに気づき、日本でもこの課題を解決していくことを決意。当時はまだLGBTQという言葉自体が社会に浸透していない状況でした。
大阪を拠点とした包括的な支援体制を実現
ー御団体ならではの強みやアピールポイントを教えてください。
長野さん:LGBTQの支援活動を行う団体は全国にありますが、特に東京以外の地域では、本業の傍らで活動している団体が多い状況です。その中で私たちの特徴は、常勤スタッフを採用し、安定した体制で活動できている点です。
また、学生インターンも積極的に受け入れており、ジェンダー平等やSDGsに関心のある学生たちが東京と大阪の拠点で活動をサポートしています。大阪を拠点とする団体として、これだけ多様なプロジェクトを展開している例は非常に少なく、それが大きな強みとなっています。
それ以外にも、大阪・天満橋という地域性を活かした「プライドクルーズ大阪」という取り組みがあります。プライドパレードを船上から行うという日本で唯一の取り組みで、地域と共に活動を盛り上げています。常に新しいチャレンジを実現させていく姿勢が、私たちの団体の大きな特徴です。

当事者に寄り添い、安心できる環境づくりを重視
ー利用者と接する際に意識していることを教えてください。
長野さん:プライドセンター大阪では、当事者の方だけでなく、パートナーの方やご家族の方も多く来館されます。特に親御さんからの相談も増えているのですが、誰もが安心して過ごせる場所、相談できる場所であることを最も重視しています。
また、私たちの活動は単にLGBTQの課題だけではなく、様々な社会課題と繋がっています。例えば、代表の村木自身がレズビアンの女性リーダーとして、また子育ても行っているように、複数のマイノリティ性を持つ方々も多くいらっしゃいます。そういった方々の声に耳を傾け、それぞれの課題に丁寧に向き合うことを心がけています。
多様な価値観や生き方を互いに認め合える環境づくりを通じて、LGBTQの課題解決が、より良い社会づくりにつながっていくと信じて活動を続けています。
教育プログラムを通じて、次世代の「チェンジメーカー」を育成
ー今後の取り組みについて教えてください。
長野さん:私たちは昨年、LGBTQに関する新しい教育プログラムを立ち上げ、その内容を20ページに及ぶ冊子にまとめました。このプログラムでは、プライドセンター大阪を拠点に、主に中高生を対象とした「LGBTQセンターで学ぶ社会を変えるはじめの一歩」というプログラムを展開しています。
具体的には、修学旅行や教育旅行の受け入れ先として、全国から訪れる学生たちにLGBTQについての理解を深めてもらうというプログラムです。このプログラムを通じて、性の多様性や社会を変える仕組みについて学び、自分たちにできることを考えてもらう機会を提供しています。
私たちが特に重視しているのは、この学びを一過性のものにしないということです。参加した学生たちには、自分たちの学校や地域に戻った際に「チェンジメーカー」として活動してもらうことを期待しています。例えば、学校でLGBTQについての理解を広める活動を始めたり、地域でのイベントで発信したりするなど、それぞれの場所で変化を生み出すきっかけづくりを担ってほしいと考えています。
誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けて
ー最後に、記事を読んでいる方へメッセージをお願いします。
長野さん:LGBTQも過ごしやすい社会を作っていくだけでなく、多様な価値観や考え方を認め合える環境づくりは、すべての人にとって暮らしやすい社会の実現につながります。
具体的な行動の第一歩として、「アライ(Ally:LGBTQの課題に自分事として取り組む人)」になることを目指していただきたいと思います。まずは映画やドラマ、書籍などを通じて知ることから始めていただければと思います。また、LGBTQの象徴である6色の虹をシンボルとしたアイテムを身につけることで、当事者の方が安心して相談できる存在であることを示すこともできます。
また、日常生活の中で、ハラスメントになるような言動に気づいた際には、お互いに指摘し合える関係性を築いていくことも重要です。実際のデータでも、アライが可視化されている職場は、心理的安全性が高いと回答する人が多いです。
私たちは、LGBTQの課題解決が、より良い社会の実現につながると信じています。一人一人が「自分にできること」を考え、行動に移していくことで、徐々に変化は生まれていきます。今この記事を読んでくださっている皆さまも、ぜひ自分なりのアクションを始めて、社会をよりよく変えていく「チェンジメーカー」を目指していただければ幸いです。