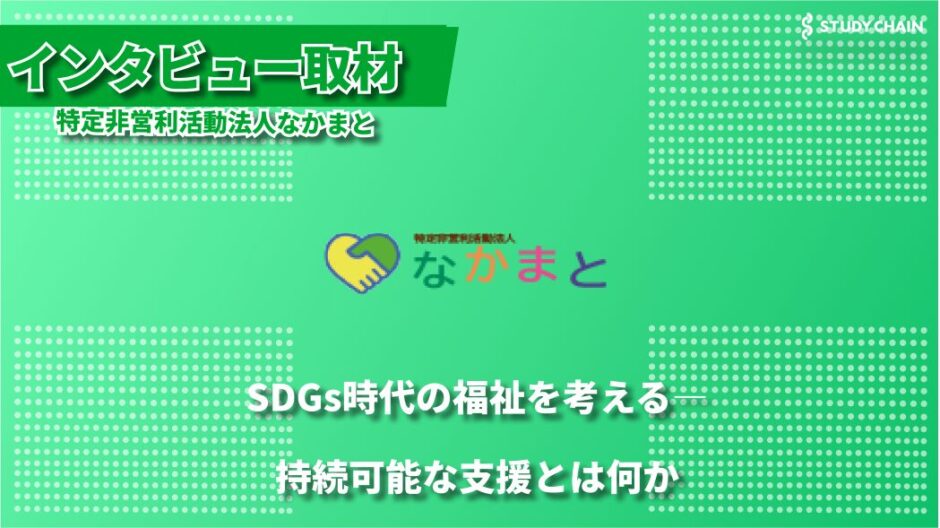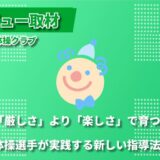『特定非営利活動法人なかまと』は、長野県で障害者就労支援事業所を運営する福祉法人です。設立から21年、強度行動障害者への支援や就労支援など、独自の取り組みを続けてきました。そして今、「差別のない社会」の実現を目指し、新たな一歩を踏み出しています。今回は理事長の梶山さんに、障害者支援にかける思いと、これからの展望についてお話を伺いました。

事業概要と支援内容
ー御社の事業内容とサービス概要について教えていただけますでしょうか?
梶山さん:主に障害を持った方に対する就労継続支援B型事業所を運営しており、地元企業の下請け作業を中心に、工賃は長野県の平均を大きく上回る水準を維持しています。
具体的な作業内容は、ニデック社のサーボモーター用ブラシの組立などの精密機械部品の作業や、カタログギフトの箱詰め、地元食品会社での蕎麦の包装作業などです。利用者の方々の能力や適性に合わせて、適切な作業を提供できるよう心がけています。
設立の経緯と時代背景
ー創立21年とのことですが、当時の状況や設立のきっかけを教えていただけますでしょうか?
梶山さん:設立当時は障害者総合支援法が施行された時期で、500人から600人という大規模な施設に障害者が収容されている状況が一般的でした。しかし、国連障害者人権委員会から人権の観点で厳しい指摘を受け、大規模施設の閉鎖が進められることになりました。
そこで大きな課題となったのは、閉鎖後の受け皿となる施設が十分に整備されていなかったことです。障害を持つ方々が生まれ育った地域で、安心して暮らしていける環境づくりが急務でした。そうした社会的背景から、地域での受け入れ体制を整えるために私たちは事業を開始したのです。
現状の課題と取り組み
ー就労支援事業所の現状について、どのような課題を感じていらっしゃいますか?
梶山さん:就労継続支援には、A型とB型という2つの形態があります。A型事業所は一般企業により近い形態で、最低賃金が保障される一方、より高い就労能力が求められます。この A型事業所は3年前から増加傾向にありましたが、現在大きな転換期を迎えています。
具体的には、社会保険の加入基準となる130万円の壁の問題があり、来年にはさらに70万円程度まで下がる可能性が指摘されています。これにより、A型事業所の運営が経済的に困難となり、残念ながら閉鎖に追い込まれるケースが増えているのが現状です。
こうした状況の中、特定非営利活動法人なかまとのB型事業所では、9時半から4時半までの約7時間の就労時間で、最高で月7万5千円程度の工賃を実現しています。A型での就労が難しい方でも、短時間勤務で働ける環境を整備することで、それぞれの方に合った就労機会を提供できるよう努めています。
特徴的な支援体制
ー御社ならではの特徴や強みについて教えていただけますでしょうか?
梶山さん:特定非営利活動法人なかまとの最大の特徴は、B型事業所に加えて生活介護事業所も運営している点です。両方の機能を持つ多機能型事業所を3カ所展開しており、利用者の方々の多様なニーズに応えられる体制を整えています。
特筆すべき点として、生活介護を利用される方の約半数が強度行動障害の方々という点が挙げられます。知的障害を伴うASDの方々で、他者とのコミュニケーションに困難を感じられたり、時には自身の気持ちをうまく表現できずに手を挙げてしまうこともあります。そのため、専門研修を受けた職員が常駐し、社会適応訓練や穏やかに過ごすための支援を丁寧に行っています。
また、住まいの支援として、グループホームを4カ所、認知症対応型グループホームを1カ所運営しています。私自身は理事長でありながら計画相談員も務めており、利用者一人一人の幸せな生活のための支援計画を立案しています。医療機関やヘルパーと緊密に連携しながら、包括的な支援を実現しています。
利用者との関わり方
ー利用者の方々とコミュニケーションを取る際に、どのような点を意識されていますか?
梶山さん:支援において最も基本的かつ重要なことは、「あるべき論」を完全に捨てることです。利用者一人一人の立場や考え方、目指す方向性は千差万別です。支援者側の「こうあるべき」という価値観を押し付けることは、かえって強い反発を招くことがあり、場合によっては、それが虐待とみなされる可能性すらあります。
そのため、私たちは常に利用者の視点に立ち、その方の言葉や表情、しぐさから真の思いを理解しようと努めています。時間をかけて対話を重ね、信頼関係を築きながら、その方が望む生活の実現に向けて一緒に歩んでいくことを心がけています。
持続可能な支援を目指して
ー今後の展望や取り組みについてお聞かせください。
梶山さん:私たちが最も重視しているのは、持続可能な運営体制の確立です。支援を必要とする方々が路頭に迷うことのないよう、しっかりとした運営基盤を築くことが何より重要だと考えています。
特に、強度行動障害者への支援は今後の重要な柱として位置付けており、専門性の高いこの分野での支援体制をさらに拡充していく予定です。
また、SDGs推進企業として認定を受けたことを契機に、現在は認定NPO法人の取得も目指しています。年間100人から3000円の寄付を3年間集めることで認定を受けることができ、これにより企業からの寄付が税控除対象となります。国からの給付金に頼るだけでなく、自立的な運営基盤を確立し、従業員への還元も実現していきたいと考えています。
社会的理解の促進に向けて
ー最後に、記事を読まれている方へメッセージをお願いいたします。
梶山さん:日本社会における障害者の人権に対する理解は、残念ながらまだまだ発展途上にあると感じています。身近に障害のある方がいる人々は深い理解を示してくれますが、そうでない方々への理解促進が大きな課題となっています。
最近では、TikTokなどのSNSで軽度の知的障害を持つ方々が積極的に情報発信を行うなど、少しずつ理解は広がりつつあります。しかし、まだ道半ばというのが現状です。実際グループホームの移転に関する住民説明会を開催した際には、「そのような施設ができては平穏な生活が脅かされる」といった反対意見が出されるなど、地域での理解促進は依然として大きな課題となっています。
こうした状況を少しでも改善するため、特定非営利活動法人なかまとでは常時ボランティアを受け入れています。学生や地域の方々との交流を通じて、障害を持つ方々への理解を深めていただければと考えています。例えば、アルミ缶の回収活動への協力や、散歩の付き添いなど、できることから始めていただければ幸いです。
私たちは、一人一人が互いの違いを認め合い、共に生きていける社会の実現を目指しています。それは一朝一夕には実現できないかもしれませんが、こうした地道な活動を通じて、少しずつでも前進していきたいと考えています。差別のない社会の実現に向けて、今後も活動を続けていく所存です。