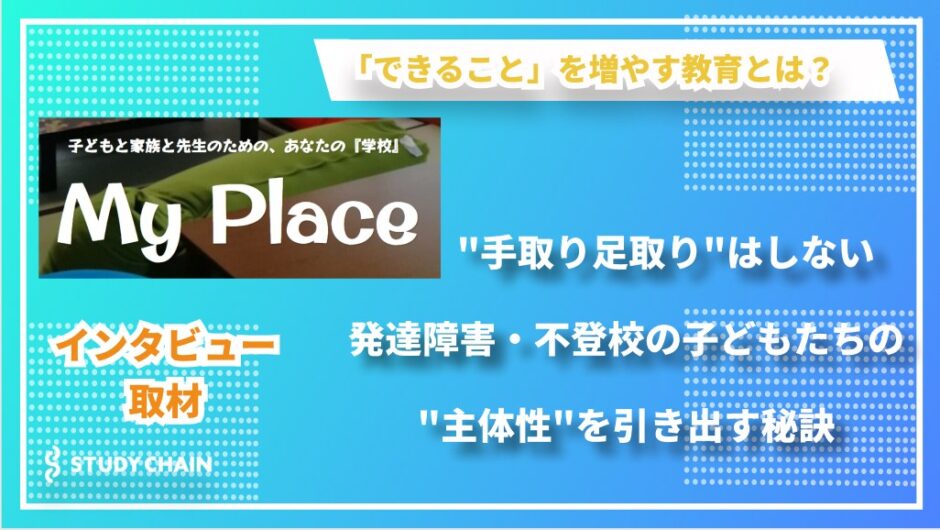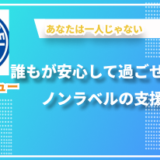不登校、発達障害、学習の遅れ…。子どもたちを取り巻く教育の課題は、年々多様化・複雑化しています。そんな中、従来の教育の枠組みにとらわれない新しいアプローチで、子どもたちの成長をサポートする施設が注目を集めています。
兵庫県に拠点を置く家庭学習応援施設 My Placeは、フリースクールと通信制高校サポート校を運営。元小学校教員の経験を持つ代表の池田謙之氏は、「社会に繋がる力を育てる」という理念のもと、独自の教育メソッドを実践しています。
画一的な指導ではなく、一人ひとりの特性や状況に合わせた支援を提供し、さらに「本人が動かないと面白くない場所」を意図的に作り出すことで、子どもたちの主体性を引き出していく。その革新的な取り組みについて、池田氏にお話を伺いました。
社会に繋がる力を育てる場所として

ー本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずは、家庭学習応援施設 My Place(マイ プレイス)の概要について、対象としているお子さんや指導方針をお聞かせください。
池田:弊施設では小学1年生から高校3年生までを対象としています。フリースクールは中学1年生から中学3年生まで、通信制高校サポート校では高校生を受け入れており、さらにスタッフやスペースを工夫することで放課後等デイサービスも実施しています。障害をお持ちの方もそうでない方も、様々な経験を持つ子どもたちが共に過ごしています。
私は以前、小学校教員をしていました。学校の中では学習指導要領に基づいた指導が基本となりますが、今の社会に求められている力として、横並びの教育だけではなく、その子その子に合った、将来に結びつく力も必要だと考えています。それは場合によっては学力であったり、コミュニケーション力であったり、障害をお持ちの方であれば、それを周囲に理解してもらうスキルであったりします。
社会が変わるのを待って自分が変わらないよりは、自分が変われば社会でより幸せになれる可能性が拡がるという考えのもと、社会に繋がる力を育てることを大きな目的として、様々な子どもたちと関わっています。
教育の本質を見つめ直す
ー池田様がこのサービスを始められた経緯について、お聞かせください。
池田:教育には様々な課題があります。子どもの権利は拡大し、それ自体は正しいことですが、一方で逃げ道が無数に存在し、何も解決しないまま小中学校を過ごしていく子どもたちが多くなる可能性があるという課題意識がありました。
例えば、中学校の教科担任制で一部の先生との関係が原因で不登校になるケースがあります。しかし、学校内部にいた経験から、そういった事例には往々にして別の側面があることも知っています。つまり、個人にフィットしたサービスではないということが本質的な問題なのです。
教育は本来、不自然な営みです。野生の動物は勝手に育つのに、人間は何かを教えるということを当たり前のようにしています。そうなると逃げたくなったり、反発したくなったりするのは自然なことです。しかし、それが本当に克服できないことなのか、あるいは適切なアプローチを見つければ乗り越えられることなのか、それを見極められる教育のプロフェッショナルが必要だと考えました。
公立小学校の教員時代、担任する子どもが私のことを嫌だと感じた時、拠り所がなくなってしまうのではないかと考えました。しかし、私たちは民間だからこそ、「こういった教育はどうですか?」という提案ができる。社会に繋がる力を育てるという意図で来てくれる人たちに対して、様々な選択肢を提供できる場所を作りたいと考えました。
主体性を育む独自のアプローチ
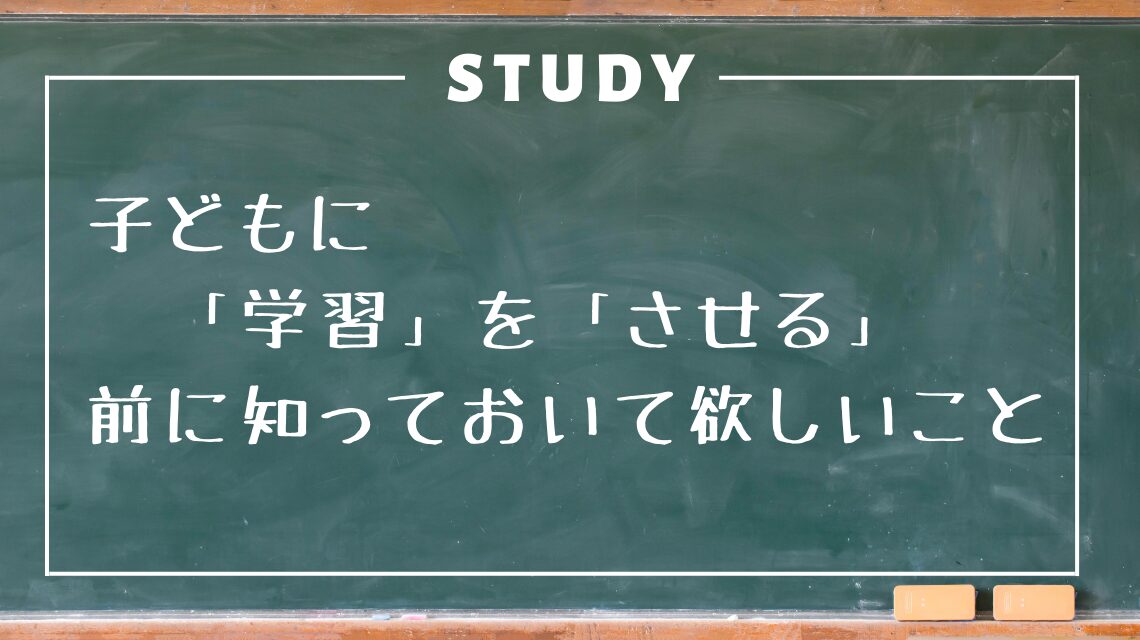
ー他のサービスにはない、My Placeならではの特徴やアピールポイントについて教えてください。
池田:私たちは「家庭学習応援施設」という言葉を使っています。この言葉には重要な意味があります。教育者としてできることは、結局のところ「応援」だけだと考えているからです。本人に意欲がなければ、どんなに良いことを教えようとしても身につきません。
そこで私たちは、本人が動かないと面白くない場所を徹底的に作っています。例えば、学校では教師が積極的に声をかけ、支援する場面が多いですが、私たちの施設では、その子の状況に応じて適切な距離感を保ちます。
興味深いことに、障がい特性の重い子どもよりも、軽い子どもの方が「何をしていいか分からない」という問題に直面することが多いのです。学校の中では特に問題なく過ごせても、様々なことを求められると対応できなくなってしまう。かといって「自由にしていい」と言われても、何をすればいいか分からない。
そこで私たちは、デジタル機器の使用を制限するなど、あえて選択肢を限定することで、自分で考え、行動する力を育てています。これは一見すると乱暴に見えるかもしれませんが、常に大人が「こうした方がいい」「ああした方がいい」と指示し続けても、社会に出た時に自立できなくなってしまいます。
可能性を広げる指導方針
ー施設を利用されている方への指導で特に意識していることはありますか?
池田:私たちは「できること」を増やすことを重視しています。発達障害の概念は近年、非常に広がってきています。診断の有無に関わらず、様々な特性を持つ子どもたちがいます。できないことを認めるだけでなく、できることを増やしていく。
タイミングが早すぎる場合は様子を見ることもありますが、「これができるまで次に進めない」というアプローチはとりません。定期的に挑戦する機会を設け、できる部分を見つけ、伸ばしていく。それは教科教育の認知能力だけでなく、運動能力や社会性、非認知能力など、あらゆる面での成長を目指しています。
柔軟な学びの場を提供
ーMy Placeのコースやプランについて教えてください。
池田:フリースクールは火曜日・木曜日の週2回、午前10時スタートで月額3万円です。通信制高校サポート校も同様のスケジュールで月額3万円となっています。通信制高校については本校への学費が別途必要となります。
現在、通信制高校サポート校では島根県にある明誠高等学校と提携しています。在籍している生徒の学習と生活のサポートを行い、高校卒業資格の取得を支援しています。
また、私たちはNPO法人として運営しており、様々な取り組みを行っています。例えば人気YouTuberの「なつめさんち」を招いてのイベントは、普段外部との交流が少ないお子さんたちにとって貴重な経験となりました。こうした企画は、生徒との日常的な会話から生まれることが多く、彼らの興味関心に寄り添った形で実現しています。
未来への展望
ー今後、より強化していきたい点について教えてください。
池田:人とのつながりをより重視していきたいと考えています。社会で活躍されている方との出会い、同じ場所で生活を共にする仲間との関係など、様々な「人」との関わりが重要です。ただし、誰でもいいわけではありません。個々の子どもたちに合った、適切な関係性を築けるような環境づくりが必要です。
私たちは「子どもとその家族と学校の先生を救える場所にしたい」という思いで始めました。民間だからこそできる柔軟な取り組みを通じて、より多くの方々に安心できる場所を提供していきたいと考えています。
昨年には自分たちでクラウドファンディングを実施し、プライベートな打ち上げ花火大会を開催しました。こうした楽しいイベントの裏には、日々の努力があります。暗黙の了解が分からず悩んだり、新しいことへの挑戦に苦労したりする子どもたちが、一歩一歩前進している姿を、もっと多くの人に知ってもらいたいと考えています。
メッセージ
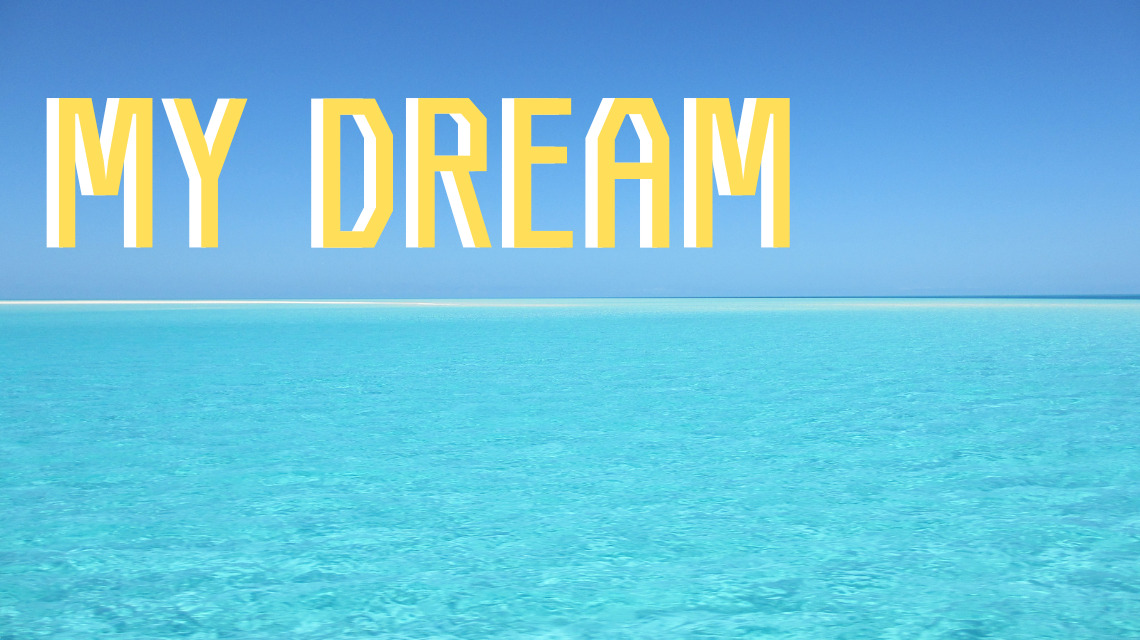
ー最後に、利用を考えていらっしゃる方へメッセージをお願いします!
池田:自分の生活を変えるのは自分自身です。しかし、方法が分からない、きっかけが得られないという方も多いと思います。自分を変えることはとてもエネルギーのいることですが、その変化を一緒にお手伝いさせていただきたい。
私たちは「何でもやります」「こんな人に育てます」とは言えません。しかし、本人が変わってみたいと願う、家族が変わりたいと願うのであれば、私たちはその応援を全力でさせていただきます。まずは一度、ご相談いただければと思います。