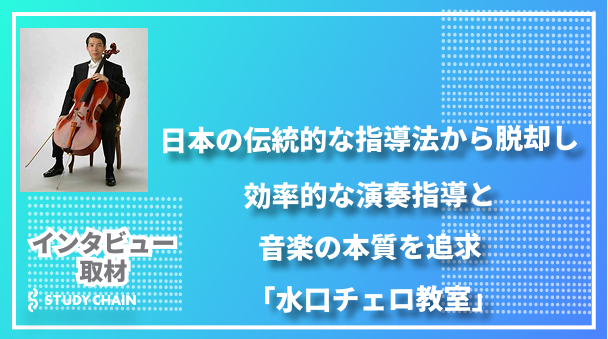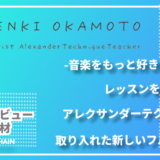ニューヨークの音楽院で学んだ経験を持つ水口貴裕氏が主宰する水口チェロ教室。
明治時代から続く日本の伝統的なチェロ指導法とは一線を画し、より効率的で音楽性を重視した独自の指導方法で注目を集めています。
テクニックだけでなく、作曲家の意図や音楽史まで踏まえた深い理解を育む指導を実践するレッスンについて、水口さんにお話を伺いました。
教室設立の背景

ーこの教室を始められたきっかけや背景について教えていただけますか?
水口さん:ニューヨークでの経験を通じて、日本とアメリカのチェロ指導法に大きな違いがあることに気づきました。
例えば、ビブラート奏法は日本では5、6年経ってからようやく教えますが、私は3ヶ月程度で導入しています。
また、日本の伝統的な教え方では低い音から徐々に高い音へと進みますが、これは非効率的です。
例えば、有名な「白鳥」という曲でも、高いポジションまで習得するのに5、6年以上かかってしまいます。
私のアメリカの先生は、ピアノと同じように最初から全ての音域を使える指導法を採用していました。
ピアノには「第何ポジションで弾いてください」という概念自体がなく、それは弦楽器特有のものなのです。
さらに、日本で使用されているテキストについても課題があります。
明治時代の終わりから大正、昭和初期にドイツから入ってきた教則本をそのまま使い続けているのです。
海外の音楽家に使用している教則本を聞かれ、「馬鹿げている」と言われたこともあります。
当教室では古い教則本を使うのではなく、新しい指導法でチェロをレッスンしています。
音楽性重視の指導法
水口さん:日本の指導法では、演奏のテクニックばかりを教えて、音楽性を教えないという傾向があります。
プロの演奏家は、一聴してベートーベンやモーツァルトの曲だと分かるような、作曲家特有のスタイルで演奏します。
例えば、ベートーベンの音楽は前期・中期・後期で全く演奏の仕方が異なります。
ベートーベンはしばしば「古典派からロマン派への橋渡しをした作曲家」と言われますが、そのような音楽史的な理解があってこそ、適切な演奏が可能になるのです。
チェロという楽器の特徴

水口さん:チェロには良い点と良くない点があります。
良くない点としては、楽器が大きく、ケースを含めると10キロ弱あることです。
一方、良い点は演奏レパートリーの豊富さです。
大きな楽器店に行くと、フルートの楽譜が1つの棚しかないのに対し、チェロの楽譜は2つの棚を埋め尽くすほどあります。
バロック時代のバッハやビバルディから、ベートーベン、ブラームス、さらにはショパンまで、多くの作曲家がチェロのための曲を書いています。
また、オーケストラでの需要も高いのが特徴です。
弦楽器セクションの4分の1がチェロパートですが、実際にチェロを演奏する人はバイオリンの10分の1もいません。
そのため、アマチュアオーケストラでも常に演奏機会があります。
特に日本はチェロ奏者が少なく、アメリカやヨーロッパと比べるとまだまだ普及の余地があります。
生徒指導の重視点
ー生徒さんにレッスンする際に大切にしていることをお聞かせください。
水口さん:クラシック音楽には多くの約束事があり、それは師から弟子へと伝統的に受け継がれてきました。
プロの演奏家の間でも、解釈の7割程度は共通しています。
残りの3割が演奏者による個性の部分です。
私の指導では、まずその基本となる7割をしっかりと身につけてもらうことを重視しています。
特にプロを目指す生徒には、楽器選びも重要な要素です。
私自身、フランチェスコ・ルッリ製の楽器をメインで使用していますが、コンクールなどでは楽器の優劣も大きな要素となります。
しかし、最も大切なのは、聴衆に音楽を届けられる演奏を目指すことです。
今後のビジョン

ー今後、新たに取り組みたいとお考えのことはありますか?
水口さん:現在、初心者から中上級者向けのテクニックや演奏法をまとめた500ページほどの本を執筆しています。
これは、これまでの「回り道」を避け、効率的に良い演奏ができるようになるメソッドをまとめたものです。
この本を通じて、より多くの人に効果的な学習方法を広めていきたいと考えています。
メッセージ
ー教室に興味を持たれた方にメッセージをお願いします。
水口さん:チェロは、年齢に関係なく誰でも始められる楽器です。
子供向けには4分の1サイズから始められる小さなチェロもあります。
60代、70代から始めた方でも、しっかりと演奏できるようになっています。
バッハから始まり、ショパンに至るまでの名曲の数々を楽しむことができます。
ぜひ一度、チェロの世界に触れてみてください。