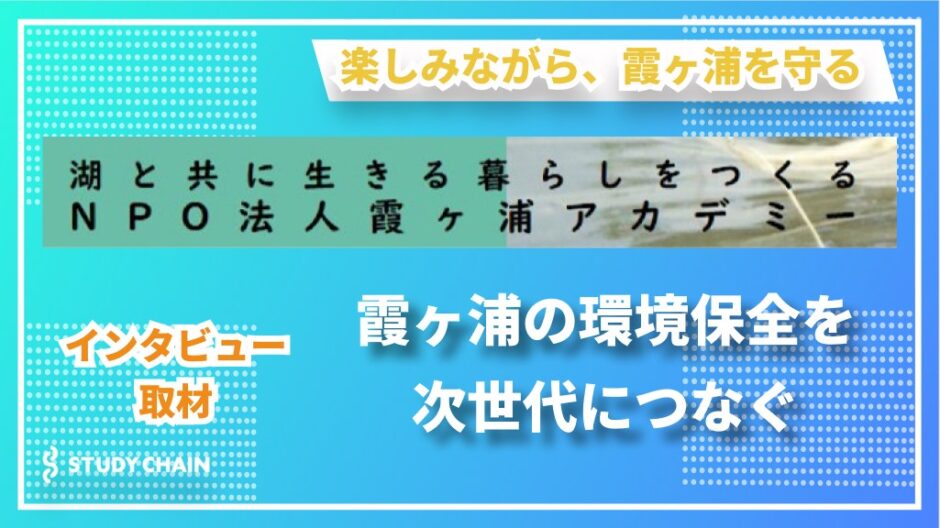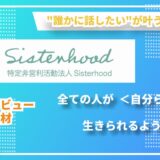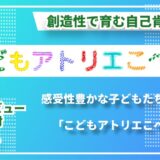環境教育の重要性が叫ばれる昨今、その実践的なアプローチとして「体験型学習」が注目を集めています。茨城県の霞ヶ浦で環境教育活動を展開する『NPO法人霞ヶ浦アカデミー』は、15年以上にわたり、子どもたちの主体性を重視した独自のプログラムを実施してきました。
同団体の特徴は、知識の一方的な伝達ではなく、子どもたち自身が考え、発見する機会を大切にしている点です。事務局長の菊地章雄氏は、かつて10歳で同団体の活動に参加した元生徒。「教えられる」のではなく「共に学ぶ」という理念に深く共感し、現在は運営の中心を担っています。
今回は、環境保全と子どもたちの成長をつなぐ架け橋として活動する『霞ヶ浦アカデミー』の取り組みについて、詳しくお話を伺いました。
環境保全と子どもたちの学びをつなぐ取り組み

ー菊地様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずは『NPO法人霞ヶ浦アカデミー』の活動について、概要を教えていただけますか?
菊地章雄 事務局長(以下敬称略):『霞ヶ浦アカデミー』は、茨城県の湖である「霞ヶ浦」の環境保全を考える市民団体です。活動の対象は広範囲に及びますが、最も注目していただいているのが「生き物アカデミー講座」という環境学習プログラムです。小学生から中学生くらいの親子に参加いただき、霞ヶ浦での環境体験学習を実施しています。その他、一般向けの講座やアウトドアイベントの開催なども行っています。

ー生き物アカデミーでは、具体的にどのような活動を行っているのでしょうか?
菊地:毎月1回、年間12回開催しており、魚を捕まえたり、カヌーに乗ったり、産卵観察をしたりと、季節に応じた活動を行っています。例えば、3月4月頃は魚の産卵状況を確認し、冬場は葦舟(あしぶね)作りなど、年間を通じて様々な体験活動を提供しています。すべての活動を無料で実施しているのも特徴の一つです。
1960年代の水質悪化から始まった環境保全の歴史

ー『霞ヶ浦アカデミー』を設立された経緯について教えていただけますか?
菊地:設立は2008年ですが、その前身となる「生き物アカデミー」の活動は2000年頃から始まっていました。実は私自身、当時10歳で生き物アカデミーの生徒として参加していました。その後、大学生になった2008年にNPO法人化する際、理事として参加させていただきました。
設立の背景には、1960年代から70年代にかけての開発による霞ヶ浦の水質悪化があります。この時期、様々な地域で環境活動が立ち上がっていきました。2008年、行方(なめがた)市側にも環境団体が必要だという声が上がり、同じ思いを持つメンバーが集まって設立されました。その際、既存の生き物アカデミーの活動を中心事業として組み込む形となりました。
「生徒から運営側へ」15年の想いを語る
ー菊地様ご自身、10歳の頃からの参加者だったとのことですが、特に印象に残っているエピソードはありますか?
菊地:個別のエピソードというよりも、生き物アカデミーという場所自体が私にとって大きな存在でした。参加する子どもたちの多くは生き物が好きで、私もその一人でしたが、ここが「学校以外の第三の居場所」として機能していたことが最も印象に残っています。
学校とは異なるコミュニティがあり、新しい友達や先生方と出会える場所でした。先生方も一方的に教えるのではなく、私たち子どもの意見に真摯に耳を傾け、それを肯定しながら学びを導いてくれました。そういった経験があったからこそ、今度は私がその場所を守っていきたいと考えるようになりました。
子どもたちの主体性を重視した独自の環境教育
ー他のNPO法人にはない、『霞ヶ浦アカデミー』ならではの特徴について教えてください。
菊地:私たちが最も大切にしているのは、子どもたちとの向き合い方です。教育団体の中では当たり前かもしれませんが、知識を押し付けるのではなく、子どもたちの考えを尊重しながら、一緒に学んでいく姿勢を重視しています。完璧にできているとは言えませんが、これが私たちの大切にしている特徴です。
ー生き物と関わることで、子どもたちにどのような力が育まれると考えていらっしゃいますか?
菊池:最も重視しているのは、自分で考える力です。例えば「なぜ魚が減ったのか」「種類が変わるのはなぜか」「どうしてここに魚が卵を産むのか」といった問いかけに対して、子どもたち一人一人が考え、意見を述べる機会を大切にしています。
また、命との関わり方についても重要な学びがあります。例えば、霞ヶ浦には豊富な水産資源があり、私たちは捕った魚を持ち帰って食べることを推奨しています。中には「かわいそう」と感じる子どももいますが、そういった葛藤も含めて、生命の循環や、人間と自然との関わり方について考えるきっかけになっています。
多彩な活動展開で広がる環境保全の輪

ー環境教育以外にも、様々なユニークな活動を展開されていますね。
菊地:はい。特徴的な活動の一つが「葦舟世界大会」です。今年で5回目を迎え、3月1日、2日に開催予定です。もともとは子ども向けの体験活動として始まりました。葦(あし)を刈り取って葦舟を作ることで、霞ヶ浦の環境整備にもつながります。より多くの方に参加していただくため、世界大会という形式にしました。
大会は2日間にわたり、1日目は全員で葦を刈って舟を作り、2日目に舟のレースを行います。昨年は8チームがエントリーし、大変な盛り上がりを見せました。今年はさらに規模が大きくなる見込みです。主に大人向けの大会ですが、チームの中に小学生が参加することもあり、世代を超えた交流の場にもなっています。
また、特筆すべき活動として「日越交流会」があります。約10年前から実施している、在日ベトナム人向けの環境教育プログラムです。日本に住むベトナム人の方々の多くは、将来ベトナムに帰国して指導者的立場になる可能性が高いと考えています。そのため、日本の環境問題について学び、考えを深めていただくことで、将来的にベトナムでの環境保全活動にも活かしていただきたいと考えています。

霞ヶ浦の”今”を知る―水質改善への果てなき挑戦

ー霞ヶ浦の水質について、1960年代から現在までの変化を教えていただけますか?
菊地:1960年代から70年代が最も水質が悪化した時期でした。工業化や生活排水の増加により、アオコの大量発生や魚の大量死など、深刻な環境問題が発生しました。その後、人口減少等により若干の改善は見られましたが、現在も課題は残っています。
例えば、大腸菌数の観点から、遊泳は公式には推奨されていない状況です。ただし、私たちは「楽しむこと」も環境教育の重要な要素だと考えており、生き物アカデミーの活動では安全に配慮しながら、子どもたちに水に親しんでもらっています。
ー今後の水質改善に向けた展望はいかがでしょうか?
菊地:水質改善は一朝一夕には進みません。例えば、かつて問題となっていたアオコの発生は、2000年代に比べると減少傾向にありますが「アオコすらでなくなった」との意見もあります。常陸川水門の柔軟な運用などかつての霞ヶ浦に戻す根本的な取り組みが必要に思えます。
一方、市民の環境意識も重要です。霞ヶ浦アカデミーの参加者についていえば、子どもたちの変化は印象的です。生き物アカデミーに参加する子どもたちは、単に「霞ヶ浦は汚い」というネガティブな認識ではなく、「どうすればもっときれいになるか」を主体的に考えてくれています。そういった若い世代の意識の変化が、長期的な環境改善につながっていくと信じています。
私たちは専門家ではありませんが、「霞ヶ浦と共に生きる」という視点から、できることを少しずつ積み重ねていきたいと考えています。環境保全は、行政や専門家だけでなく、地域に住む私たち一人一人が担い手となることで、初めて実現できるものだと思います。
「新しい仲間と共に」霞ヶ浦の未来を創る
ー今後の展望についてお聞かせください。
菊地:私たちは、参加してくださる方々や協力してくださる方々との「つながり」を大切にしながら活動を進めている小さな団体です。より多くの方に参加していただき、それぞれの「やりたいこと」を持ち寄って、霞ヶ浦の環境保全について一緒に考えていける場を作っていきたいと考えています。
茨城県外の方の参加も大歓迎ですし、会員になっていただくことも嬉しいです。また、アイデアの提供や情報収集など、様々な形での関わり方が可能です。

「環境保全は楽しむから始まる」新たな仲間への想い
ー最後に、これから霞ヶ浦の環境教育や地域の環境保全に関わりたいと考えている方へメッセージをお願いします!
菊地:「環境保全は難しい」「専門知識が必要」と構えず、まずは気軽に足を運んでみてください。霞ヶ浦での活動は、子どもから大人まで、誰もが楽しみながら自然と向き合える場所です。魚を捕まえ、船を作り、時には泳ぐ。そんな体験を通じて、自然との新しい関係性を見つけられると思います。
環境保全は、決して重たい責任ではありません。仲間と一緒に楽しみながら、できることから始める。そんな気持ちで、ぜひ一度活動に参加してみてください。新しい発見と出会いが、きっとあなたを待っています。