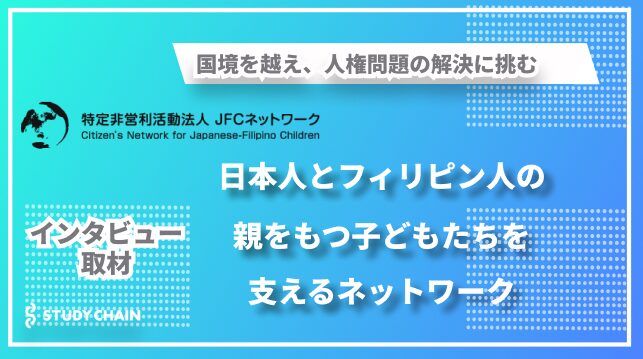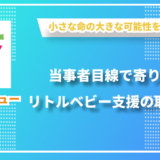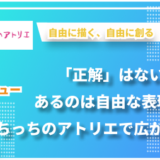1994年の設立以来、日本人とフィリピン人の間に生まれた子どもたち(JFC: Japanese Filipino Children)の支援を続けてきた特定非営利活動法人JFCネットワーク。設立以来30年以上の活動を積み重ねてきた同団体は、時代とともに変化する課題に柔軟に対応しながら、日本人とフィリピン人の親をもつ子どもたちの権利を守り続けています。今回は、これまでの活動の軌跡と現在も続く課題、そして未来への展望について、同団体の伊藤様にお話を伺いました。
設立の背景~1990年代の社会問題として浮上したJFCの存在~

ー まず、JFCネットワークの活動内容についてお聞かせください。
伊藤様:JFCネットワークは昨年30周年を迎えましたが、フィリピン人と日本人の両親を持つ子どもたち、いわゆるJapanese Filipino Children(JFC)の法的支援を行うNPO法人として1994年に設立されました。
当時、フィリピンから多くの出稼ぎ女性が来日し、夜の接客業で働いていました。その中で日本人男性との間に子どもが生まれ、女性たちがフィリピンに帰国後、様々な理由で日本人父親との連絡が途絶え、養育費の支払いが止まるなど、フィリピンに取り残される子どもたちが社会問題となっていました。当時フィリピンでは売買春ツアーなども社会問題化しており、複合的な人権問題として国際的な注目を集めていたような状況でした。
弁護士ネットワークの形成と支援体制の確立
ーそうした社会問題を受けて、具体的にどのように団体は立ち上がったのでしょうか。
伊藤様:1993年、日本人の父から遺棄された子を育てる母親たちからの相談がフィリピンのNGOに殺到し、NGOから相談を受けた日本人弁護士が問題の深刻さに気づき、北海道から沖縄まで60名の有志の弁護士で弁護団を結成しました。当初は手弁当でボランティアとして活動していましたが、言語の壁や通信手段の制限など、様々な課題がありました。
特に困難だったのは、フィリピンのNGOからの相談が英語やタガログ語で寄せられ、それを日本の法制度に照らし合わせて対応する必要があった点です。通信手段も電話やFAXが主流だった時代で、国際的な連携には大きな困難が伴いました。
そこで翌1994年、ジャーナリストの松井やより氏の提案により、弁護士とクライアントを繋ぐ役割を担うNGOとして、JFCネットワークの前身となる団体が設立されました。現在では、フィリピン国内に2つの拠点を持ち、フィリピン全土からの相談に対応できる体制を整えています。
30年で変化する課題:子どもたちの成長と新たな問題
ー30年の活動の中で、JFCを取り巻く状況も変わってきたかと思われます。時間の流れの中で、課題感はどのように変化していますでしょうか。
伊藤様:設立当初は幼い子どもを持つ母親からの養育費や認知請求に関する相談が中心でしたが、仰る通り30年という時を経て、課題も大きく変化してきています。フィリピン女性が生活費を稼ぐ為に日本へ接客の仕事を求めてくる、という流れ自体は途絶えてきましたが、今はその当時生まれた子どもたちが成長し、自身のルーツを探す段階に入っています。
最近の相談の多くは、子どもたち自身からのものです。SNSを通じて「日本人の父親がいると聞いているが、一度も会ったことがない。父親を知りたい、会いたい」という相談が圧倒的に増えています。これは単なる経済的な問題ではなく、アイデンティティに関わる深い問題です。子どもたちは口を揃えて「自分の存在の意味を知りたい」と言います。母親のことは知っていても、父親を知らないということは、人間として半分しか完成されていないような感覚を持っているのです。
法的支援の成果と新たな課題
ー歴史ある貴団体の活動の中で、特に大きな支援実績などがあればぜひお伺いしたいです。
伊藤様:その点で言いますと、「国籍法3条に関する国籍確認訴訟」は、私たち団体の歴史の中でも大きな活動であり、転換点であったといえます。これは2005年に、9人の子どもたちが原告となって、両親が結婚していない子どもたちの国籍取得に関する制限は憲法14条違反だと訴えた訴訟です。この訴訟では、最終的に最高裁で違憲判決を勝ち取ることができ、2009年1月に新国籍法が施行されました。この法改正により、両親が結婚していなくても日本人の父親から認知されれば日本国籍を取得できるようになり、子どもたちの権利は大きく拡大されました。
ーそれは素晴らしい実績ですね。法律の改正というのは大きな事象だと思いますが、それにより新たな課題が生じるといったこともあるのでしょうか。
伊藤様:はい、実は予期せぬ問題が発生してきています。私たちとしては、日本人の父親を持つ子どもたちが等しく日本国籍を取得できるようになり、子どもたちの選択肢が広がることを願っていました。しかし、この法改正により、日本で生まれ育っていない子どもたちも、父親から認知されれば日本国籍を取得できるようになったことで、新たな人身売買のスキームが作られてしまうなど、深刻な課題が浮上してきました。
JFCを取り巻く問題の根は多層に広がっているので、時代に応じた課題への向き合い方が必要であると感じています。
支援システムの進化と成果
ー具体的な支援の在り方についても、この30年間で大きな変化があったのではないでしょうか?
伊藤様:そうですね。特に大きな転換点となったのが、2000年代に日本弁護士連合会の法律扶助制度を活用できるようになったことです。それまでは弁護士費用の捻出が大きな課題でしたが、この制度のおかげで、フィリピンに住む母子に大きな費用負担をかけることなく、法的支援を提供できるようになりました。
ー現在の支援体制について、さらに詳しくお聞かせください。
伊藤様:現在は約250名の弁護士の方々と連携しながら活動を進めています。特に近年は、オンラインでの相談や打ち合わせが可能になり、支援の幅が大きく広がりました。以前は国境を越えた支援に様々な制約がありましたが、特にコロナ禍以降はオンラインシステムが整備され、よりスムーズな支援が可能になっています。フィリピンと日本の物理的な距離を感じることなく、迅速かつ効果的な支援を提供できるようになったのは、大きな進歩だと感じています。
未来への展望:継続的な支援と新たな取り組み
ー今後、特に注力したい活動についてお聞かせください。
伊藤様:大きく分けて3つの課題に取り組んでいきたいと考えています。1つ目は、死後認知の期限制限の問題です。現在、死後認知に関しては父親死亡後3年という期限があり、多くの子どもたちが認知の機会を失っています。既に数件の訴訟を起こしており、この問題の社会的認知を高めていきたいと考えています。
2つ目は、国籍喪失の問題です。両親が結婚していても、日本国外で子どもが生まれた場合、出生後3か月以内に出生届と日本国籍の留保届を提出しないと、日本国籍を失ってしまう現状があります。これにより、子どもたちは実の父親の戸籍に記載されず、戸籍上、父子関係がない状態となっており、相続権すら失われてしまうケースが発生しています。特に父親の高齢化が進む中、早急な対応が必要だと考えています。
そして3つ目は、来日するJFCの若者たちへの支援です。昨年88名の調査を実施し、日本語の壁が最大の課題であることが分かりました。今後は、来日前の日本語教育支援にも力を入れていきたいと考えています。単なる就労支援ではなく、アイデンティティの確立を含めた包括的な支援を目指しています。
ーJFCネットワークの活動に興味を持った方々へのメッセージをお願いします。
伊藤様:問題の本質を理解し、共感していただける方には、サポーター会員やボランティア、インターンとして支援していただければ嬉しいです。また、毎年8月にはフィリピンでスタディーツアーも実施していますので、現地で直接子どもたちと触れ合う機会もございます。問題の複雑さゆえに一言で説明することは難しいですが、より多くの方々に関心を持っていただき、共に活動できることを願っています。