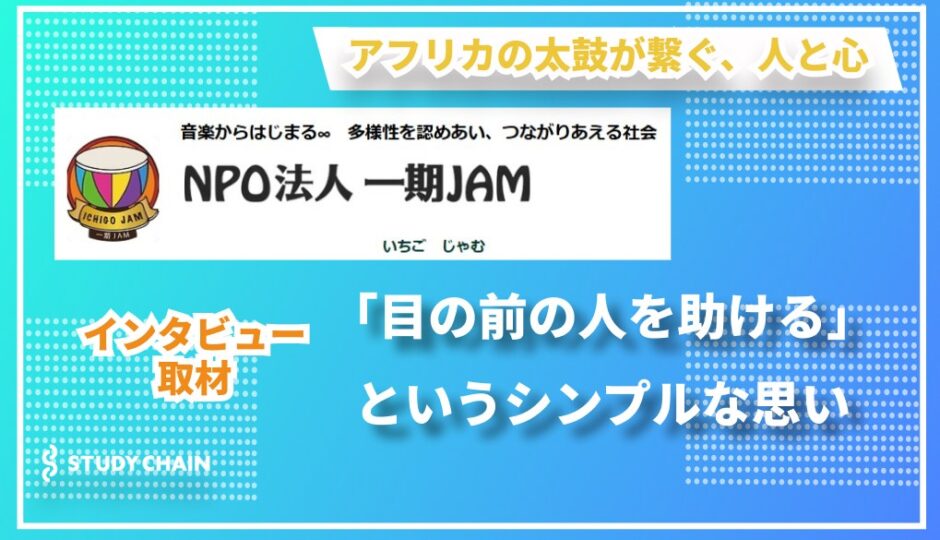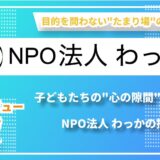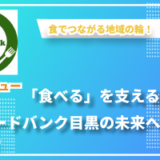アフリカの伝統楽器「ジャンベ」との出会いをきっかけに、在日アフリカ人支援からスタートし、現在では地域福祉まで活動の幅を広げている『NPO法人 一期JAM(いちごじゃむ)』。2013年12月の設立以来、音楽を通じた人との繋がりづくりから、子ども食堂、寺子屋の運営まで、多岐にわたる活動を展開しています。
「目の前にいる人を助ける」という誰もが実践できるはずの、しかし現代社会では見落とされがちな基本的な行動を軸に据え、国籍や文化、年齢、障害の有無を超えた支援活動を続けてきました。セネガル人との偶然の出会いから始まったこの活動は、いまや東京・大田区を拠点に、アフリカ・ギニアでの国際支援にまで広がろうとしています。
理事長の山﨑剛司氏に、設立から12年間の歩みと、音楽が持つ人々を繋ぐ力、そして製造業を通じた新たな挑戦について伺いました。

「日本語が不自由な外国人と出会って気がついた。目の前に困っている人がいることに」—セネガル人との運命的な出会いから支援の道へ

ー 山﨑様、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは、『NPO法人 一期JAM』の概要について教えていただけますか?
山﨑剛司 理事長(以下敬称略):アフリカ音楽を通して人とのつながりを創造し、そこで生まれる心の繋がりを育てていく活動をしています。具体的には、ワークショップの開催や子ども食堂、寺子屋など、多岐にわたる事業を展開しています。手探りで始めた活動も今年で12年目を迎えました。
ー この法人を立ち上げた経緯について教えてください。
山﨑:私が20歳前後の頃、神奈川県川崎市中原区の武蔵小杉にあるスポーツショップで働いていた時に、セネガル人と出会ったことがきっかけです。当時の武蔵小杉は、東京に比べて家賃が2万円ほど安く、アフリカ人が出稼ぎで働きながら生活する小さなアフリカンコミュニティがありました。
その時代、日本社会はまだ外国人の受け入れ体制が整っておらず、外国人が日本社会に馴染めない葛藤や、厳しいルールに苦しむ姿を間近で見てきました。そんな中、渋谷の雑貨屋で働くセネガル人の友人から「アフリカンドラムを輸入してほしい」という依頼を受けたのです。
アフリカの伝統楽器「ジャンベ」との運命的な出会い

山﨑:最初は断ったものの、何度も頼みこまれたので、一度だけ輸入代行を引き受けることにしました。成田空港で受け取ったボロボロの段ボールの中に入っていたのが、「ジャンベ」という楽器との初めての出会いでした。
結局、約半年ごとに輸入の依頼が続き、2年ほどその輸入代行の仕事を続けることになりました。次第に、楽器の叩き方やメンテナンスについての問い合わせも増えてきました。当時はその問い合わせに対応できる人がおらず、「それなら、自分でやるか」と思い立ち、日本人の先生からジャンベの叩き方や革の張り方などを教わるようになり、少しずつ演奏のスキルも身につけていきました。
その先生が「リズムを何曲か覚えたら、その仕上げとして小学校や幼稚園で演奏しよう」と誘ってくれたことで、学校訪問での演奏機会が始まりました。ジャンベは5人から10人で叩くことで迫力のある演奏となりますが、そうした本格的な演奏を子どもたちの前で披露する機会を得たのです。
この経験が、大きな転機となりました。子どもたちが演奏に心から喜び、元気になっていく姿を目の前にして、音楽の持つ力を強く実感したのです。特に印象的だったのは、障がい者施設で演奏した際、耳の不自由な子どもたちが振動で音を感じ取り、楽しむ姿でした。
そして、もう一つの重要な発見がありました。日本社会で自信を失いがちなアフリカ人たちの文化が、このように受け入れられ、価値あるものとして認められる様子を目の当たりにしたのです。当時、在日アフリカ人の多くは、言葉の壁や文化の違いに悩み、時には解雇されたり、自己嫌悪に陥ったりすることも少なくありませんでした。しかし、彼らの音楽は、日本社会で確かな存在感を示し、高く評価されていたのです。
この発見は、後の活動の方向性を決定づける重要な転機となりました。学校訪問の経験を重ねる中で、個人的にジャンベを教えてほしいという依頼も増え始め、2010年頃には定期的な活動として確立していきました。これが、NPO法人設立への第一歩となったのです。
「困っている人がいれば助ける。その”当たり前”が忘れられている」— 他のNPOにない独自のポリシー

ー 他のNPO法人にはない、『一期JAM』ならではの特徴やアピールポイントを教えてください。
山﨑:私たちの特徴は、「目の前にいる人の助けになる」というシンプルなポリシーです。これは、あるエピソードがきっかけでした。コンビニでレジを済ませた時、私が募金箱にお釣りを入れたところ、一緒にいたアフリカ人の友人が「なぜ見たこともない人にお金を渡せるのに、目の前で困っている人が見えないのか」と指摘したのです。
強い、本当に強い衝撃を受けました。
この経験から、国際交流や文化交流という枠だけにとらわれず、目の前で困っている人に手を差し伸べるという姿勢を大切にしてきました。活動を続ける中で、引きこもりの子どもたちや発達障害を持つ子どもたち、その親御さんとの出会いもあり、活動の幅は自然と広がっていきました。
他のNPO法人と異なる点として、私たちは国内で活動する外国人、特にアフリカ人の方々が自信を持ち、日本人との接点を作れるような支援に重点を置いています。
音楽を通じたコミュニケーションの新たな可能性
ー ジャンベの音楽の魅力と、人間のコミュニケーションにおける音楽の効果について教えてください。
山﨑:ジャンベという楽器は、最小単位の音を繰り返してリズムを作り出す楽器です。リーダーが太鼓の音で始まりと終わりを指示し、その間を最小単位のリズムで繋いでいくという、シンプルなルールで成り立っています。このシンプルさゆえに、お年寄りから子どもまで、1人でも100人でも一緒に演奏することができます。
近年では、欧米のドラムサークル音楽療法の分野で、複数人で一緒にドラムを叩くことが、セロトニンの分泌を促進し、うつ病などにも効果があることが科学的に証明されています。特にジャンベは、シンプルな楽器であるため、先進国の子どもたちの精神的な健康に必要なツールになると考えています。
多岐にわたる活動内容と地域との繋がり
ー 『一期JAM』の主だった活動について教えてください。
山﨑:まず、音楽ワークショップでは、ジャンベを中心に、カホンやウクレレ、アサラト(西アフリカの木の実を使用したシェイカー)など、様々な楽器のワークショップを行っています。特にジャンベは、初心者の方が入りやすいように工夫しており、在日アフリカ人の先生との交流にも繋げています。

2017年にスタートした「いちご食堂」は、地域交流を目的とした子ども食堂です。東京・大田区は東西に長く、富裕層と貧困層がグラデーションのように分布している地域です。特に蒲田地区では、核家族化による子どもの孤独や、高齢者の一人暮らしによる孤独が課題となっています。子どもだけでなく、大人やお年寄りも含めて、食事を通じた安全な地域社会づくりを目指しています。

また「ゴミ拾い活動」は、国際交流と地域交流のクロスオーバーを狙った取り組みです。アフリカ人の先生方と一緒にゴミ拾いをすることで、地域の方々との自然な交流が生まれています。初めは「何をしているんだろう」と不思議がられますが、「アフリカから来ました」と日本語で話しかけると、「日本語が上手ですね」「どこに住んでいるんですか」というコミュニケーションが自然と始まります。外国人の方々も日本社会に貢献したいという思いを持っており、その橋渡しの役割を果たしています。

製造業を通じた新たな挑戦と国際支援への展開
ー 『一期JAM』の今後の展望について教えてください。
山崎:私は20年間、大田区の製造業に携わってきました。その経験を活かし、新たに町工場を立ち上げることを計画しています。日本の製造業は高齢化が進み、70代、80代の方々が引退される中、後継者不足が深刻な問題となっています。
一方で、地域活動や子ども食堂で出会う子どもたちの中には、発達障害などを持ち、一般的な教育課程には馴染みにくいものの、プログラミングなどの特殊な才能を持つ子どもたちがいます。しかし、多くの場合、そういった子どもたちは月給が少ない軽作業の仕事に就くことが多いのが現状です。そういった子どもたちの受け皿となる雇用の場を作りたいと考えています。
さらに、アフリカの方々の雇用の受け入れ先としても機能させたいと思います。アフリカは「地球最後のフロンティア」と呼ばれ、今後の産業発展が期待されています。日本で技術を身につけたアフリカの方々が、その技術を母国に持ち帰り、アフリカの産業発展に貢献できるような、そんな未来を描いています。
2025年からは、新たにギニアでの国際支援活動も開始します。ギニアでは、政情不安などにより、伝統的な音楽文化の担い手が減少し、教える場所も人材も不足している状況です。そこで、音楽教育の場を作り、子ども食堂も併設する計画を進めています。
共に成長できる活動を目指して

ー 最後に、『一期JAM』に関わりたいと考えている方々へ、熱いメッセージをお願いします!
山崎:私たち『一期JAM』は、目の前で困っている人の手助けをするという、とてもシンプルな思いから始まりました。現在では活動内容も多岐にわたり、それぞれの場面で多くの仲間の力を必要としています。私たちの活動を通じて支援を受ける人々が幸せになることはもちろんですが、それ以上に大切にしているのは、活動に関わる仲間たち一人一人が、この活動を通じて生きがいを感じ、人生の糧となるような気づきを得られることです。人を助けることで自分も成長する。そんな共に育ち合える場所を作っていきたいと考えています。ぜひ、私たちと一緒に成長していける仲間との出会いを楽しみにしています。
セネガル人との出会いから始まり、アフリカの伝統音楽との偶然の出会いによって広がった活動は、今や国際交流、地域福祉、そして国際支援へと発展しようとしています。しかし、どれだけ活動が広がっても、「目の前にいる人を助ける」という原点は決して変わりません。むしろ、活動の幅が広がるほど、この原点の大切さを実感しています。人と人との出会いを大切にし、目の前の人の幸せを願う。その小さな思いが、やがて大きな社会の変化を生み出すのだと信じています。