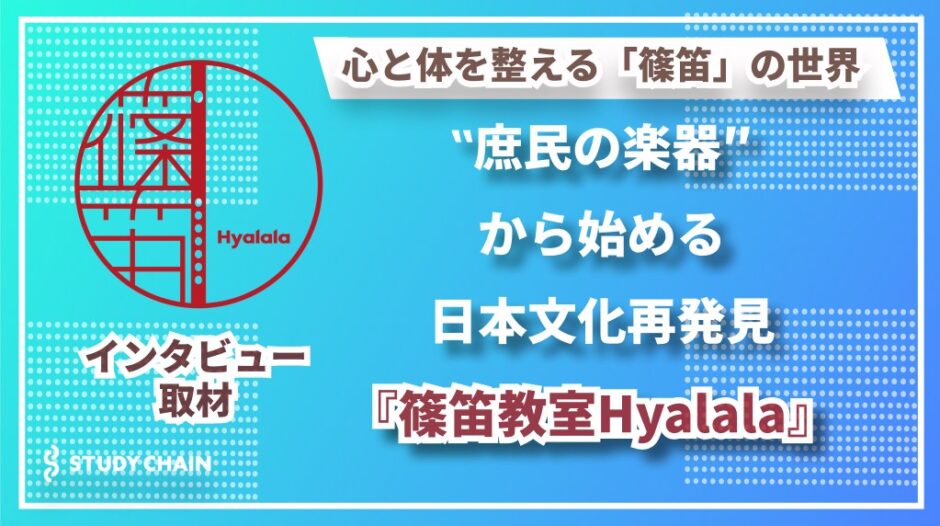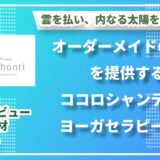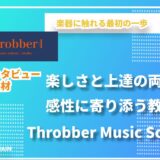デジタル社会の喧騒の中で、静かに息づく日本の伝統楽器「篠笛」。その澄んだ音色と深い呼吸は、忙しい日常から私たちを解き放ち、心の奥底に眠る感性を呼び覚ます力を持っています。宮城県仙台市を拠点に活動する『篠笛教室Hyalala(ひゃらら)』の主宰・石田陽祐氏は、自らの経験から培った独自の指導法で、篠笛の魅力を多くの人に伝えています。
「一人ひとりの『やりたい』に応える」をモットーに、小学生からシニア世代まで幅広い世代が集う同教室。最大の特徴は少人数制のグループレッスンと、生徒それぞれの目標に合わせたオーダーメイドの指導スタイルです。お祭りのお囃子から現代の歌謡曲まで、生徒の希望に応じた多彩なレパートリーを学べる柔軟性も魅力の一つ。
「息を通して自分と向き合う時間」を大切にする石田氏の指導哲学から、篠笛が持つ心身への効果、そして和楽器が現代に果たす役割まで、日本の伝統が紡ぐ新たな可能性に迫ります。

Yosuke Ishida
1986年宮城県出まれ。11歳で篠笛を始める。『閃雷(せんらい)』等でのチーム活動を経て、2018年独立。国内外での多数の公演実績を持つ他、数々の著名なアーティストとの共演、ゲーム音楽・映画音楽への参加を経験。その他、コンサート制作、グラフィックデザイン、CM出演、教育機関での講演なども行っている。
自身が主宰する『篠笛教室Hyalala』では60名を超える生徒と共に年間約600回のレッスンを実施。2021年には個人事務所『篠八屋商店』を開業し、仙台市中心部に音楽スタジオ『Hyalala Music Studio』をオープン。
現在は鍵盤楽器奏者・齋藤めぐむ氏とのユニット『FEEK ON(フィーク・オン)』や、津軽三味線演奏家・小野越郎氏が主宰する『音会わせBAND』等でも活動している。
「呼吸と音色が紡ぐ場所」〜幅広い世代に開かれた少人数制の教室〜

ー石田先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは、『篠笛教室Hyalala』はどのような方を対象に、どのような指導を行っているのでしょうか?
石田陽祐 主宰(以下、敬称略):弊教室は日本の伝統楽器である篠笛を教えています。対象年齢は限定せず、どなたでも気軽に通っていただける環境を心がけています。現在は小学生からシニア世代の方まで幅広い年齢層の生徒さんが通われています。
指導方法の最大の特徴は少人数制であることです。グループレッスンではありますが、1回のレッスンの定員を最大4名に限定しています。全国の篠笛教室の多くは大人数でのレッスンか個人レッスンが主流ですが、弊教室ではこの少人数制を採用することで、一人ひとりに目が行き届きながらも、グループならではの学び合いの環境を提供しています。
「デジタル時代のアナログな癒し」〜息を通して心と向き合う篠笛の魅力〜

ー篠笛という楽器の魅力について、石田先生のお考えをお聞かせください。
石田:篠笛の魅力は様々ありますが、特に感じるのは「自分自身と向き合う時間」を作ってくれることです。現代の生活はデジタルに囲まれ、慌ただしく情報が押し寄せてくる中で、篠笛に触れる時間は自分の内面、自分の心と向き合う貴重な機会になります。
篠笛は自分の息がそのまま音になる楽器です。心が穏やかな時と、心がざわついてもやもやしている時では、出る音の表情がまったく異なります。この楽器に触れることで、自分の心の状態を映し出し、ニュートラルな状態へと導いてくれるのです。
デジタルな時代だからこそ、このアナログな時間が自分の心をリセットしてくれる。それが篠笛の大きな魅力の一つです。また、和楽器特有の美しい音色、何とも形容しがたい日本の「和」の音色が持つ癒しの効果も、多くの方を魅了しています。
「独学の苦しみから生まれた使命」〜教室設立に秘められた思い〜

ー石田先生が篠笛教室を開かれた経緯やきっかけを教えてください。
石田:私自身は小学生の頃に篠笛を始めましたが、特定の先生について学ぶことはなく、ほぼ独学で続けてきました。上手な方の演奏を見よう見まねで学んでいましたが、篠笛は目に見えない要素が多い楽器です。息の使い方や口の中の形など、外からは見えない部分が重要になるため、なかなか上達せず、長い間もどかしさを感じていました。
紆余曲折を経て自分なりに技術を身につけていく中で、「同じような思いをしている人は必ずいるはずだ」と考えるようになりました。自分が経験した遠回りを少しでも減らし、より直接的に「できた」という喜びを積み重ねていけるよう手助けしたい。その思いが教室を開くきっかけとなりました。
ー石田先生自身が篠笛を始めたきっかけは何だったのでしょうか?
石田:私の原点は和太鼓にあります。小学校1年生の時に地元の太鼓グループに誘われて和太鼓を始めました。家族で一緒に活動する中で、太鼓と篠笛がセットで使われることに気づきました。笛を担当する人は少数で限られていましたし、太鼓では表現できないメロディを奏でられる篠笛に強く惹かれました。「自分もやってみたい」という純粋な思いから笛を借りて始めたのが最初のきっかけです。
「あなただけの道を奏でる」〜一人ひとりの「やりたい」に応えるオーダーメイド指導〜
ー他の篠笛教室とは違う、石田先生の教室ならではの特徴的なアピールポイントは何でしょうか?
石田:弊教室の最大の特徴は、生徒さん一人ひとりが「習いたいこと」「練習したいこと」を自由に決められる点だと思います。これはおそらく他の教室ではあまり見られない特徴ではないでしょうか。
例えば、お祭りのお囃子を吹けるようになりたい方、私が拠点にしている宮城県の「仙台すずめ踊り」という芸能の笛を学びたい方、テレビで見た演奏に憧れて始める方など、きっかけは様々です。中には具体的な目標がなく「なんとなく篠笛に興味があって」という方もいらっしゃいます(笑)。
それぞれの方が習いたい内容は異なります。お囃子をベースにしたい方もいれば、好きな歌謡曲や民謡を吹けるようになりたい方もいます。少人数制だからこそ、このような一人ひとりの希望に丁寧に応えることができるのです。
もちろん、篠笛の基礎技術は共通して学んでいただきますが、その先でどのような曲を練習材料にして技術を磨いていくかは、生徒さんそれぞれの興味関心に合わせています。決まった教則本に沿って全員が同じ内容を学ぶのではなく、オーダーメイドに近い形で指導を行っています。
「感覚を言葉に、音色を心に」〜見えない要素を「見える化」する指導法〜

ー生徒さんに指導する際に、特に意識していることや方針などがあれば教えてください。
石田:先ほども申し上げたとおり、篠笛は「見えない要素」が非常に多い楽器です。例えば、音を出すための息も目に見えませんし、息の出し方もろうそくを吹き消すような強い息と、ゆっくりとした深呼吸のような息では全く違います。さらに、体の内側の使い方や口の中の形なども重要で、これらはすべて外からは見えない部分です。
多くの人は感覚的にいろいろな方法を試しながら「なんとなくこんな感じかな」と自分の中で覚えていきますが、それを他者に伝えることは非常に難しいものです。
私が指導で最も心がけているのは、これらの「見えない要素」をできるだけわかりやすく言語化し、具体的なイメージで伝えることです。「なんとなく」というあいまいな表現ではなく、身近な例えを使ったり、イメージしやすい言葉を選んだりして、感覚を共有できるよう工夫しています。
また、小学生に教える時と大人に教える時では、同じ内容でも伝え方を変えています。その人の経験や知識に合わせて、最もイメージしやすい言葉を選ぶことを大切にしています。男性と女性でも感覚の捉え方が異なることもあるので、一人ひとりに合わせた表現を心がけています。
「最高のアンチエイジングは吹奏にあり」〜心と体を整える篠笛の健康効果〜

ー石田先生は、とても若々しいですね!篠笛を演奏することで得られる健康面や心理面でのメリットについて教えてください。
石田:篠笛は‟呼吸”を使う楽器であることが大きな特徴です。日常生活で意識的に深呼吸をする時間を作っている方は、実はごく少数ではないでしょうか。現代社会では呼吸が浅くなりがちで、リラックス状態で一日を終えることも難しくなっています。
篠笛の演奏では、腹式呼吸を使った深い呼吸が不可欠です。これにより副交感神経が優位になり、「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの分泌が促進されます。体がふっとリラックスした状態になれるのは、息を使う楽器ならではの効果と言えるでしょう。
また、研究によると音楽を聴くだけでも脳に良い影響があることがわかっていますが、自分自身が楽器を演奏することの方が、脳への刺激ははるかに大きいとされています。篠笛の演奏では目、耳、指、そして呼吸を同時に使うため、脳の様々な部位が活性化します。いわゆる「脳のアンチエイジング」の効果も期待できるのです。

さらに、和楽器には日本文化特有の精神性も宿っています。例えば、演奏前後の所作や心の持ち方など、一見すると意味がないように思える部分にも重要な意味があります。相撲や茶道など、日本の伝統文化に共通する「形」の美しさや意義を、篠笛を通して体感できることも大きな魅力です。
「音楽が繋ぐ人と心」〜コミュニティの場としての教室づくり〜

ー提供されているレッスンプランについて教えてください。
石田:弊教室は宮城県の仙台市と大崎市(古川教室)の2か所で展開しています。
メインとなる仙台市の教室では少人数制のレッスンを提供しており、平日の火・水・木曜日に月3回の1時間レッスン、土曜日には月2回の1時間半レッスンを行っています。各クラスの定員は4名までとしています。
大崎市では月に1回、第3金曜日に最大10名までのグループレッスンを開催しています。また、個別のニーズに応えるため、個人レッスンも別途承っています。
仙台の教室は、以前レコーディングスタジオだった物件を活用しています。コロナ禍の時期に契約しましたが、すでに防音設備が整っていたことは非常に幸運でした。
「響き合う心を育む場所へ」〜音楽と人を繋ぐ未来の教室像〜

ー今後、より強化していきたいことや、新たに取り組んでいきたいことを教えてください。
石田:弊教室では単に篠笛の技術を提供するだけでなく、「通うことが生活の彩りになる場所」を目指しています。最近では「サードプレイス(第三の場所)」という言葉もありますが、教室に来ることが生徒さんの幸福感につながるような環境づくりを今後さらに強化していきたいと考えています。
技術革新で便利になる一方で、人と人との心の繋がりが希薄になりがちな現代社会。SNSがいくら発達しても埋められない寂しさがあるように、実際に会って交流する「生の繋がり」の価値はますます高まっていくでしょう。私自身や会員さん同士の交流を通じて、心の豊かさを育む場を提供していきたいと思います。
また、生徒さんが成長を実感し、満足度を高めるためには、学んだ技術を披露する機会が重要です。発表の場や演奏の機会をさらに増やし、一人ひとりの成長をサポートする取り組みも強化していきたいと考えています。
「伝統を身近に、敷居を低く」〜庶民の楽器としての篠笛の魅力〜

ー最後に『篠笛教室Hyalala』に興味をお持ちの方へ、石田先生からメッセージをお願いします!
石田:日本の和楽器は日常生活ではなかなか馴染みがなく、「自分には縁がないもの」「格式の高いもの」と感じる方も多いかもしれません。しかし、篠笛は歴史的に見れば「庶民の楽器」であり、暮らしの中で親しまれてきた楽器なのです。
良い意味で肩の力を抜いて、気軽に取り組める楽器だと思います。実際、自分の息で音を鳴らしてみると、年齢に関係なく誰もが子どものような表情で「わあ、素敵」と反応してくれます。難しいものだと構えず、ぜひ親しみを持って篠笛の世界に触れていただけたら嬉しいです。
入会される方に楽器経験を尋ねると、半数以上の方が「全く楽器の経験がない」と答えます。「小学校の授業でリコーダーを触ったくらいで、楽譜も読めませんが大丈夫でしょうか」と不安に思われる方も多いのですが、そういった方々も皆さんしっかりと吹けるようになっています。
音楽の経験の有無に関わらず、篠笛は誰でも楽しめる楽器です。興味を持たれた方は、ぜひ一度体験してみてください。思いがけない自分との出会いがあるかもしれません。