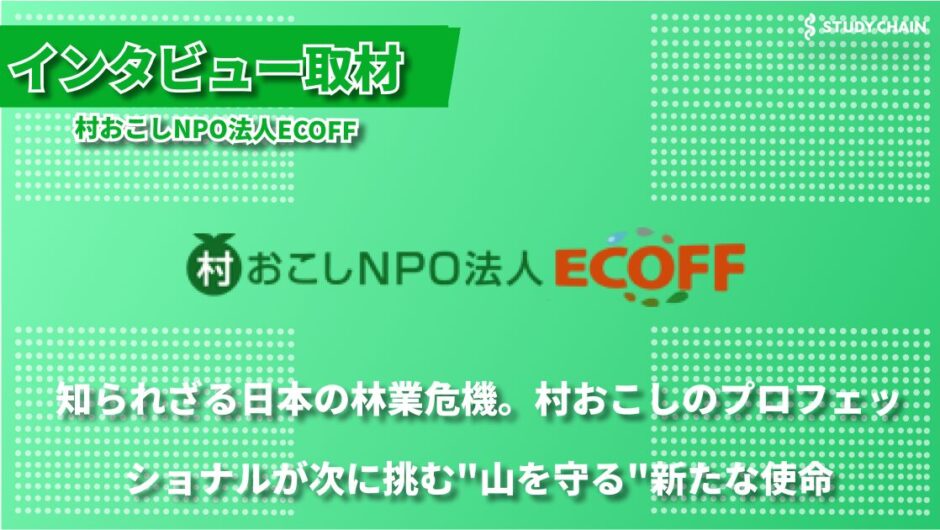「まちづくりには観光だけでなく、その土地に根付いた文化や知恵を継承していくことが大切です」。そんな思いから2011年に設立された村おこしNPO法人ECOFFは、大学生を中心に年間100回以上のボランティアプログラムを実施しています。今回は代表理事の宮坂さんに、地域活性化の新しい取り組みと、これからの展望についてお話を伺いました。

事業概要と活動内容について
ーまず、ECOFF様の事業概要と主な活動内容について教えていただけますでしょうか。
宮坂さん:私たちの活動は、基本的には10日間の離島や農山漁村での住み込み型のボランティア活動を提供しています。当初は年齢制限を設けていませんでしたが、長期休暇が必要なため、現在は主に大学生を対象としています。
基本的には18歳から25歳の方を対象としていますが、コースによっては未成年の方や社会人の方も参加いただけます。
プログラムの詳細と実施状況
ー年間でどのくらいの頻度でプログラムを実施されているのでしょうか。
宮坂さん:主に2月、3月と8月、9月の大学生の長期休暇の時期に実施しており、年間で約100回のプログラムを展開しています。
これまでに活動してきた拠点の数は約50か所です。現在も継続して活動している地域は、ウェブサイトのコース一覧ページで確認できます。
設立の経緯
ーECOFF様を立ち上げられたきっかけについて教えていただけますでしょうか。
宮坂さん:2011年の設立当時、「地方創生」という言葉さえまだ一般的ではない時代でしたが、その中で私たちが目指したのは、単なる地域活性化ではなく、各地域に残された文化や知恵を後世に残していくことでした。
当時は「関係人口」という概念もなく、「交流人口」という言葉が使われていた程度です。しかし、ある地域の文化や伝統を守るためには、その地域自体を維持していく必要があります。
そのためには、まずその地域のことを知ってもらわなければなりません。知らない地域には誰も訪れることはなく、移住も考えず、その地域の商品を買おうとも思わない。そうして誰からも忘れ去られていく地域が、どんどん活気を失っていく―。この悪循環を何とか断ち切れないかと考えました。
私自身、それまで各地の農家で活動をしていた経験があり、そこでの学びは非常に大きなものでした。その経験から、より多くの人々が地域と関われる仕組みを作れば、地域への興味や理解が深まるのではないかと考えました。
様々な形を模索する中で、「ある程度の期間、その地域に滞在して活動する」というスタイルが、地域理解を深める上で最も効果的だとわかってきました。そこで、10日間という期間を設定し、その地域で必要とされているボランティア活動を行う、という現在の形に行き着いたのです。
初めは試行錯誤の連続でしたが、この形式であれば、参加者は地域の実情を深く理解でき、地域側も継続的な受け入れが可能になります。また、活動を通じて地域の方々との信頼関係も築きやすく、本当の意味での文化継承や地域活性化につながっていくと確信しました。
プログラムの特徴と参加者の声
ープログラムの期間や費用について教えていただけますでしょうか。
宮坂さん:参加費は39,000円で、宿泊費は無料です。この金額には保険代や自炊の食材費、水道光熱費などが含まれています。ただし交通費は別途必要です。現地には多くの場合スーパーマーケットがないため、地域の世話人の方が食材を調達したり、地元の方からのお裾分けをいただいたりしています。
参加者からは「人生観が変わった」という声が圧倒的に多く、約9割の方がそのような経験をされています。多くの方が観光地化を想像して参加されますが、実際の地域活性化は全く異なる現実があり、それが大きな学びになっているようです。
ECOFFの特徴と強み
ーECOFF様ならではの特徴やアピールポイントを教えていただけますでしょうか。
宮坂さん:ECOFFの最大の特徴は、サポート体制の充実さです。10日間という期間、知らない場所で知らない人々と過ごすことへの不安は大きいと思います。そのため、私たち運営側は様々なサポートを用意しています。
参加者は代表理事である私と直接LINEや電話で連絡を取ることができますし、匿名でのフォーム送信も可能です。さらに、専門の精神科医によるメンタルケアも無料で受けられる体制を整えています。
また、現地での活動はすべて各地域の世話人の方々に委ねています。私が同行しないことで、地域の自立性を保ち、参加者の主体的な学びを促進しています。これにより、コストを抑えることができ、年間100回という多くのプログラムを実施することが可能になっています。
私たちの活動の特徴として、経済的な価値だけではない、本質的な価値を提供していることが挙げられます。リゾートバイトや移住体験プログラムなど、お金が介在する形での地域との関わりも増えていますが、ECOFFは純粋なボランティア活動として、人口100人程度の小さな村や離島など、経済的な理由で他のプログラムでは訪れることができない地域での活動を可能にしています。
今後のビジョン:林業への挑戦
ー今後の展開についてお聞かせください。
宮坂さん:これからは林業分野に力を入れていきたいと考えています。
なぜなら日本の森林の約半分は人工林で、その管理が大きな課題となっているからです。適切な管理がされていない人工林は、土砂崩れや洪水の原因にもなります。
日本の林業が抱える課題
ー具体的にどのような課題があるのでしょうか。
宮坂さん:日本の森林の現状について、多くの人が誤解や理解不足の状態にあります。人間が住んでいる場所の近くにある森林のほとんどは、実は天然林ではなく人工林なのです。スギやヒノキといった樹木は、建築用として計画的に植えられたものです。
しかし、木材輸入の自由化により国産材の価値が大きく下落し、林業の収益性が悪化しました。林業には50年という長期的な視点が必要で、植林から収穫までの間、継続的な管理と投資が必要です。現在は、その管理を担う人材が不足している状況です。
森林管理の重要性と環境への影響
ー森林管理が環境に与える影響について教えていただけますでしょうか。
宮坂さん:適切な管理がされていない人工林は、環境に深刻な影響を及ぼします。例えば、間伐が行われないと木々が密集し過ぎて、地面まで光が届かなくなり、その結果、下草が育たず、土壌が露出した状態になりうるのです。
特に針葉樹は、大雨が降った際に水を分散させずに一気に地面に落とすため、土壌の流出や洪水の原因となります。かつては地域の人々が適切に管理していましたが、高齢化や後継者不足により、その体制が崩れつつあります。
解決に向けた取り組みとECOFFの役割
ー課題解決に向けて、ECOFF様ではどのような取り組みを考えていらっしゃいますか。
宮坂さん:この問題を解決するためには、人工林を適切に管理するか、もしくは天然林に戻すかの選択が必要です。しかし、現状では人手不足により十分な管理ができず、また管理しても追いつかない状況が続いています。
ECOFFとしては、これまで地域活性化で培ってきた経験を活かし、林業の課題についても多くの人に知ってもらい、理解を深めてもらうことが重要だと考えています。例えば、国産材を使用した家具を選ぶなど、消費活動を通じた支援の方法もあります。今後は、このような林業の課題に取り組み、より多くの人々が山のことに目を向けられるような活動を展開していきたいと考えています。
ECOFFからのメッセージ
ー最後に、ECOFF様の活動に興味を持った方へメッセージをお願いします。
宮坂さん:現在、地域に触れる活動は増えていますが、ECOFFの特徴は純粋な非営利のボランティア活動である点です。リゾートバイトなど、お金で繋がる縁とは異なり、人口100人程度の村や離島など、経済的な理由で他のプログラムでは訪れることができない地域で活動しています。
お金では解決できない問題に取り組み、経済的な価値だけでなく、本質的な出会いや学びを得られることが私たちの強みです。ありのままの地域の方々と触れ合いたい方には、自信を持ってECOFFをお勧めできますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。