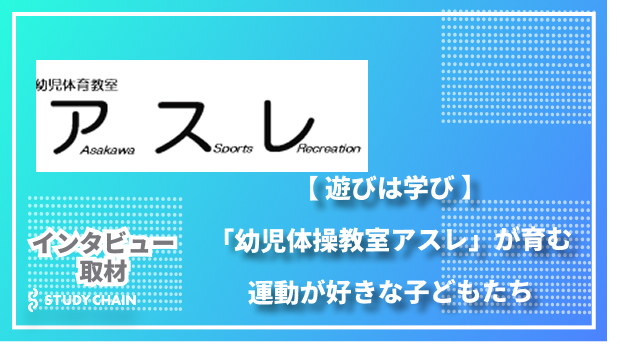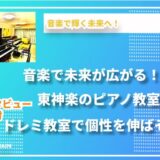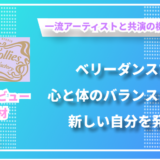幼稚園教諭としての経験を活かし、子どもたちの発育発達に適した運動遊びを提供する「幼児体操教室アスレ」。
単なる体操教室ではなく、子どもの成長を多角的に支援する場を目指す教室の同活動について、淺川正堂さんにお話を伺いました。
子どもの発達に合わせた運動遊びを提供

ー どういった方を対象にどのような指導をされていますか?
淺川さん:淺川さん:教室名は幼児体育教室としてありますが、現在は幼児から小学2年生程度までを対象にした運動教室となっています。
一般的に体操教室というと、器械体操をイメージされると思いますが、鉄棒やマット、跳び箱など器械体操や学校体育で使用されるような体操器具に加えて、様々なオリジナル遊具を使いながら、子どもの発育と発達をとらえた「遊び」を中心としています。
子どもの運動機会創出への思い
ーご自身がこの教室を始められたきっかけであったり、背景についてお聞かせください。
淺川さん:「幼稚園の先生」として働くなかで幼児の身体や体力・運動能力の現状、そして「子どもの体力低下」を肌で感じました。
また、私も子を持ち、現代の家庭や社会では、子どもが十分に身体を動かして遊ぶ環境が少なくなっていることを知りました。
我が子も含めて「子どもが元気いっぱいに身体を動かして遊べる環境を提供しよう」と思ったことがきっかけです。
「遊びは学び」をコンセプトにした独自の教育方針
ー教室の特徴であったり、アピールポイントだとお考えの点はどういったところでしょうか。
淺川さん:身体を使って遊ぶことが楽しい!もっとやりたい!という環境を作ることで、子どもは繰り返し遊び、経験を重ねて動作を習得していきます。
アスレでは子どもたちが「楽しい♪→できた!」の体験をたくさん出来るように簡単なものから複雑で難しいものまで、非常に細かな段階(スモールステップ)を組んであります。
小学生までにはほとんどの子が「運動が好き」「友達と〇〇して遊びたい」という気持ちと身体に育っていきます。
実は妻も幼稚園教諭なんです。
特に幼児期は個人差が大きいですから、一般的な子どもの発育・発達を意識しながらも一人一人の心身の成長段階やその日の気分や状態も良く見極める必要があります。
その点については妻の方が良く見てくれるのでありがたく思っています。
いろいろな体操教室や運動教室がありますが、スタッフの皆が保育経験者であることで安心して通っていただけると思います。
様々なニーズに応える教室運営
ーお子さんを通わせていらっしゃる保護者の方はどういったことを期待されていますか?
淺川:割合は分かりませんが、「この子は運動するのが好きだから、幼稚園から帰ってきても、もっと遊ばせてあげたい」というご家庭もあれば、「運動に興味がなくて心配なんです」というケースもあります。
また発達支援の相談を受けたところ、「運動をした方がいいです」と言われたものの、「何をしたら良いのか・・・家庭でできることには限界が・・・」と相談に来られるというケースもあります。
いずれの場合でもアスレに来ていただければ、お子さんに運動が「楽しい♪→できた!」の経験をたくさんしてもらえます。
幼児クラスはほとんどの保護者が活動の様子を見ていらっしゃって、預けて帰られる方はほとんどいません。
我が子の可愛いらしい姿を愛でながらも「どのように遊んでいるのか」「どのように他の子と関わっているのか」とよく観察しておられます。
表向きは身体の育ち(運動)という一本の柱ですが、お母さん方は恐らく二本目の柱として心の育ち(教育・保育)を期待していただいていると思っています。
子どもの興味関心を大切にする指導
ー教室でレッスンされる際に大切にしていることや、意識していることはありますか?
淺川さん:終わりの挨拶をする時に「えっ、今日おしまい?」「もう終わりなの?」と子どもたちがポロリとこぼす言葉は、私たちへの褒め言葉かなと思っています。
ですから「ごめんね」ではなく「ありがとうございます」と返事をします。
幼児教育で一つ面白いキーワードがあります。
「遊びは学び」子どもは遊びの中で学ぶということです。
活動が少しでも「遊び」に近づくように
①子どもが好きな遊具を使って遊べる時間を作る。
②「大きなヘビをジャンプするぞっ!」と縄跳びで遊んだり、「お猿さんに変身しよう♪」と鉄棒で遊んだりと楽しく運動できるように関わる。
③時々「次は何に変身する?」「こんなルールはどう?」「ゲームで勝つための作戦を考えよう」と子どもと一緒に考えて遊びを作る。
こうして幼稚園教諭の経験と知識を活かして子どもの「主体的な活動=遊び」に近づくようにしています。
「楽しいからもっとやりたい」と繰り返し経験を積んでいけば必ず体力・運動能力は向上していきます。
ただし・・・
子どもの好きなことだけでは動作の経験が偏ります。
走る、跳ぶ、投げる、転がる、バランスをとるなど多様な動作が経験できるように意識しています。
その場合も「子どもの興味・関心」を大切に!です。
子どもは運動をすることで身体の使い方をどんどん学びます。
しかし、学ぶのは身体の使い方だけでなく、数や時間の概念、そして言葉、人との関わり方も学んでいきます。
体力・運動能力の向上はもちろんですが、子どもの成長を広く捉え「遊びが学び」となるように常々意識しています。
幼児・小学生の二つのクラス展開
ー実際に提供しているクラスについて教えてください。
淺川さん:クラスは幼児クラスと小学生のクラスがあります。
自分の力で友達と運動遊びを楽しめる子どもたちの育成
ー今後強化したいとお考えのことや将来的なビジョンについて教えてください。
淺川さん:子どもたちが豊かに成長して丈夫に生きてくれればと思っています。
創立の大きな背景はこれですので、この点についてはどこまでも頑張りたいと思っています。
幼児期に身体を動かす気持ちよさを感じ運動を好きになり、友達と一緒に遊ぶ方法を身につけて欲しいと思っています。
その経験と力があれば、小学生になっても学校の先生や大人から「この遊び、このルールで遊ぶんだよ」と提供されなくても、友達とコミュニケーションをとって遊びを創造できるようになるでしょう。
「好きな遊び」を見つけること、そして「友達と一緒に遊ぶ楽しさ」を知れば幼稚園や保育所を楽しみにして通ってくれるでしょう。
学校では「好きな遊び」が「好きな教科」になっていくでしょうし、就職すれば「好きな仕事」になっていくでしょう。
それを見つけられて、仲間と一緒に取り組む楽しさを知っていれば、人生何とかなるかな、楽しく過ごせるかなと思います。
夢という言葉で良いのであれば、大人になった彼らが「アスレ楽しかったよ」と教えてくれたり、自分の子どもと楽しげに遊ぶ幸せそうな姿が見られれば最高かなと。
運動が苦手な子こそ体を動かす楽しさを知ってほしい
ー入会を考えていらっしゃる方にメッセージをお願いできますでしょうか?
淺川さん:身体を動かして遊ぶことが好きな子はもちろんですが、苦手な子こそ入会していただきたいです。
お子さんには身体を動かして遊ぶことの楽しさや気持ちよさをもっともっと感じていただけるでしょうし、保護者の方には我が子の可愛さと豊かな育ちを感じていただけると思います。