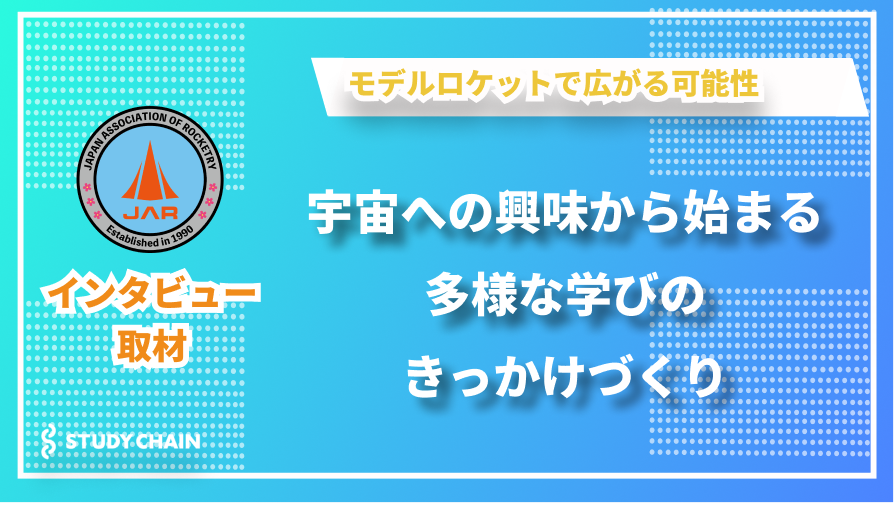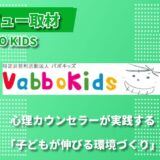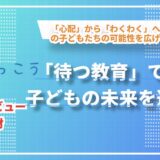34年の歴史を持つ日本モデルロケット協会。モデルロケットの製作・打ち上げを通じて、子どもたちに宇宙への興味だけでなく、多岐の分野にわたる学びのきっかけを提供しています。
その活動の意義と今後の展望について、会長の桐生氏にお話を伺いました。
法改正を実現し、日本にモデルロケットを普及

ー団体の概要ついてお聞かせください。
桐生:子どもから大人まで、年齢や性別を問わず、モデルロケットや宇宙工学、モデル工作に興味を持つ方々を対象に活動しています。特に中学・高校生向けの宇宙教育に力を入れていますが、実際には活動を通じて様々な分野への興味が広がっています。
例えば、モデルロケットの製作では接着剤を使用します。子どもたちは製作過程で最適な接着剤を探究するうちに、接着剤という化学分野に興味を持つようになることもあります。
また、モデルロケットの打ち上げには火薬類取締法や航空法など、複数の法律が関係します。150メートルを超える高度で打ち上げる場合は航空局への届出が必要です。こうした経験から法律に興味を持ち、将来は法曹界を目指したいという生徒も出てきています。
34年の歴史と設立の経緯
ー団体設立の経緯について教えてください。
桐生:設立のきっかけは、初代会長の宇宙への情熱でした。当時、日本では火薬類取締法の関係で、モデルロケットの輸入や打ち上げができない状況でした。これを合法的に実現するため、まずは任意団体として発足し、法改正に向けて取り組みました。
当時の埼玉県火薬類保安協会の会長の協力を得て、当時の通産省(現・経済産業省)との交渉を重ね、ようやく法改正が実現しました。米国では学校教育の教材として普及していたモデルロケットを、日本でも安全に楽しめる環境を整えることができたのです。
安全性を重視した教育プログラムを全国展開
ー実際に行っている活動の具体的な内容を教えてください。
桐生:主な活動として、毎月定期的にロケット教室を開催しています。モデルロケットのエンジンは火薬量が少なく、一般の花火と同様に誰でも購入できますが、経済産業省からの通達に基づき、安全な取り扱いと打ち上げについての教育を行っています。
また、年2回JAXAの筑波宇宙センターで全国大会を開催し、120〜150名ほどの参加者が高度と滞空時間を競います。
さらに中高生を対象とした「ロケット甲子園」では、長さ70センチほどのロケットに鶏卵を搭載し、指定された高度と時間での着地を競う大会を実施しています。
特筆すべきは、モデルロケットの安全性です。エンジンは米国で開発された規格に基づいており、専用の点火具なしには発火しない設計になっています。これにより、幼稚園児から安全に扱うことができます。
グローバルな活動展開と子どもたちの可能性を広げる取り組み
ー貴法人だからこそ提供できる学びについて教えてください。
桐生:当協会の特徴は、モデルロケットの安全な取り扱いと宇宙教育を組み合わせたカリキュラムを提供していることです。また、指導講師制度を設け、全国各地で教室を開催できる体制を整えています。
現在では、北海道から沖縄まで、全国の中学・高校生が活動に参加しています。さらに、国際航空連盟(FAI)の世界選手権への選手派遣も行っています。これは他の団体では実現できない、当協会ならではの取り組みです。
興味のきっかけづくりを重視した活動方針
ー今後の展望についてお聞かせください。
桐生:より多くの地域でロケット教室を開催し、子どもたちの興味を広げていきたいと考えています。
実際にロケット1機を打ち上げるには、エンジニアだけでなく、制御用ソフトウェアの開発者、気象データの分析者、そして人事・総務・法務など、様々な職種の人々が関わっています。
モデルロケットの製作を通じて、工学、法律、化学など、多様な分野への興味を持つきっかけを提供したいと思います。
現代の子どもたちの中には、明確な目的を持たないまま進学する例も少なくありません。当協会の活動を通じて「やってみたい」という思いを見つけ、将来の進路を考えるきっかけになればと考えています。
ー最後に、記事をご覧の方へメッセージをお願いします。
桐生:ロケットや宇宙に興味がない方にこそ、まずは一度、教室に参加していただきたいと思います。紙と木とプラスチックで、実際に飛ぶものを作る体験を通じて、新しい発見があるはずです。
何をしたいのか、どうなりたいのかまだ決まっていない方こそ、ぜひ参加してみてください。