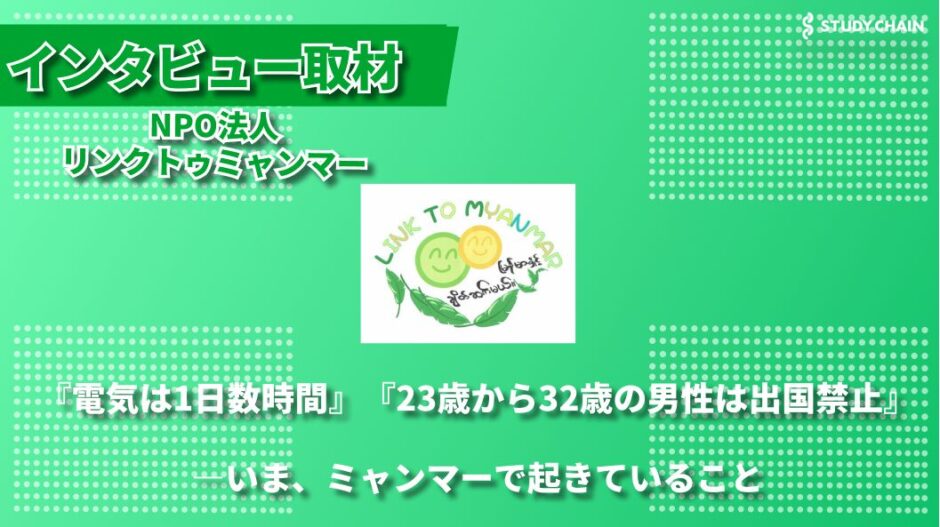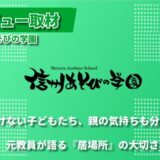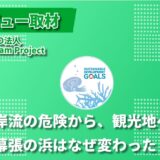横浜市金沢区を拠点に活動するNPO法人リンクトゥミャンマー。在日ミャンマー人への生活支援から、日本人への啓発活動まで、幅広い活動を展開しています。設立から7年、ミャンマー語で相談できる支援体制と、次世代の人材育成に力を入れる同団体の取り組みを紹介します。
団体概要と主な活動内容
ーまず、リンクトゥミャンマーの活動内容について教えてください。
西尾さん:横浜市金沢区を中心に活動している団体で、在日ミャンマー人の方々への支援を主な活動としています。活動内容は多岐にわたり、携帯電話の契約補助から、保育園入園手続きの支援、さらには横須賀市教育委員会との通訳契約に基づく学校での通訳業務なども行っています。
設立の経緯と理念
ー法人設立に至った経緯や、活動の理念についてお聞かせください。
西尾さん:当会の代表は日本人女性で、その配偶者がミャンマー人です。もともとは配偶者が個人的なレベルで、来日したミャンマー人の生活支援や相談対応を行っていました。
活動を続けていく中で、支援を必要とする方が徐々に増えていき、より組織的な対応が必要だと感じていきます。また、単なる支援にとどまらず、「多文化共生」という大きな理念のもと、ミャンマー人と日本人が互いの文化を理解し、尊重し合える社会を作っていきたいという思いも強くなっていきました。
そこで2017年にNPO法人として認証を受け、本格的な活動を開始。配偶者自身が来日経験者として直面した様々な困難や、それを乗り越えてきた経験を活かし、より多くのミャンマー人の方々の支援ができる体制を整えました。私も、このような理念と活動内容に強く共感し、スタッフとして参加することを決めました。
ミャンマー人と日本人が一方的な支援関係ではなく、互いに学び合い、理解を深めながら共生できる社会を横浜から作っていく。その思いは設立から現在まで、変わることなく私たちの活動の原点となっています。
団体の特徴と強み
ー他の支援団体と比べて、特徴的な点を教えていただけますか。
西尾さん:私たちの最大の強みは、ミャンマー人からの相談をミャンマー語で受けられる点です。外国人支援団体の中には日本人だけで構成される組織も多く、どうしても言葉の壁や文化の壁が生じてしまいます。当会では代表の配偶者がミャンマー語のネイティブスピーカーで、自身も日本での生活経験が20年以上あることから、行政システムにも精通しています。この体制により、支援を必要とする方々の課題を正確に把握し、適切な支援を提供できています。
また、大学生インターンの受け入れにも力を入れている点も特徴です。ミャンマー人支援だけでなく、将来的に外国人との共生社会を担う日本人人材の育成も重要な活動の一つと考えています。インターンの学生たちは単なる研修生ではなく、団体の職員として実践的に活動に携わっています。
現在のミャンマー情勢と今後のビジョン
ー現在のミャンマーの状況と、今後の活動の展望についてお聞かせください。
西尾さん:現在のミャンマーは軍事クーデターにより、非常に厳しい状況にあります。電力供給は1日数時間に制限され、23歳から32歳までの成人男性には徴兵制が敷かれ、国外への出国も制限されています。しかし、ウクライナや中東情勢と比べ、メディアでの注目度は低く、この現状を知る人も少ないのが実情です。
当会では、ミャンマー本国でも日本語学校を運営するなど、両国での活動を展開しています。今後は特に日本人への啓発活動に力を入れていく予定です。これまでは多文化共生や国際交流に関心のある方々向けのイベントが中心でしたが、今後は就職活動に役立つイベントなど、より幅広い層に向けた企画を通じて、ミャンマーの現状や外国人との共生について理解を深めていただきたいと考えています。
利用者と接する際に気をつけていること
ー支援者として、日本語が母語ではない方々とコミュニケーションを取る際に意識されていることを教えてください。
西尾さん:日本に来られるミャンマーの方々は、基本的に日本語能力検定などである程度の日本語レベルを持っておられますが、日本語を学ぶ機会がないまま来日される難民の方もおられますし、医療機関での専門用語など日本人でも難しい表現については、理解が困難な場合があります。
そのため、私たち日本人スタッフは、漢字をひらがなに直したり、「現金で支払う」を「お金を機械に入れる」というように、できるだけ簡単な日本語で説明するよう心がけています。
また、日本人スタッフで対応できる部分は直接対応し、専門的な説明が必要な場合は、ミャンマー語が堪能なスタッフを介して正確な情報伝達を行うようにしています。
記事を読んでいる方に向けたメッセージ
ー最後に、この記事を読んでいる方々へメッセージをお願いできますでしょうか。
西尾さん:日本はすでに多くの外国人が暮らす社会となっており、職場の半数が外国人という環境も珍しくありません。外国人との共生は、もはや遠い未来の話ではなく、私たちの目の前にある現実です。
特にミャンマーについては、現在の厳しい状況をまず知っていただきたいと思います。実は、私たちの活動を通じて、日本の方々からの支援で難民キャンプにトイレを設置するなど、具体的な支援の成果も生まれています。しかし同時に、国軍の空爆によってそういった施設が破壊されてしまうという厳しい現実もあります。
このような状況下で、金銭的な支援ももちろん重要ですが、まずは多くの方にミャンマーの現状を知っていただき、関心を持っていただくことが何より大切だと考えています。当会では、ミャンマーの伝統料理を楽しむイベントなど、気軽に参加いただける形で交流の機会を設けています。SNSでの情報発信も行っていますので、ぜひInstagram、X、Facebookなどをご覧いただければと思います。
一人ひとりの小さな関心や行動が、より大きな変化につながっていくと信じています。皆様のご理解とご支援が、ミャンマーの人々の希望となり、そして日本における多文化共生社会の実現への一歩となることを願っています。