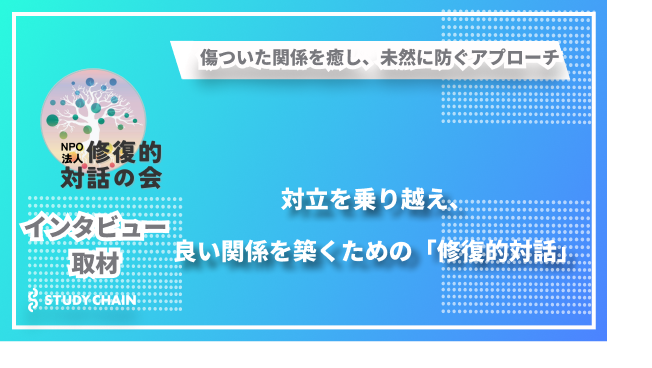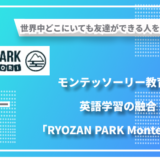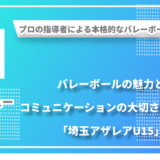いじめ、ハラスメント、家族間の不和など、現代社会では様々な人間関係の課題が存在しますが、これらの問題に対して、従来の解決方法では十分な効果が得られないケースも少なくありません。
そんな中、対話を通じて関係修復を目指す「修復的対話サークル」という手法が注目を集めています。
問題が起きた後の修復だけでなく、未然防止にも大きな効果を発揮するとされる修復的対話を広める活動をする「修復的対話の会」の梅崎さんにお話を伺いました。
多様な場面で活用できる修復的対話サークルとは

梅崎さん:修復的対話は、元々は刑事司法の分野から始まった対話手法です。
その特徴は、話し手と聞き手をはっきりと分ける独特の対話構造にあります。
トーキングピースという、話し手を示すものを持っている人だけが話せるというルールがありますが、このルールのおかげで、怒りや悲しみ、差別など、通常の社会では話しづらいテーマについても話しやすくなります。
また、一緒に意思決定をする必要がある場合や、意見が食い違う状況、誰かに害を加えた経験に向き合う必要がある場合など、様々な場面で効果を発揮する手法です。
対話を通じた未然防止の重要性
ー修復的対話サークルの特徴について教えてください。
梅崎さん:修復的対話の大きな特徴は、問題の未然防止に重点を置いているという点です。
人間関係のコンフリクト(対立)は、そう簡単には解決できないものです。
特に学校や職場では、人間関係を簡単に切ることができません。
そのため、対立が深刻化する前に、日常的な対話を通じて互いを理解し合うことが重要です。
定期的な対話を通じて、一人一人が自分の行動を振り返り、変化していくことができるのです。
「対話の会」の実践 ― 安全な場での対話体験

ー対話の会ではどのような活動をされていらっしゃるのですか?
梅崎さん:対話の会は、対面とオンラインの両方で定期的に開催しています。
対面の会は10年近い実績があり、特に地域で孤立しがちな女性たちのための対話の場として機能してきました。
参加者は多岐にわたり、ソーシャルワーカーやカウンセラー、キャリアコンサルタントなどの専門職の方も多いですが、実は過去に様々な傷つき体験をされた方々も参加されています。
家族や職場の同僚や友人との関係がうまくいっていない人、イジメや親からの虐待を経験した方までいらっしゃいます。
この場では、誰もが特別な専門家としてではなく、一人の人間として対等に存在することを大切にしています。
職場での活用 ―― ハラスメント防止と組織風土の改善
ー修復的対話サークルはどのようなシーンで役立つとお考えですか?
梅崎さん:近年、企業のハラスメント防止研修にも修復的対話が導入され始めています。
従来型の「してはいけない」という禁止型の研修ではなく、より前向きなアプローチを目指しています。
特に、トーキングピースを用いる修復的対話サークルには、組織の風土や文化を変える力があります。
かつての日本企業では、飲み会などを通じて仕事以外での人間関係を築いていましたが、現在はそういった機会が減少し、職場の人間関係がドライになりつつあります。
3回程度の対話を実施することで、職場の雰囲気が大きく変わっり、参加者が次第に打ち解け、自分の趣味や人生経験を話せるようになり、より良い人間関係が築かれた例もあります。
学校教育での可能性

ー教育現場でも修復的対話サークルは活用できますか?
梅崎さん:学校では現在、、イジメ防止対策として道徳教育に力を入れています。
しかし『お友達と仲良くしましょう』『これは駄目ですよ』といった教えだけでは不十分です。
子どもたちは実際の人間関係の中で、時には対立や葛藤を経験しながら成長していきます。
トーキングピースを使う修復的対話を道徳の授業に取り入れることで、より実践的な学びの場を提供できると考えています。
活動のきっかけと今後の展望
ー修復的対話サークルを広める活動を始めたきっかけについて教えてください。
梅崎さん:この活動は、高齢者虐待、特に家族間の虐待を未然に防ぎたいという思いから始まりました。
社会的な孤立が虐待の背景にあることが多いため、地域の中で緩やかな人間関係を作ることが重要だと考えたのです。
現在は、企業や学校、保健福祉施設など、様々な場所での実践を通じて、この手法の効果を検証しています。
ー 最後に、読者へのメッセージをお願いします。
すごく平凡に見えるかもしれませんが、この対話にはパワフルな力があります。ぜひ一度、体験してみてください。
修復的対話サークルは、単なる対話の手法ではありません。
それは、人と人とのつながりを再構築し、より良い関係を築く実践的な対話アプローチであり、哲学やライフスタイルだと言う人もいて、職場や学校、地域社会など、様々な場面での活用が期待されています。