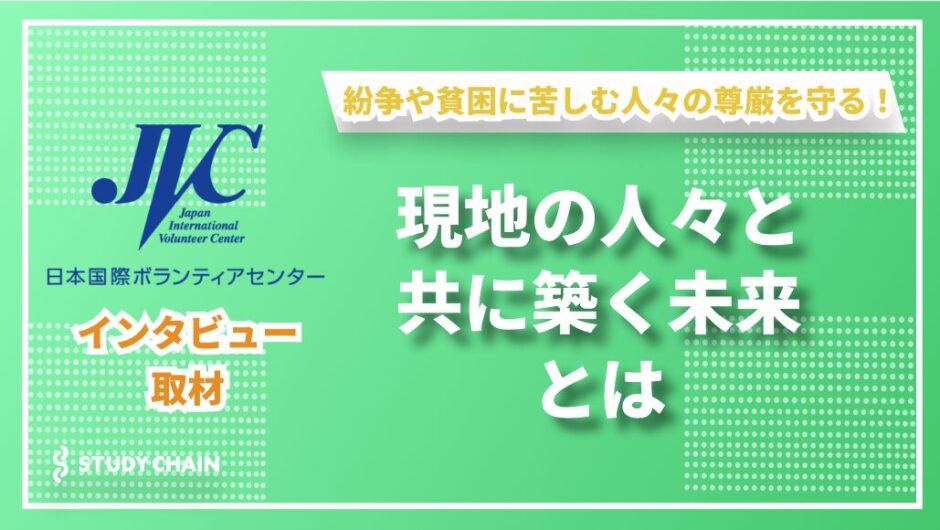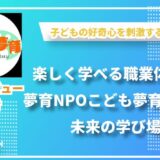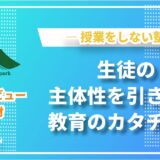日本国際ボランティアセンター(JVC)は、紛争や貧困、栄養失調といった深刻な問題に直面する地域で、現地の人々と共に持続可能な未来を築くための活動を続けています。スーダンやパレスチナ、ラオスなど、多様な地域で教育支援や栄養改善、自然資源の保全に取り組み、それぞれの地域のニーズに応じた柔軟な支援を展開中です。
特に、現地の住民が自分たちの力で課題を解決できるような仕組みを作ることに注力。支援を「与える」のではなく「共に考え、乗り越える」姿勢が特徴です。設立以来40年以上にわたり、国際協力を通じて平和で公平な社会の実現を目指してきたJVCの理念と活動の詳細をお届けします。現地で何が行われているのか、その意義や課題を具体例とともに深掘りし、私たちの日常にもつながる国際協力の形を探ります。
活動地域と内容について

ーまず、日本国際ボランティアセンター(以下JVC)がどのような地域で活動されているのか、具体的な内容を教えていただけますか?
日本国際ボランティアセンター広報事業担当 仁茂田さん(以下敬称略):現在、JVCはイエメン、スーダン、パレスチナ、ラオス、コリアの5カ国/地域、さらに日本国内で活動しています。地域によって課題が異なるので、私たちの活動内容もその地域のニーズに合わせて変わってくるんです。
例えば、スーダンでは紛争が長く続いているため、学校に通えない子どもたちが多いんです。特に昨年4月に首都で大きな戦闘が起こり、それが全国的に広がってしまって。それで、私たちが元々活動していた地域でも学校が閉鎖されてしまったんですね。学校が閉鎖される以前から正規の学校に編入することを目標に補修校運営の活動をしていたのですが、活動地の子どもたちにとって本当に貴重な教育の機会となっています。
家族を亡くしたり暴力を目の当たりにするなど、大変な経験をしている子どもたちも多く、勉強だけじゃなくて、スポーツやレクリエーションの時間を設けて、子どもたちが安心して過ごせる場を作るよう心がけています。
一方、パレスチナのガザ地区では、栄養失調や発達の遅れが深刻な子どもたちを支援してきました。地域の女性ボランティアを育成して、家庭訪問を通じて栄養指導や健康チェックを行っています。具体的には、病院で診てもらった方がいいお子さんがいれば病院に繋げたり、栄養失調を防ぐ食事のアドバイスをしたりしています。現在はガザが壊滅的な被害を受けている状況なので、できる形での親子のサポートを行っている状況です。
また、ラオスでは、企業による開発等で生活基盤を奪われるリスクに直面している人々の支援を行っています。たとえば、自然資源をどう管理すれば生活を守れるか、住民と一緒に考えながら進めています。

JVC設立の経緯
ーJVCが設立された背景について教えていただけますか?
仁茂田さん:JVCが設立されたのは1980年です。当時、インドシナ地域の難民問題が日本国内でも大きく報じられていて、見過ごせないと感じた日本の若者たちが現地に向かったのがきっかけです。最初は個人での活動でしたが、難民キャンプ内での活動の許可取得のために団体化しました。
当初は「日本国際奉仕センター」という名前で活動を始めましたが、その後、「日本国際ボランティアセンター」に改名しました。これは、遠い国の人たちに一人の市民として自発的に支援を行っていく、そういった国際協力やボランティアという考え方をもっと広く根付かせたいという思いからなんです。
活動を通じて解決を目指す課題

ーJVCの活動を通じて、世の中の解決したい課題について教えてください。
仁茂田さん:私たちが取り組んでいるのは、紛争や貧困といった、個人ではどうしようもない大きな問題です。ただ、解決するには物資配布のような対症療法的な支援では不十分とJVCは考えていて、「問題の根本」にアプローチすることを大切にしています。
これは、一番最初のインドシナ難民支援で、難民キャンプでいくら活動してもあとから次々と難民になった人たちがくる、どうすれば難民にならない社会をつくるかが大切なんだ、という気づきからきていて、40年以上活動を貫くポリシーとなっています。
例えば、ガザ地区での栄養改善の支援も、栄養豊富な食べ物を配るのではなくて、地域の人々が自分たちで子どもたちの健康を守れるようにすることを目指しています。JVCがいなくなっても地域の人々が自立して問題を解決できるような仕組み作りを心がけています。
また、現地での支援活動のみでなく現地の人々の声を広く発信したり、声明などの政府への働きかけのような、世の中の構造や社会の流れを変えていくための活動も大切にしています。2024年10月5日は、ガザ地区での深刻な人道危機に関心を持ってもらうために、「停戦を、今すぐに。」というキャンドルアクションを日本の増上寺で開催しました。
参加者にはキャンドルで「ガザ」という文字を作っていただいて、ガザの人々への思いを共有しました。その場では、ガザ支援をおこなうJVCを含むNGOスタッフたちから現地の状況や、具体的な支援内容についても詳しくお話しました。
ガザについては、2023年10月からのニュースをきっかけに国際問題に関心を持って、イベント参加や寄付などのアクションを初めて起こしました、という方も多くて、このような形で市民一人ひとりが関わることで、ガザの人々への連帯の気持ちが広がっていくと信じています。
活動における大切な理念

ーJVCが活動する上で、特に大事にしていることを教えてください。
仁茂田さん:JVCでは3つの柱を大切にしています。
- 奪うのではなく分かち合う
ラオスの例でいうと、自分たちの利益優先の開発などで暮らしが壊されてしまう人々が出なくなるような社会を目指すための取り組みをしています。 - 分断を対話の力で乗り越える
いわゆる北朝鮮、韓国、中国、日本の子どもたちによる絵とメッセージの交換、日本の大学生と平壌(ピョンヤン)の大学生の交流(現在はコロナ禍の影響で休止中)など、一人ひとりの「顔」が見える、草の根から平和を築くための活動をしています。 - 可能性を共に開く
これは「助けてあげる」というスタンスではなく、「一緒に乗り越える」という考え方です。現地の人々が自分たちで問題を解決できる力を育むような支援をしています。
今後の展望とメッセージ

ー最後に、JVCへの寄付や活動への参加を考えている方にメッセージをお願いします。
仁茂田さん:国際協力って、どうしても「自分には関係ない」って思われがちなんですけど、実はそうじゃないんです。日々の生活の中でできることがたくさんあります。
例えば、JVCのSNSをフォローして活動内容をシェアしてもらうとか、イベントに参加してみるとか。寄付やボランティアももちろん大歓迎ですけど、それ以外にも小さなアクションがたくさんあるんです。
東京の事務所で、もしくはZOOMなどを通した遠隔でのボランティア体験もできますし、学校への講演も行っています。学生さんの中には特に、こういった活動を通じて新しい視点を持つことができる方もたくさんいますよ。
一人の100歩よりも100人の一歩のほうが世の中へのインパクトは大きいと考えていて、一人でも多くの方に一歩を踏み出していただけたらと思います。
もし少しでも興味を持っていただけたらこちらから参加していただけると嬉しいです!