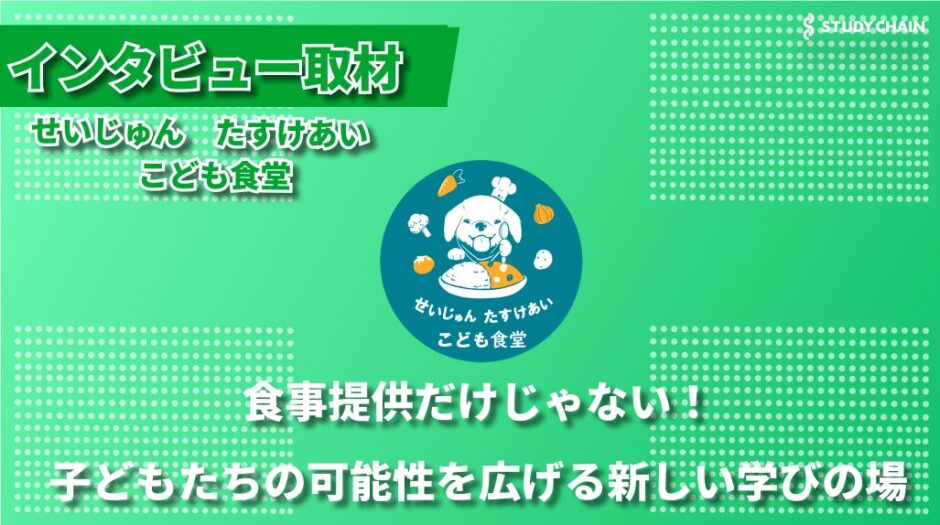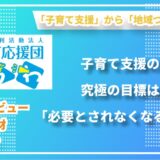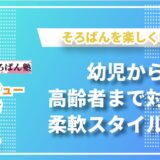2018年の設立以来、子どもたちの未来を支え続けてきた「せいじゅん たすけあい こども食堂」。食育と教育を柱に、発達障害のある子どもたちの支援や、引きこもり状態にある青年層への支援まで、活動の幅を広げてきました。今回は、子どもたちの「生きる力」を育むために、どのような取り組みを行っているのか、事務局長の乾さんにインタビューしました!

子どもの生きる力を育む多角的な支援活動
ー御社の活動概要について教えてください。
乾さん:当法人は「教職」「食育」および様々な学びを通じて子どもたちの生きる力を育むことを基本戦略とした子ども食堂です。対象は乳幼児から中学生までの子どもとその保護者、また引きこもり状態にある青年層です。
活動範囲は非常に広く、子ども食堂の運営を中心に、親子料理教室の開催や子ども食堂農園での野菜作り、夏休みの調理体験デイキャンプなど、食育に関する様々な取り組みを行っています。
また、学習支援も重要な活動の一つです。対面での学習支援に加え、パソコンとカメラを貸し出してのオンライン学習支援も実施しています。これは5年ほど前から始めた取り組みで、NPO団体として無料でマンツーマンの学習支援を提供している事例は国内でも珍しいものです。
成り立ちと開設の背景
ーこの活動を始められたきっかけについて教えてください。
乾さん:元々は地域における経済的な貧困、特に食事が十分に取れない子どもたちと保護者への支援という目的でスタートしました。
しかし、実際に活動を始めてみると、経済的な問題以外にも様々な社会課題が見えてきました。例えば保護者の方から、学校に行きづらくなった、いじめの問題で困っている、育児ノイローゼで悩んでいるなど、多岐にわたる相談を受けるようになったのです。
そういった経験から、私たちは「貧困」の定義をより広い意味で捉え直し、現在の3つの貧困(経済的貧困、つながりの貧困、経験の貧困)に対する支援体制につながります。
今では発達障害のある子どもたちの参加も全体の約半数を占めており、これからの社会を生きていく子どもたちへの支援の在り方を日々模索しています。
多彩な学びの機会を提供する各種イベント
ー具体的にどのようなイベントを実施されていますか。
乾さん:子ども食堂の活動に加えて、プログラミングクラブ、子育て講演会、親子料理教室、アニメイラスト・グラフィック講座など、食事提供に限らない様々な体験の場を提供しています。
またウェブを活用した学習支援も特徴的な取り組みの一つです。学校に通うことが難しい子どもたちや、学習面で課題を感じている子どもたちに対して、オンラインでのマンツーマン指導を実施しています。
社会見学として水族館や博物館への訪問なども行っており、普段なかなか体験できないような機会を提供することで、子どもたちの視野を広げる活動も行っています。
さらに、家庭教育支援の一環として、保護者向けの子育て勉強会や個別相談会、幼児教室なども月1回開催しています。これらは保育士を中心としたスタッフが担当し、専門的な知見を活かした支援を提供しています。
子育て世代に寄り添う支援の形
ー子育て支援についての具体的な取り組みを教えてください。
乾さん:「マミーズカフェ」という取り組みでは、子育てに悩むお母さんたちに向けて、月1回、保育士や子育て経験豊富な方々との交流の場を提供しています。昼食を共にしながら子育ての悩み相談ができ、その間、お子さんは保育士の見守りのもと遊ぶことができます。
現代社会が抱える3つの貧困への対応
ー現状どのような課題を感じていらっしゃいますか。
乾さん:私たちは3つの貧困に対する社会課題の解決を目指しています。1つ目は経済的貧困です。これについては、月1回、ひとり親や子育て困窮家庭45世帯、約100人以上の方々に夕食の提供や食料品、文具などの支援を行っています。
2つ目は「つながりの貧困」です。子育ての悩みを相談できる相手がいない、学校でのいじめ問題に対して誰に相談したらよいかわからないなど、社会的なつながりの欠如が問題となっています。
3つ目は「経験の貧困」です。核家族化が進み、親になるまで子どもを抱いたことがないという母親が多く、子育ての経験不足が様々な問題を引き起こしています。また、コミュニケーションを取る機会の減少により、発達障害や引きこもりの傾向がある子どもも増えています。
新しい学びの形「EDUCARE」の展開
ー課題解決に向けた具体的な取り組みについて教えてください。
乾さん:昨年から「EDUCARE」という新事業を立ち上げ、より専門的な学びの場を提供しています。例えば、芸術系の進学を目指す子どもたちへのアニメイラスト講座や、プログラマーを目指す人向けの基本情報技術者資格取得講座、ジュニアプログラミング検定対策講座などを、低価格で提供しています。
現在、奈良県で最も規模の大きな子ども食堂運営団体となり、年間延べ6000人の方々が活動に参加し、活動日数も300回を超えています。
子ども食堂というと経済的に困っている方のための食事提供の場というイメージが強いかもしれませんが、私たちは様々な学びの機会を提供する場として、より広い支援を目指しています。
子どもたちの未来を支える活動へのメッセージ
ー最後に、記事を読まれている方へメッセージをお願いします。
乾さん:私たちが目指すものは、子育て家庭における貧困や社会的な孤立、子どもの教育格差・体験格差の解消です。どのような子どもたちであっても、自分の夢を描き、それを実現できる社会を作っていくために、私たち大人がその社会をリードしていく必要があります。そのような観点から、私たちは教職と食育、様々な学びを通じて子どもたちの生きる力を育む活動を行っています。
子ども食堂と聞くと、経済的に困っている方が利用する食事提供の場というイメージをお持ちの方が多いかもしれません。確かに、多くの子ども食堂がそうした役割を担っていますが、私たちの活動はそれに加えて、子どもたちが社会で育っていくための様々な学びの機会も提供しています。
ぜひホームページをご覧いただき、お子様の興味のある分野や、ご自身が支援者として参加できそうな活動を見つけていただければと思います。ボランティアとしての参加も大歓迎です。子どもたちの未来のために、皆様のご支援とご参加をお待ちしています。