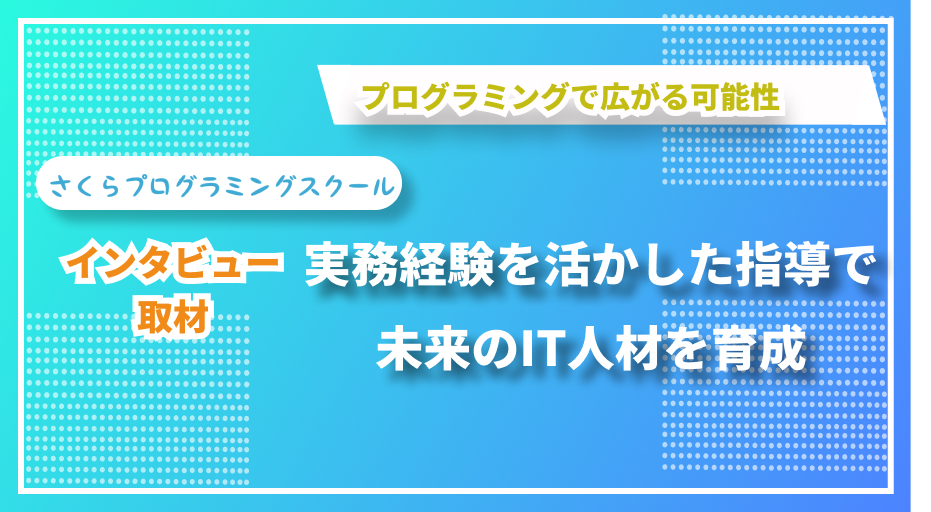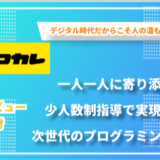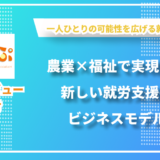青森県で展開するさくらプログラミングスクールは、小学生から高校生を対象としたプログラミング教室です。独自の指導方針により、生徒一人ひとりの個性と興味を大切にした指導を行っています。
プログラミング教育必修化の時代に、地域からIT人材の育成を目指す取り組みについて、同スクールの櫻木さんにお話を伺いました。
生徒の自主性を重視した柔軟な指導体制

ーまず、教室の概要について教えてください。
櫻木:小学生から高校生までを対象としており、現在は主に小学生と中学生が在籍しています。カリキュラムとしては、Scratchやマインクラフト、LEGOのマインドストームを使用したコースを用意しているほか、生徒の希望に応じた個別指導も行っています。
当スクールの特徴は、生徒の自主性を尊重する指導方針にあります。基本的な内容は指導しますが、その後は生徒が何を考え、何をやりたいのかを重視しています。
決められたカリキュラムをただこなすのではなく、基礎を学んだ上で生徒の興味に従って学習を進められる環境を整えています。
経験と時代のニーズが導いた教室開設
ー教室を始められたきっかけについて教えてください。
櫻木:私自身、高校時代からパソコンに親しみ、大学でも情報系を専攻していました。その後、20年ほど別の業界で働いていましたが、5年前に起業を機に新たな挑戦を考えました。
当時は高齢者向けのサービスに携わっていたのですが、これからの未来を担う若い世代の育成に携わりたいという思いが芽生えてきました。そこで自分のスキルを振り返った時に、プログラミング教育という選択肢が浮かび上がってきたんです。
ちょうどそのタイミングで、学校教育においてプログラミングが必修化されるという時代の流れもあり、このタイミングでスクールを始めることを決意しました。
実務経験を活かした実践的な指導
ー他の教室にはない特徴やアピールポイントを教えてください。
櫻木:私自身がプログラミングの実務経験を持っているため、その楽しさや難しさを十分に理解しています。保護者の方からお聞きする話では、多くのスクールが決まり切ったカリキュラムで、イレギュラーな事態に対応できないケースが多いようです。
当スクールでは、生徒が行き詰まった際に一緒に考え、「こうすればもっと良くなるのではないか」といったアドバイスができる点が強みです。実際にプログラミングの仕事に携わった経験を活かし、柔軟な指導を心がけています。
将来を見据えた段階的な学習支援
ー指導する際に特に意識されていることはありますか?
櫻木:プログラミングを通じて、学校の授業よりも少し先の内容も紹介するようにしています。例えば、小学校では学ばないマイナスの数字や、中学校で習わない三角関数などについても、プログラミングの中で簡単に触れるようにしています。
将来の学習内容を先取りして知っておくことで、実際に学校で習う際の理解度が深まると考えています。完全な理解を求めるのではなく、「プログラミングスクールでこんなことをやったな」と思い出してもらえれば十分です。
多彩なコース設計で楽しみながら学べる環境を提供
ーどのようなコースを提供されていますか?
櫻木:現在、主に3つのコースを提供しています。1つ目は、MITが開発したビジュアル言語「Scratch」を使用するコースで、プログラミングの基礎を学ぶ入門として最適です。
2つ目は、マインクラフトの教育版を使用するコースです。スクラッチがベースとなっていますが3D表現が可能なため、空間的な認識を深められる特徴があります。
3つ目は、LEGOのマインドストームを使用したロボットプログラミングコースです。実際に動くロボットを通じてプログラミングを学ぶことで、機械工学への興味にも繋がると考えています。
地域全体のIT教育の底上げを目指して
ー今後の展望についてお聞かせください。
櫻木:青森県はIT教育においてまだ発展途上の段階にあります。そのため、子どもたちだけでなく、保護者世代のIT教育への理解と関心を高めることが、地域全体の教育レベル向上には不可欠です。
今後はそれを実現するための具体的な取り組みを検討し、青森県の子どもたちが他県に遅れを取ることのないよう、教育環境の整備を進めていきたいと考えています。
ー最後に、入会を検討されている方へメッセージをお願いします。
櫻木:これからの世界では、人工知能をはじめとするIT技術がますます重要になっていきます。そうした時代の中で、子どもたちが世の中に置いていかれることなく、むしろ先導する立場になれるようサポートしていきます。