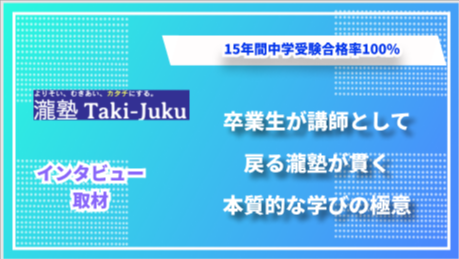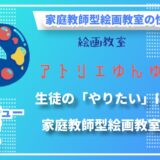昨今、子どもたちの学力低下や学習意欲の減退が懸念されている中、千葉県のある学習塾が注目を集めています。その塾では、「勉強嫌い」だった子どもたちが自ら学ぶ喜びを見出し、3-4時間も集中して学習に取り組むようになるといいます。さらに驚くべきことに、15年以上の歴史の中で、中学受験に挑戦した生徒全員が志望校への合格を果たしているのです。
この塾の名は「瀧塾」。塾長の瀧澤大氏は「教育とサービスは異なる」という信念を持ち、大手学習塾とは一線を画した独自の教育メソッドを実践しています。講師は全員が卒業生という特徴的な運営体制や、生徒一人一人に寄り添った丁寧な指導は、従来の学習塾の概念を覆すものです。
今回は瀧澤塾長に、その革新的な教育理念と具体的な指導方法について、詳しくお話を伺いました。

「覚えさせられる」から「自然に身につく」学びへ
ー多くの生徒さんが、驚くほど集中力を発揮されているそうですね。その秘訣を教えてください。
瀧澤:実は私自身も勉強が嫌いでした。なぜ嫌いだったのか。それは「覚えさせられる」という受け身の学習が最大の理由だったと思います。子どもたちも同じです。だからこそ、自然に学んでいけるような環境作りを最も重視しています。
当塾の特徴の一つは、講師が答えを教えないということです。必ずヒントを出して、最後は生徒に答えを言わせます。特に算数と国語については、一緒に考えていく時間を大切にしています。出すヒントの質によって、生徒が答えにたどり着けるかどうかが決まってきます。
このアプローチには、いくつかの重要な利点があります。まず、生徒が自分で考える力を養えます。そして、答えにたどり着いた時の達成感が、次への意欲につながります。さらに、この方法では小学校3年生でも3-4時間、集中して学習を続けることができるんです。
ー3-4時間も休憩なしで学習するのは、小学生には負担ではないでしょうか?
瀧澤:実は、私たち大人が考えているほど、子どもたちの集中力は脆弱ではありません。むしろ、10分間の休憩を入れることで、せっかくの集中力が途切れてしまうことの方が多いのです。
もちろん、体調管理には十分注意を払っています。具合が悪くなった生徒には、外で空気を吸って休憩するよう促します。また、お手洗いなどの生理的な休憩は自由に取れます。大切なのは、形式的な休憩時間を設けることではなく、生徒一人一人の状態に応じた柔軟な対応です。
個別最適化された学習環境の実現
ー教室では学年の異なる生徒が一緒に学習していると伺いました。どのように個々の生徒の学習を管理されているのでしょうか?
瀧澤:当塾では、教材選択から指導方法まで、完全に個別最適化を図っています。四谷大塚、サピックス、日能研といった大手塾の教材は、どれも優れたものです。これらの教材であれば、適性検査から一般入試まで十分に対応できます。
ただし、重要なのは教える側の質です。同じ教材でも、生徒によってヒントの出し方を変える必要があります。そのため、生徒一人一人の特性を見極めて、最適な教材と指導方法を選択しています。
教室には、学年がバラバラの生徒がいますが、全員の進捗状況は私が把握しています。生徒から質問が出るのを待つのではなく、表情を見て、こちらから積極的に声をかけることを心がけています。
感情と記憶をつなぐ独自の学習メソッド
ー暗記に苦手意識を持つ生徒も多いと思います。どのようなアプローチをされていますか?
瀧澤:暗記の問題で最も多い相談が、「覚えても直ぐに忘れてしまう」というものです。その原因の多くは、アプローチの仕方にあります。
例えば100個の単語を覚える場合を考えてみましょう。多くの生徒は最初から終わりまで一気に見てしまい、結果として7、8個しか覚えられません。また、1日目に1から10まで、2日目に11から20までというように区切って覚えようとする方法も、効果的ではありません。なぜなら、前日の学習内容が定着する機会がないからです。
当塾では、以下のような方法を採用しています:
- 1日目:1から10まで
- 2日目:1から20まで(前日の復習を含む)
- 3日目:1から30まで このように、既習内容を含めて学習を重ねていきます。
一見すると時間がかかりそうに思えますが、実際にはそうでもありません。1から10を覚えた経験が、次の学習をスムーズにするからです。例えば、1から100までの暗記に必要な時間は、予想の3分の1程度で済むことも珍しくありません。
本質的な学びを目指す中学受験指導
ー中学受験に対する瀧塾独自の考え方について教えてください。
瀧澤:中学受験は、勉強の本質を理解する絶好の機会だと考えています。単なる暗記や問題演習ではなく、なぜその知識が必要なのか、どのように活用できるのかを理解することが重要です。
例えば、参考書や問題集は100点を取ることを目標に作られています。しかし、実際の入試では満点を取る必要はありません。むしろ、どの部分で点を落としても良いのか、どこを確実に押さえるべきかを戦略的に考えることが大切です。
当塾では、科目や生徒によって異なりますが、例えば算数なら55%の正答率で十分だと伝えています。つまり、45%は間違えても良いのです。このように、完璧を求めすぎない姿勢が、かえって生徒の精神的な負担を軽減し、効果的な学習につながっています。
卒業生が紡ぐ教育の継承
ー講師陣の特徴について教えてください。
瀧澤:当塾の最大の特徴の一つは、講師全員が卒業生だということです。これまで講師募集をかけたことは一度もありません。彼らは自分が受けた教育を次の世代に伝えたいという強い思いを持って、講師を務めています。
実際に、ある卒業生は「1年間給料はいらないから、この塾のやり方で教える練習をさせてほしい」と申し出てきました。現在その生徒は、千葉県でナンバーワン理科教師として表彰されるほどの優秀な教員になっています。
時給で働いているわけではない彼らは、生徒との時間を惜しみなく共有します。夜遅くまで生徒と向き合うこともありますが、それは決して強制ではありません。むしろ、「もう帰ってください」と言っても、生徒たちが自ら学び続けたいと願うのです。
生徒の人生に寄り添う教育者として
ー進路指導についての考え方を教えてください。
瀧澤:よく「進むべき道は自分で考えなさい」と言われますが、特に中学受験の段階では、それは適切ではないと考えています。行ったことのない学校について、生徒自身が正しく判断するのは難しいものです。
そのため、生徒の適性を見極めて、私が方向性を示すことがあります。これまでの経験上、その選択はほとんどの場合で正しかったと感じています。例えば、ある生徒は現在幼稚園の園長として活躍していますし、別の生徒は司法試験に合格して法曹界で活躍しています。
重要なのは、その生徒に合った道を見つけることです。東大に行くことが全ての生徒にとって正しい選択とは限りません。一人一人の適性や興味を見極めて、最適な進路を提案することを心がけています。
心と心をつなぐ教育の実践
ー最後に、入塾を考えている方へメッセージをお願いします。
瀧澤:当塾には入塾テストはありません。まずは相談に来ていただければと思います。特に中学受験については、保護者の方のお考えもとても重要です。最初の面談では、3時間程度かけてじっくりとお話を伺います。
その際、私からの質問が多くなります。「幼稚園の時はどんな様子でしたか?」「ご家庭ではどんな過ごし方をしていますか?」といった具合です。それは、お子様のことを深く理解したいからです。
時には「来年から始めた方が良いのではないでしょうか」とアドバイスすることもあります。なぜなら、私たちは単なる学習塾ではなく、親族のような関係性を築きたいと考えているからです。
お子様の成長に関する悩みや不安など、どんなことでもご相談ください。成績の向上はもちろん大切ですが、それ以上に大切なのは、お子様が自ら学ぶ力を身につけることです。その過程で、私たちは全力でサポートさせていただきます。
15年以上の実績の中で、中学受験生は全員が志望校に合格しています。しかし、それは結果であって目的ではありません。私たちが本当に目指しているのは、生徒一人一人が「学ぶ喜び」を発見し、自らの力で成長していける環境を作ることなのです。