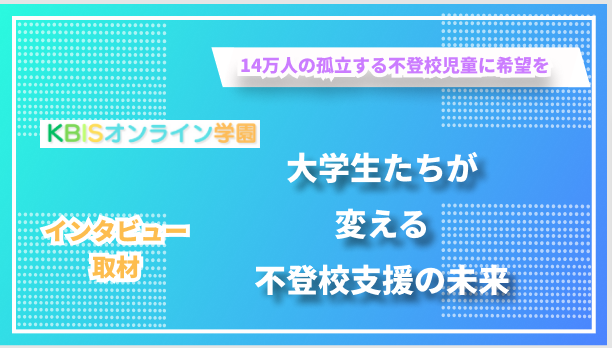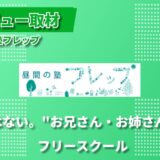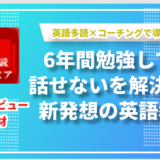不登校児童生徒数が過去最多の35万人を超え、その増加に歯止めがかからない日本の教育現場。特に深刻なのは、その40%にあたる14万人の子どもたちが、学校にもフリースクールにも通えず、支援から孤立している現状です。
この課題に、革新的なアプローチで挑戦しているのが、KBISオンライン学園です。教育や福祉を目指す現役大学生たちが、オンラインを通じて不登校児童に寄り添う無償の支援プログラムを展開。子ども家庭庁のモデル事業にも選ばれ、注目を集めています。
従来の不登校支援では、支援を受けるためには自ら通う必要がありました。しかし、それが困難な子どもたちこそ支援を必要としているのではないか。そんな思いから始まったKBISオンライン学園の取り組みは、不登校支援における新たな可能性を示しています。35年の教職経験を持つ代表の山田良一氏に、その革新的な支援の詳細と思いを伺いました。
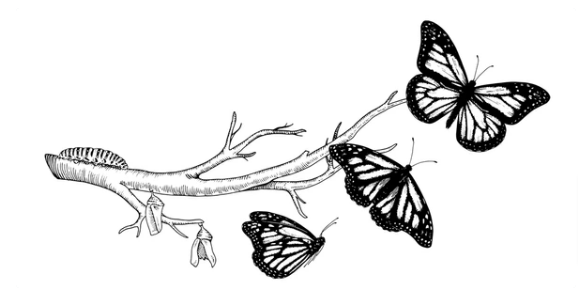
孤立する不登校児童への新たなアプローチ
ー不登校支援における革新的な取り組みについて、ぜひ詳しく教えてください。
山田:当社KBISオンライン学園は、不登校のオンライン支援を基本としています。文部科学省の発表によると、不登校は35万人に達し、15%ずつの増加傾向が続いています。特に気がかりなのは、そのうちの40%、つまり14万人の子供たちがどことも繋がっていない現状です。
従来の不登校支援には、適応指導教室や教育センター、フリースクール、塾など様々な選択肢がありますが、これらのサービスを受けるためには自ら通える必要があります。私たちは、この課題を解決するために、家にいながらにしてオンラインを通じて支援を受けられる環境を提供しています。
教育系大学生との出会いがもたらす可能性
ーほかにはない「KBISオンライン学園」の特徴的な支援体制について、より具体的に教えてください!
山田:私たちの最大の特徴は、支援者として教育や福祉を目指す現役の大学生が関わっているという点です。この事業は3年前に私が勤務する高千穂大学でスタートしました。当初は私の出身地である兵庫県の不登校児童と東京の学生をつなぐところから始まりましたが、現在では支援する大学が6校にまで広がっています。
兵庫教育大学、淑徳大学、東京学芸大学、武蔵野大学など、各地域の教育系大学の学生たちが週に1回60分、オンラインでの相談活動や交流を行っています。学生たちは将来、教育現場で活かせる貴重な経験を得ることができます。
社会的自立を目指す丁寧な支援
ー不登校の生徒さんに寄り添う際に、特に大切にされていることを教えてください。
山田:私たちは文部科学省の方針に沿って、学校復帰ではなく社会的自立を目指す支援を行っています。まずは子どもたちとの関係作りを最優先し、子どもが望むことに寄り添うスタイルを大切にしています。
オンラインという形態は、直接会うことの負担やストレスを軽減できる大きな利点があります。ゲームや音楽など、共通の話題を通じて関係性を築いていきます。年齢が近い大学生だからこそ、子どもたちと自然な会話が生まれ、信頼関係を築きやすいのです。
さらに、支援体制の中核には教育現場を熟知したスタッフが揃っています。退職された校長先生や教員が、大学生と不登校児童をつなぐサポート役として活躍しています。私自身も小学校の教員を35年務めた経験があり、その経験を活かしながら大学生の指導と不登校支援の橋渡しを行っています。
教育を受ける権利を守る「無償の支援」
ー驚くべきことに、支援を完全無償で提供されているとお聞きしました。その思いについて教えていただけますか?
山田:義務教育は法律で無償と保証されています。不登校になった子どもたちの教育を受ける権利を守るためにも、費用負担のない支援を続けていきたいと考えています。運営には確かにコストがかかりますが、不登校になると家庭の経済的負担は既に大きくなっています。そのため、私たちの支援では追加の経済的負担が発生しないよう心がけています。
実際に不登校生徒の支援には様々な場面で費用が発生することが多く、家庭の経済的負担は決して小さくありません。だからこそ、KBISオンライン学園では、教育を受ける権利を守るという観点から、支援を無償で提供することにこだわり続けています。
子ども家庭庁モデル事業としての展開
ー今年度、子ども家庭庁のモデル事業に選ばれたと伺いました。今後の展望についてお聞かせください。
山田:このモデル事業では、将来の教育者・支援者となる大学生と不登校児童の出会いが双方にとって有効であるかを検証しています。教育実習では不登校の生徒と関わる機会がほとんどありませんが、現在の状況を見ると、小学校でクラスに1人、中学校ではクラスに3人程度の割合で不登校の生徒がいます。
4月から教壇に立つ新任教師にとって、不登校への理解と対応は避けて通れない課題です。教育実習では出会えない不登校の生徒との関わりを、学生時代に経験できることは非常に貴重です。その経験は、教師になってからの生徒理解や支援に大きく活かされると確信しています。
行政との連携強化と包括的支援の実現へ
今後は教育委員会との連携を強化し、より包括的な支援を目指していきます。特に課題となっているのが、情報格差の解消です。学校やフリースクールとつながっている家庭は情報を得やすいのですが、どことも繋がっていない家庭は情報から孤立しがちです。
私たちは、オンラインをベースとしながら、フリースクールや学校への橋渡し支援など、アウトリーチ活動も展開していきたいと考えています。支援は高校進学後も継続することがあり、大学生の「お兄ちゃん・お姉ちゃん的存在」として、長期的な関係性を築いていることが特徴です。一歩外に踏み出してみても、また戻ってきてしまう生徒にも、継続的なサポートを提供していきます。
活動継続への課題と支援のお願い
ー今後の活動における課題について、お聞かせいただけますか?
山田:今年度は子ども家庭庁のモデル事業として選定され、安定した運営のもと、保護者の方々に無償での支援を提供できています。しかし、このモデル事業は単年度の取り組みであり、来年度以降も同じ形で支援を継続していくためには、新たな支援の枠組みが必要となります。
特に重要なのは、支援してくださる大学生の存在です。現在、多くの学生が学業と生活の両立に苦心しながら、熱意を持って活動に参加してくれています。私たちは、その献身的な努力に報いるため、ボランティアではありますが、活動に対して時間単位での報奨金をお支払いできる体制を整えています。
この「大学生による不登校児童のためのオンライン居場所づくり」を継続し、さらに発展させていくためには、教育経験者によるサポート体制の強化と、活動に賛同してくださる企業や個人の方々からのご支援が不可欠となります。
不登校の子どもたちは、決して特別な存在ではありません。むしろ、多様な経験を経て、将来、社会の様々な場面で活躍する可能性を秘めた存在です。企業経営者の皆様には、彼らが将来、皆様の企業でも大きな力を発揮する可能性があることを、ぜひ念頭に置いていただければと思います。
私たちの活動にご賛同いただける方は、下記の方法でご支援いただけます:
[※編集部註:KBISオンライン学園への支援方法について、詳しくは公式サイトをご覧ください。また、本件に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いいたします。]この活動を通じて支援した子どもたちの中から、すでに高校や大学に進学し、新たな一歩を踏み出している例も出てきています。一人でも多くの子どもたちの未来を支えられるよう、皆様のお力添えを心よりお願い申し上げます。
見えない成長を支える温かな支援
ー最後に、今まさに不安を抱えていらっしゃる保護者や生徒の方々へ、山田先生からメッセージをお願いします!
山田:私は常々、不登校の時期を植物の成長に例えてお話ししています。人の成長には、木の枝や葉が伸びていく「目に見える成長」と、根が地中でしっかりと張り巡らされていく「目に見えない成長」があります。不登校の期間は、まさにその根を張る大切な時期なのです。表面的には何も変化が見えなくても、確実に強い根を育んでいるのです。
また、保護者の方々には、さなぎの姿を思い浮かべていただきたいと思います。さなぎは一見すると動きが見えず、何も変化していないように映ります。しかし、その静かな時期にこそ、大きな変容が起こっているのです。この時期に必要以上に干渉してしまうと、羽化の際に影響が出てしまうことがあります。だからこそ、この時期は焦らず、じっくりと見守ることが大切なのです。
私たちKBISオンライン学園は、そんな大切な成長の時期にある子どもたちと、その子どもたちを支える保護者の方々に寄り添い、共に歩んでいきたいと考えています。必ず、その子らしい羽ばたきの時が来ると信じています。