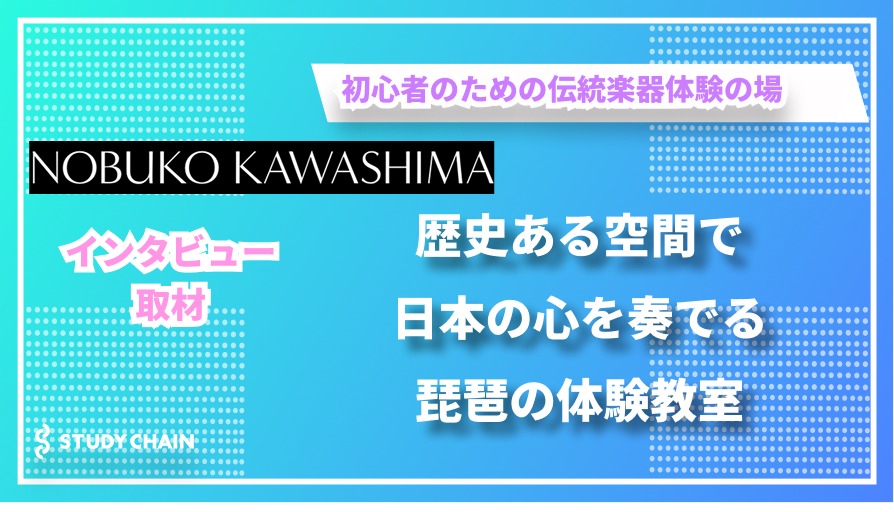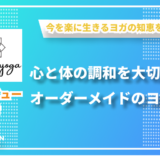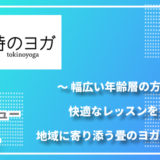日本の伝統楽器である琵琶を気軽に体験できる教室「まなびわ」。歴史ある古民家での体験と、敷居の高さを取り除いた温かな雰囲気が魅力です。
川嶋さんに、教室の特徴や指導方針についてお話を伺いました。
築100年の蔵で行う伝統楽器・琵琶の体験

ー教室の概要についてお伺いさせてください。
川嶋:月に一度、東京の千駄木にある築100年の「記憶の蔵」という場所で、琵琶の体験教室を開催しています。
琵琶は、多くの方が見たことも聞いたことも触ったこともない楽器です。そのため、小さなお子さんからお年寄りまで、どなたでも琵琶に触れていただくことを目的としています。
私が使用している薩摩琵琶は楽器自体が大きく、演奏に使うバチも顔くらいの大きさがあるため、小学校高学年くらいからでないと扱うのは難しいです。
ただ、興味を持ったお子さんが来られなくなるのはもったいないので、親御さんと一緒に来ていただき、何らかの形で体験できるようにしています。
震災がきっかけで生まれた教室
ー教室を始められたきっかけや経緯について教えてください。
川嶋:教室は2011年の秋に始めましたので、今年で14年目になります。東日本大震災の時に、音楽や芸能に携わる者として自分の無力さを感じました。
しかし、自分がこの道を仕事として選んだからには、何か小さなことでも始めて続けていこうと思いました。
琵琶の演奏活動を続けていると、聴きに来た方から「初めて聴きました」「どこで聴けるんですか」といった質問をされます。
それならば、気軽にどなたでも来て琵琶に触れ、音を聴き、琵琶について知ることができる場所が、必ず月に一度あればいいなと思い始めました。
特別な空間で自然素材の楽器に触れる体験
ー教室独自の特徴や、一番のアピールポイントを教えてください。
川嶋:アピールポイントは、普段出会えない琵琶を気軽に体験できることです。和楽器のお稽古となると、きちんとした格好でなければいけないのではという問い合わせがよくありますが、構えずに楽しみに来ていただければと思っています。
また、築100年の蔵をお借りしているのは、空間も含めて記憶に残るような体験になってほしいからです。
琵琶本体は無垢の木、弦は絹糸でできた自然素材の楽器で、歴史ある建物としっくりと馴染みます。蔵という空間の中で響く音や空気感も一緒に楽しんでいただけたらと思い、この場所で開催しています。
楽しむことから始まる琵琶との出会い
ー生徒に指導する際に、特に意識していることや方針などを教えてください。
川嶋:まずは琵琶に触れて楽しんでいただくことを大切にしています。実際に自分で楽器を持って音を出すことは、誰かの演奏を見聴きするのとは全く異なる体験になります。
最初に、琵琶の種類や歴史についてお話をします。琵琶の中でも体験するのは薩摩琵琶という楽器であることや、他の種類の琵琶の魅力などもお話してから、実際に触れていただきます。
通常は3人程度の少人数で行うので、参加者同士の交流が生まれます。皆さんで息を合わせて楽器の音を出す体験をし、全員の音が合わさった時の響きを蔵の空間で聴く楽しさを味わっていただいています。
また、琵琶は本来、歌を歌いながら弾き語る楽器です。声を出すところまでは至らないことが多いのですが、機会があれば発声練習からのレッスンも行っています。
継続と進化の狭間で
ー今後より強化していきたい部分や、取り組んでいきたいことがあれば教えてください。
川嶋:皆さんの知っているメロディを演奏してもらったり、複数回で完結するコースを設定したりするなど、次の段階も考えています。しかし、琵琶があまりにも知られていないという現実があります。
琵琶の演奏者の数が少ないため、すそ野を広げる活動は必要ですが、本気で習いたい人に来てほしいという思いと、どんな方でも気軽に触れてほしいという思いの間で葛藤しています。
すそ野を広げる役割を担いながらも、次の段階への進化を模索しています。
日本の文化を身近に感じるきっかけに
ー最後に、この記事をご覧の方に向けたメッセージをお願いします。
川嶋:私はたまたまこの楽器に出会い仕事にしていますが、多くの方はこの楽器に出会う機会がありません。
琵琶は日本独自の楽器です。改めて自分の国の文化に触れることの大切さを、多くの方にも体験していただきたいと思っています。もちろん、日本の文化に触れたい外国の方の参加も大歓迎です!