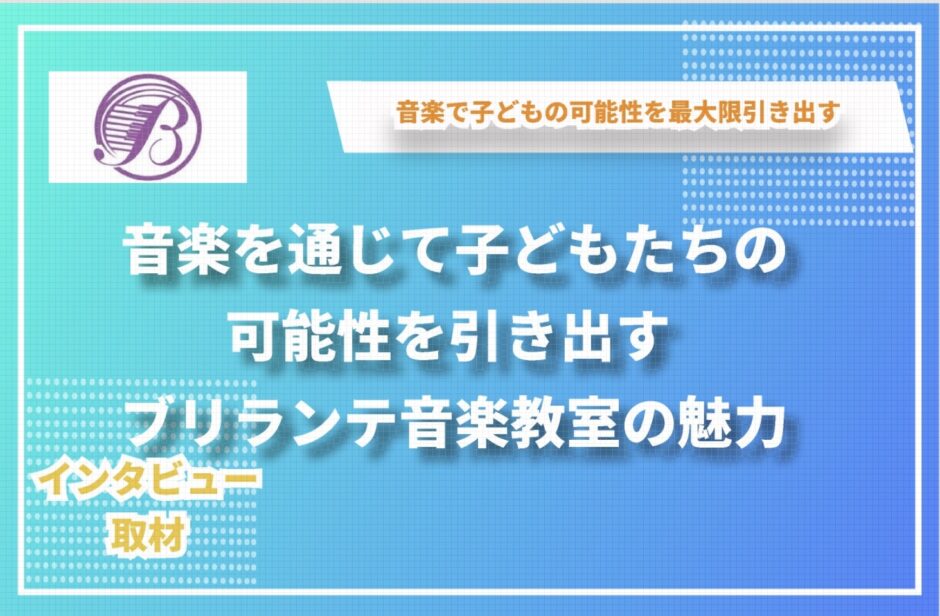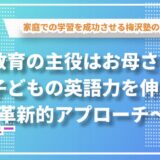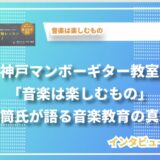ブリランテ音楽教室では、音楽の楽しさを第一に考えた指導を行っています。長年の教育経験を活かし、一人ひとりの個性に合わせたレッスンで、躓きやすいポイントを素早く見極め、最短で上達へと導きます。幼児教育から大人のレッスンまで、音楽の喜びを伝える教室の魅力に迫ります。

他で上手くいかなかった生徒を伸ばす独自の指導法
ー教室の概要について教えてください!
私の教室のコンセプトは、他で上手くいかなかった方を伸ばす教室というものです。音楽はとても素敵なもので、ピアノを上手にきれいに弾けるようになりたいという気持ちで習い始める方が多いと思います。しかし、技術習得はなかなか難しく、皆さんそれぞれに躓きや悩みが出てくるのです。
まず重点を置いているのは、楽譜を読むということを短期間でスムーズに上手になることです。その後、きれいな音色でリズム感やテンポも曲に合ったもので弾き、自分の感情を入れて弾けるようになるのが理想です。特に難しいところで躓いてしまうポイントをいかに短い時間で楽して上手になるかということを大切にしています。
これまで大学の講師も含め1000人近くの生徒さんを指導してきましたので、その方の状態を見ると、どこで躓いているか、どういう練習をすると一番速く到達するかが一瞬で分かります。笑顔を持って「練習楽しいよ」という風にして、2、3回の練習でそこをクリアし、「できた!」の瞬間をたくさん増やして、もっとやってみたいという気持ちでお家に帰って頂くことを大事にしています。
ピアニストから教育者へ – 音楽の魅力を伝える使命
ー教室を始められたきっかけや経緯について教えてください!
音大のピアノ科を卒業し、大学院を出て留学もしました。5、6歳から夢であったピアニストの道を歩み始めたのですが、手が小さいこともあって、練習のやり過ぎで手を壊しかけたことがあります。自分で弾くことも大切でしたが、この素晴らしいピアノ音楽を皆さんに体得していただきたいと思いました。プロを目指す方だけでなく、小さいお子さんや大人になってから弾けるようになりたいという方にも、彩り豊かに弾けるようにお手伝いできるのではないかと考え、教育の道を選びました。
ちょうどその時、大学からレッスンの授業を依頼され、大学講師になりました。80人〜100人ほど教える生活が始まり、それを20年ほど続けました。大学生たちは年に4回のピアノ試験があります。いかに高い目標へのやる気を起こさせ、上達させ、達成感を味合わせるか。一人ひとりに合った指導をする。…こちらは必死だけれど、それを見せず笑顔で育てていく。その連続でした。しかし、18歳人口の減少により大学が学部を縮小することになり、ピアノを学ぶ学生も減ったため、そのキャリアを一旦終えることになりました。
まだ余力もありますし、自分の経験値も豊富にあるので、1から音楽教室を開いて自分の教室をやっていきたいと思いました。母が長年英語教室をやっていた教室をフルリフォームし、グランドピアノを入れてきれいな教室で音楽を学んでいただきたいと思い、昨年開始しました。
リトミックからピアノへ – 音感とリズム感を育てる総合的なアプローチ
ー他の教室にはない特徴や、教室としての一番のアピールポイントを教えてください!
音楽は音感とリズム感がとても大事です。なくても楽しめますが、あればより楽しめるものです。小さいお子さんは手も小さく弱いので、いきなりピアノを弾くのはハードルが高いのです。そこで私はリトミックの資格を取得し、2歳3歳のお子さんからでも音感を楽しく学べるよう工夫しています。
絶対音感をつける目標はありますが、とにかく楽しくなければお子さんもやる気になりませんので、ピクチャーカードや鈴、タンバリン、フラフープなど体も使いながら音感を育てています。特に即時反応として、楽しい音楽を弾いていて高い音が鳴ったらジャンプしたり、低い音が鳴ったらしゃがんでみたりと、音を聞いて反応する力を養います。
ストーリーの中で「今日はお天気がいいからお山にお散歩に行こう」というようにスキップしてリズムを感じたり、「山登りは大変だ。よいしょ、よいしょ」という重くて長いリズムで表現したり。逆に「野原が出てきてお花も咲いているね、楽しく走ってみよう」と軽やかで速いリズムを手で打って感じてみたり。リズム感や音感を育てています。
このようにして、ピアノやバイオリンなどの楽器への道をスムーズに、抵抗なく、しかも楽しんで進めるようにしています。小さいお子様にはリトミックから音感とリズム感をつけ、5、6歳のお子さんはそれと並行してピアノのレッスンをある程度しっかり行います。「しっかり」とは厳しくということではなく、よりきれいな音楽になるよう最短の道を探りながら、来週も来たいと思われるようなレッスンを目指しています。
一人ひとりに寄り添うオーダーメイドの指導
ー現在受講されている方々に指導する際に意識していることや、教室全体としての方針があれば教えてください。
お子さん一人ひとりの個性が違いますし、男の子と女の子でも特性は違います。まず笑顔で出迎え、この子は何が好きで何をやりたいのかをとにかく観察し、ありのままの気持ちを汲み取ることを大切にしています。
例えば、お母様がさせたくてもお子さんがあまり乗り気でない場合は、まず「楽しい、面白い」ということを前面に出します。ピアノから離れて絵本を見せ、絵本の色合いや物語を見ながら「こんな音楽どう?」と私が弾いたり一緒に歌ったりすることから始めることもあります。
また、本人がやりたいけれど上手くいかずに「つまらないな」と感じているお子さんもいます。どこで躓いているのかを見極め、練習の話ばかりではなく、できあがりを見せて聞かせ、「こうなるには、ここをこうするとそうなるんだよ、やってみよう」という心掛けを常にしています。
とにかく一緒に歩むという姿勢を見せながらも、私の中では次はこういう順番で提案しようと考えています。ただ、2〜3回のレッスンで完璧にできるまでさせるということはしません。そういった積み重ねの中で、自然とできるようになってくるものです。短い練習でその子の気持ちを汲み取りながら進めることが、私の指導の一番のポイントだと思います。
集団レッスンの可能性 – お友達と共に学ぶ喜び
ー今後、さらに強化していきたい取り組みについて教えてください。
現在は個人的に1対1でレッスンしていますが、今後は少し集団で3、4人で楽しく学べる方法を掘り下げていきたいと思っています。特に小さいお子さんは、お友達と一緒にやることで切磋琢磨できるのです。「あの子ができるなら自分もできるんじゃないか」「あの子より先にできるようになりたい」「仲良しだから一緒にできるようになりたい」など、お友達がいると様々な感情が湧いてきます。
「皆で一緒に頑張ろう」という初期段階として、楽しいイメージで意欲を高めていきたいです。そういう気持ちを持ってもらえると、多少の躓きや大変なことがあっても比較的簡単に乗り越えていくことができます。ですから、3、4人の集団グループを作って、前向きな気持ちをさらに強化していきたいと考えています。
ピアノで広がる音楽の世界 – 楽しく学ぶことの大切さ
ー最後に、今後ご入会を考えられている生徒さんや保護者の方々へメッセージをお願いします!
ピアノはとても素敵なもので、一人で音楽を完結することができます。弦楽器やフルートなどもとても素敵ですが、それらは基本的にメロディーだけの楽器です。一方、ピアノはメロディーがあって伴奏があって、様々なハーモニーを織りなすことができるので、一人で音楽を作り上げることができるのです。
その楽しみを、苦しく習得するのではなく、いかに楽しく幸せな気持ちになっていただくかというところに力を入れています。楽しくレッスンに来ていただいて、様々なことを学びながらも「来てよかった、来週も来よう」という気持ちになって帰っていただきたいと思っています。
特に最初に申し上げた通り、これは、私自身が6歳から習った先生がものすごく厳しくて泣きながらレッスンを受けた、という事があります。先生は素晴らしい高度なテクニックと高い音楽性を兼ね備えた日本を代表するピアニストでした。
私の場合は先生のピアニズムが素晴らしいので歯を食いしばって泣きながらついていきましたが。できるなら、もっと楽しく習得したかった…その想いがあります。
私が得たもの全てを皆さんに受け取って頂きたいのです。他で躓いている方、「もうピアノはやめる、つまらないからいい」というお子さんや、「半年や1年たっても上達している気がしない、他の習い事の方がいいのではないか」とお悩みのお母様方にもぜひ来ていただきたいです。ピアノは自分の内面を豊かにしてくれますから、笑顔の指導を受けに来ていただき、目の前で上達する実感を感じていただきたいと思います。