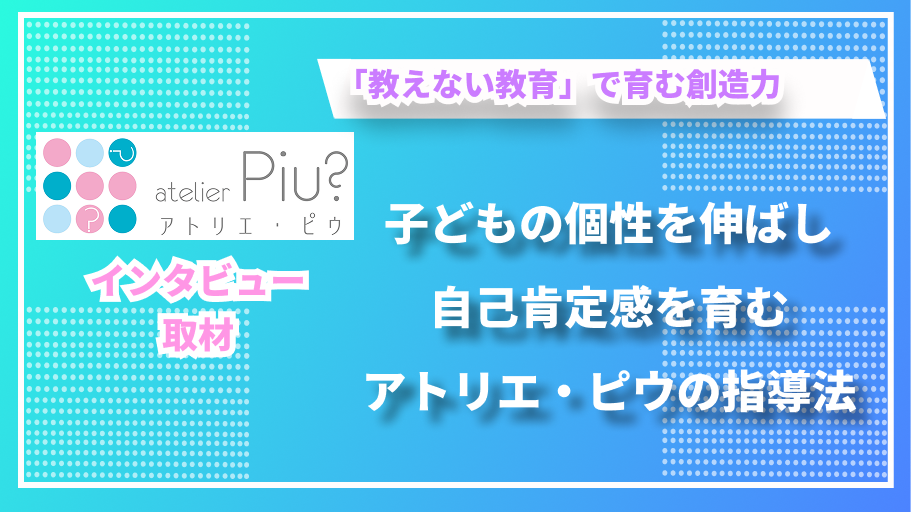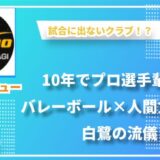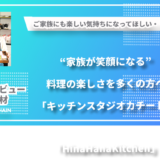アート教育を通じて子どもたちの創造力や自己肯定感を育む、アトリエ・ピウ知育こどもアート教室。
「教えない教育」という独自の教育方針や指導方法について、同教室代表の今泉さんにお話を伺いました。
幅広い活動で子どもの好奇心を刺激する

ー教室の概要について教えてください。
今泉:幼稚園児、小学生、中学生を対象としたアート教室で、絵画や工作に取り組んでいます。それ以外にも、料理や裁縫、屋外でのワークショップなど、子どもの好奇心を刺激して、手と頭を動かすことなら何でも取り入れています。
年間を通じたプログラムがあり、全日本こども美術展などのコンクール出展に向けた制作や、クリスマスやハロウィンなどの季節に合わせた工作も行っています。
作品づくりの際は、大人が思う「正解」を押し付けるのではなく、子どもの好奇心が赴くままに、自由にのびのびと創作できる環境を整えています。

天気の良い日は外で描くと気持ちいい
イギリスと日本、二つの教育観から生まれた教室
ー設立のきっかけについて教えてください。
今泉:イギリスでの5年間の留学経験を活かし、「イギリスと日本の教育、それぞれの良いところを取り入れたアート教室を開きたい」と考えていました。
もともとは日本でジュエリーデザイナー、イギリスではシアターデザイナーとして活動していましたが、子育てを始めたことをきっかけに、13年前にアート教室を開設しました。
「創造力や発想力が豊かな大人になってほしい」「アート思考を取り入れたい」「ゼロから1を生み出せる子どもになってほしい」など、アート教育への期待が高まる中、そのニーズに応えられるよう日々精進しています。

アットホームな雰囲気のアトリエ
独自のアクティブラーニングで育む創造性
ー教室ならではの特徴やアピールポイントについて教えてください。
今泉:最大の特徴は、アクティブラーニングを取り入れ、子どもたちが能動的に学習できる場を設けている点です。
例えば、「新宿区子育てメッセ」や「四谷文化祭」では、当教室の生徒たちが先生となって、来場者の子どもたちにアートを教えるワークショップを開催しています。
公的機関が主催する本格的なイベントで、初対面のお客様に教えるという経験は、子どもたちにとって大きな成長の機会となっています。
社会貢献をしているという実感や、知らない方から「ありがとう」と言われる経験を通じて、子どもたちの自己肯定感が高まっています。この取り組みは10年以上続けており、「早く先生になりたい」と、子どもたちも楽しみにしている活動です。
このようなワークショップに幼児期の子どもたちが挑戦しているのは、世界でも大変珍しい取り組みではないかと自負しています。

アトリエ生がご来場のお子様に工作を教えるワークショップ
子ども自身に考えさせる「教えない教育」
ー指導をするうえで大切にしていることを教えてください。
今泉:子どもたちが常に自分で考え、自分の力で形にする「教えない教育」を実践しています。
「どうしたらいいですか?」と大人の力を頼ろうとする子どもに対して、「こうすればできるよ」と教えるほうが簡単ですが、それでは本当の意味で子どもの力を伸ばすことにはなりません。
子ども自身が試行錯誤して、答えにたどり着くよう導くことが大切です。主体的な行動を妨げずに見守ることで、発想力や創造力を育んでいます。
また、制作のペースも一人ひとり異なり、パパッと取り組んですぐに終わる子もいれば、じっくり時間をかける子もいます。どちらが正解というわけではありません。
早く終わる子は瞬発力があり、アイデアを素早く形にする力を持っています。時間をかける子は丁寧に考え抜く力があります。それぞれの持ち味として捉え、伸ばしていくことを心がけています。
その日の体調や気分によっても子どもの様子は変わります。学校で嫌なことがあったり、疲れていたりする日もあります。5、6年生になると思春期に入り、表現の仕方も変化してきます。
そういった状況をよく観察し、その時々に合わせた声かけや指導を心がけています。

毎年作品展を開催し、達成感を得る体験をします
正解を決めない指導と「上手い・下手」で評価しない重要性
今泉:大人はついやり方を教え、次々と指示を出してしまいがちです。しかし、それでは子どもはただ指示された作業をしているに過ぎません。
私たちは素材を提供し、「これで何ができるかな?」と問いかけ、「自分で考え、自分で形にする」という方針に基づいてクリエイティブな力を身につける訓練をしています。
子どもが自分なりに考え模索して、ようやく作りたかったものができたとき、初めて「自分でできた!」と感じられます。この体験の積み重ねが自信につながり、「ゼロから1」を生み出すアート思考が自然と身についていきます。
また、「上手い・下手」という評価に基づく声かけはしないようにしています。その言葉は、無意識のうちに「上手に描かなくてはいけない」というメッセージを送ってしまうためです。
最初は褒められて喜んで描いていたとしても、小学校低学年を過ぎると、筆が進まなくなる子どもたちをたくさん見てきました。また、「褒められたいから描く」という自己承認欲求を満たすための創作になってしまうケースもあります。
「この色使いが素敵」「ここを工夫したのね」「最後までじっくり描いたね」など、作品の具体的な特徴や努力のプロセスに着目した感想を伝えることを心がけています。
評価や比較ではなく、その子なりの表現を認め、伸ばしていくことが大切だと考えています。

みんな大好きクリスマスお料理レッスン
アート教育のさらなる普及を目指して
ー今後取り組んでいきたいことについて教えてください。
今泉:アート教育に関する執筆活動を通じて、ご家庭でも気軽に取り組める方法などをご紹介していきたいと思っております。創造力や発想力を伸ばすだけでなく、心を癒す効果もあるアートの力を、ぜひ多くの方に感じて頂きたいです。
また、幼稚園や保育園の先生向けの指導講座にも力を入れていきたいと考えています。大人数のクラスではどうしても画一的な作品になりがちですが、工夫次第でもっと自由で個性的な作品作りが可能です。
その具体的な方法を広めていくことで、より多くの子どもたちがアートを通じて成長できる環境づくりを目指していきたいと考えています。
ー最後に、読者に向けたメッセージをお願いします。
アートには「正解」がありません。だからこそ、試行錯誤を重ねる中で子どもたちは自分で考え、決断する力を養うことができます。
子どもたちは、みんな素晴らしい可能性を秘めています。アトリエは、個性豊かな子どもたちを大きく包み、色とりどりの花を咲かせる場でありたいと考えています。

今泉 真樹(いまいずみ まき)
東京都出身。アトリエ・ピウ 知育こどもアート教室 代表。桑沢デザイン研究所を卒業後、英ローズ・ブルフォード大学を主席で卒業。国内外の有名ブランドや宝塚歌劇団のジュエリーデザインなどを手がける。2012年、アトリエ・ピウ 知育こどもアート教室を設立。子どもの自由な発想力や思考力を育てることに焦点をあてた絵画・工作・野外アート活動の指導を行う。 新宿区子ども未来基金助成活動【アートミック】アート講師も務める。 アート教育について、マイナビ様やこどもまなび☆ラボ様などへ執筆。保育園や幼稚園の先生向けに、アート教育セミナーも開催している。保育 絵画指導スペシャリスト ライセンス保有。