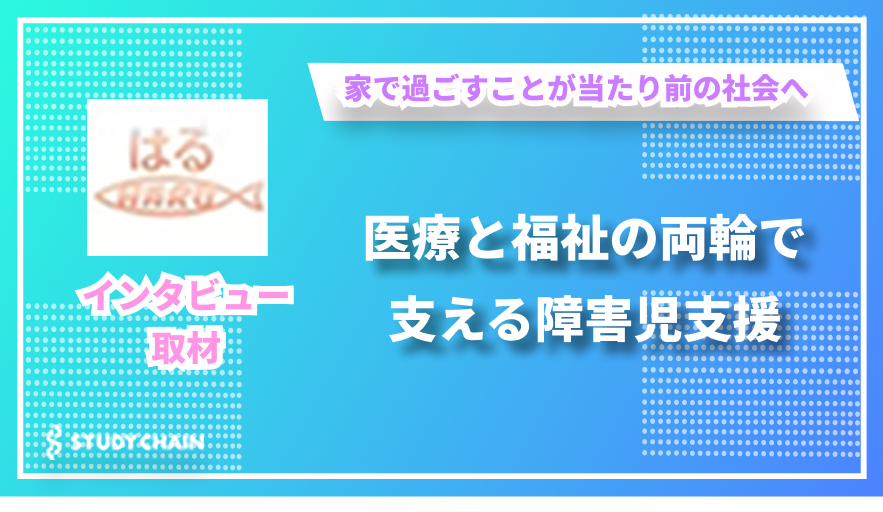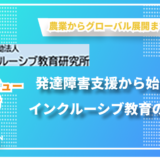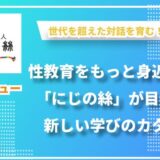横浜市を拠点に、医療的ケアが必要な子どもたちの在宅生活を支援する「はる訪問看護ステーション」。訪問看護に加え、障害児通所支援や相談支援など、医療と福祉の両面からサポートを行っています。
同法人の三島さんに、設立の経緯や活動内容についてお話を伺いました。
医療と福祉の両輪で子どもたちの生活を支える

ー法人の概要について教えてください。
三島:横浜市で訪問看護事業と障害児通所支援、障害児相談支援という医療と福祉の3つの事業を展開しています。主な対象は0歳から18歳としていますが、未就学時に利用された方が成人になっても、継続して支援する場合もあります。
対象となるのは医療依存度の高いお子さんで、重症心身障害児や医療的ケア児が中心です。最近では発達障害のお子さんも増えていますが、基本的には医療的なケアが必要なお子さんを対象としています。
在宅生活支援への想いから始まった15年の歩み
ー法人設立のきっかけや経緯を教えてください。
三島:法人自体は2011年に立ち上げ、最初に訪問看護事業からスタートしました。そこで医療のサービスだけでは限界があることを感じ、障害児通所支援や相談といった福祉サービスも併設していくことになりました。
当時は障害のあるお子さんは基本的に家で過ごすことが一般的で、外出の機会が非常に限られていました。しかし、時代の流れとともに放課後等デイサービスなどが増え、医療的ケアや障害があっても外出する機会が増えてきています。
また、以前は子どもの介護のために仕事を辞めるお母さんが多かったのですが、仕事を続けたいというお母さんの思いもある中で、医療だけでなく福祉のサービスも展開していく必要性を感じ、事業を拡大してきました。
専門性を活かした多角的な支援体制
ー実際に行っている活動の内容について詳しく教えてください。
三島:主な事業として、訪問看護、放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児相談支援を行っています。
さらに横浜市からの委託事業として、障害のあるお子さんの通学支援や、医療的ケアが必要なお子さんへの学校への看護師派遣なども実施しています。
相談支援では、お子さんの生活に必要なサービスの設計を行います。医療的ケアが必要なお子さんは看護師の存在なしには外出が難しいケースも多く、そういったお子さんに適したサービスを一緒に考え、実際のサービス提供先を探すなどの支援を行っています。
安全・安心を第一に考えた支援の提供
ー貴法人ならではの強みについて教えてください。
三島:職員のほとんどが看護師で、医療的依存度が高いお子さんに対して安心してサービスを提供できることが最大の強みです。
教育的な観点ももちろん大切ですが、まずは安全・安心に子どもたちが過ごせることを第一に考え、その上でお子さん一人ひとりに合った療育を提供しています。
ー活動を通じてお子さんと接する際に特に意識していることはありますか?
三島:体調を崩しやすいお子さんが多いのですが、そういった子どもたちにも普通に家で生活することが当たり前となるよう支援したいと考えています。
医療的ケアが中心となりがちですが、どんな障害があっても家庭や地域で生活できるよう意識して関わるようにしています。
地域との連携強化による支援の充実へ
ー今後より強化していきたい部分や、取り組んでいきたいことがあれば教えてください。
三島:時代の流れとともに、医療的ケアや障害があるお子さんでも学校に通ったり、外部の施設を利用したりする機会が増えています。そのため、在宅サービスだけでは子どもたちの生活を支えることに限界を感じています。
地域の施設とより密接な関わりを持ち、そこでも我々の専門性を活かしてお子さんの生活をしっかりと支えていきたいと考えています。医療と福祉の公的サービスを提供する立場として、制度の枠組みの中でできる最善の支援を追求していきます。
ーこの記事をご覧になる方へメッセージをお願いします。
三島:どんな障害があっても、どんな医療的ケアが必要でも、おうちで過ごすことが当たり前で、地域で生活できることが当たり前である社会を目指しています。
ご家族やお子さんたちが笑顔で生活できるよう、これからもお手伝いを続けていきたいと考えています。