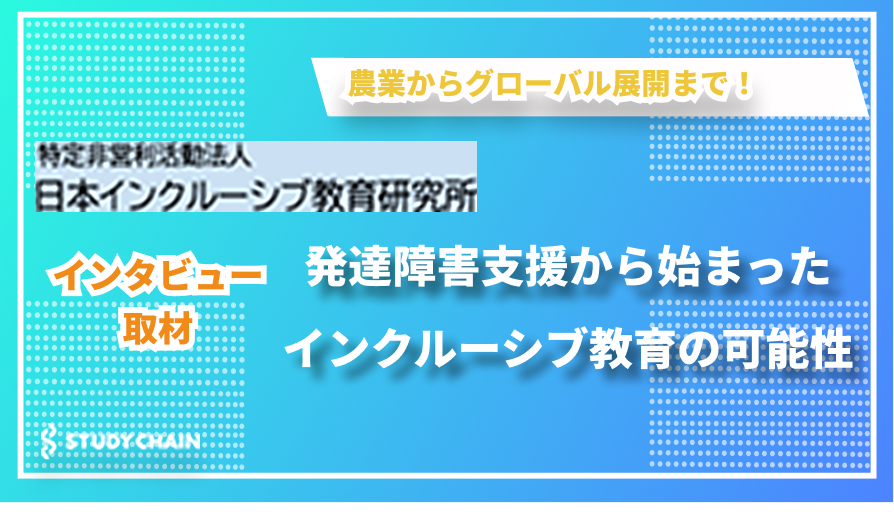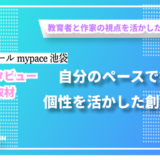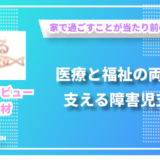発達障害の子どもを持つ親の支援から始まり、教師や支援者、そして社会全体のインクルーシブ教育の実現へと活動の幅を広げるNPO法人日本インクルーシブ教育研究所。
同法人の代表である中谷さんに、インクルーシブ教育の重要性と、その実現に向けた取り組みについてお話を伺いました。
全ての人を対象とした段階的な支援体制

ー団体の概要についてお伺いさせてください。
中谷:12年前の設立当初は「全ての人」を対象としていましたが、より具体的な支援を提供するため、まずは発達障害のお子さんをお持ちの保護者をターゲットに、子育ての仕方や対応方法をお伝えすることから始めました。
しかし、保護者だけでなく学校の先生方も適切な対応を学ぶ必要があることに気づき、教師や支援者へと対象を広げていきました。
その後、ピアノ講師やスポーツインストラクターなど、子どもに関わる様々な方々にも支援の必要性が認識され、さらには祖父母の方々からも「孫のために」という声が寄せられ、徐々に活動の範囲が広がっていきました。
結果として、当初目指していた「全ての人のためのインクルーシブ教育」という理念に近づいていったのです。
メディア経験を活かした啓発活動
ー活動を始めた経緯についてお聞かせください。
中谷:私は元々テレビ局のアナウンサーでしたが、ディレクターもしておりましたので学校取材などへも行っていました。その中で、不登校の児童生徒や、その親御さんの苦悩に触れる機会が多くありました。
取材を進める中で、多くの子どもたちや保護者が苦しんでいる現実を目の当たりにし、不登校やひきこもり、家庭内暴力など、さまざまな課題に直面する中で、「発達障害」という言葉にも出会いました。
当時は発達障害に対する理解が十分でなく、「親の育て方が原因」といった誤った認識が広がっていました。しかし、同じ親から育てられた兄弟でも、発達障害の特性を持つ子とそうでない子がいることから、それが誤りであることに気づきました。
東京や大阪、九州など各地で学びを深める中で、発達障害は生まれつきの特性であり、誰もが何らかの特性を持っているというグラデーションの考え方に至りました。
このことを多くの人に伝えることで、自責の念に苦しむ母親たちが救われる姿を見て、より多くの人が幸せになれる社会の実現を目指したいと考えるようになりました。
体験型学習による支援者育成
ー実際に行っている活動の内容について詳しくお聞かせください。
中谷:主な活動の一つとして、「学習・発達支援員養成講座」を実施しています。約20人の講師陣が、8回にわたる講座を通じて、幼児期の子育てから思春期の対応まで、幅広いテーマについて知識や経験を共有し、共に学び合いながら探究を深めています。
特徴的なのは、子どもを変えようとするのではなく、まず大人自身が変わることの重要性に気づき、そのプロセスを大切にしている点です。
講座の初回では「発達障害の疑似体験」を取り入れ、子どもたちが教室で感じる心理的な苦痛や困難さを、参加者自身が体験できるようにしています。
この体験を通じて、受講者は子どもたちの苦悩を理解するだけでなく、自身も教育の中で同様の経験をしていたことに気づくケースが多くあります。
農業を通じたインクルーシブ教育の実践
ー貴団体独自の取り組みについてお聞かせください。
中谷:特徴的な取り組みの一つに「インクルーシブな農業プロジェクト」があり、農業を通じてインクルーシブ教育について考える試みです。
土の中の様々な菌がバランスを保っているように、社会でも一人ひとりが必要な存在であるということを体感的に学べる取り組みとなっています。
また、「多様な発想支援士養成講座」では、インクルーシブ教育を体系的に学ぶ機会を提供しています。7つのステップを通じて、自身の中にある固定観念や偏見に気づき、それを見直していくプロセスを大切にしています。
例えば、「医師」という言葉を聞いたときに男性を思い浮かべるような無意識の偏見に気づき、それを手放していく実践的な学習を取り入れています。
さらに、今年からは海外視察ツアーも計画しており、フィリピンのような発展途上国で自然に育まれているインクルーシブな社会や、カナダにおける先進的なインクルーシブ教育の実践から学ぶ機会を提供する予定です。
グローバルな視点でのインクルーシブ教育の探求
ー最後に、読者の方に向けたメッセージをお願いします。
中谷:自分にとっての「普通」は、他人にとっての「普通」とは限りません。それぞれに異なる価値観や考え方があることを理解し、対話を通じて互いを知ることが大切です。
特に、上司と部下の関係など、立場の違いを超えて人間同士として対話できる社会を目指したいと考えています。
フランスの哲学者モンテスキューは、「私たちは3つの教育を受ける。1つ目は両親から、2つ目は学校から、3つ目は社会からである。そしてこの3つ目の教えは、初めの2つの教えに全て矛盾するものである」と述べています。
社会から学ぶインクルーシブな価値観を大切にしながら、一人ひとりが「同じでなければならない」という思い込みから解放され、互いの個性を尊重し合える社会の実現に向けて、皆さんと共に歩んでいけることを願っています。