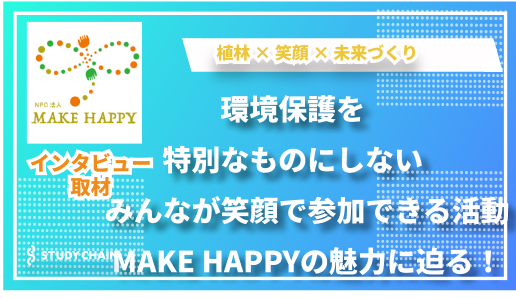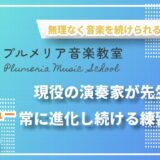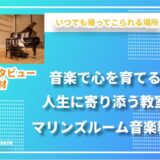環境問題を楽しみながら解決するNPO法人MAKE HAPPY。植林・間伐、災害支援、海洋クリーン活動を通じて、社会をより良くするプロジェクトを展開しています。参加者が笑顔になれる独自の活動方針とは?これからの展望と共に、その魅力に迫ります!
活動の概要について教えてください。
NPO法人MAKE HAPPYは、2004年に誕生した環境・社会への応援を目的とする団体です。活動の主軸は、「地球に緑を、世界に笑顔を、社会に志を」というミッションの下で、地球環境の保全、災害復興支援、生態系の保護に関わる不定期なプロジェクトです。
主な活動内容として、以下の4つのプロジェクトを運営しています。
植林・間伐活動: 欧米や中国の砂漠地域での植林活動や、日本国内の森林間伐を通じて、環境リフォームを推進しています。
災害復興支援: 東日本大震災をはじめ、石川県能登半島での災害支援を継続し、恒久的な移行支援や現地のコミュニティケアを行っています。
海洋クリーン活動: バリ島を中心に、水域環境保護のための海洋クリーンイベントを実施しています。
講演・教育プログラム: 現地の知識を活かしたワークショップを開催し、学生や主婦を中心に活動の意義を伝える教育活動を実施しています。
立ち上げたきっかけについて教えてください。
MAKE HAPPYは、2004年に一枚の写真から始まりました。その写真に映っていたのは、アフガニスタンのストリートチルドレン。貧困が他人事ではなく、地球を取り巻く環境問題に混在していることを知り、「何か自分にできることを」と考えたことがはじまりです。
先代の代表は光景自然や海洋ゴミを話題にしたドキュメンタリー映画を制作するつもりでしたが、そこから活動のエリアが大きく広がり、いままでの展開に至りました。最初の活動は、中国内モンゴルの砂漠地帯における植林でした。環境破壊の深刻さを目の当たりにし、「砂漠化を防ぐには木を植えるしかない」と考え、現地での植林を開始しました。その後、東日本大震災をきっかけに災害復興支援活動にも着手し、今では多岐にわたる活動を展開しています。
特徴・強みについて教えてください。
MAKE HAPPYの特徴は、「環境問題を問題として捉えず、楽しみながら乗り越えていく」ことにあります。多くの環境保護団体がシリアスなアプローチを取る中で、私たちは笑顔や楽しさを重視し、ボランティア参加のハードルを下げることで、より多くの人々に関わってもらう工夫をしています。
特に、災害復興支援では地域の住民とともにお祭りやイベントを開催し、支援活動を単なる「援助」ではなく「共に楽しむ場」にすることを心掛けています。例えば、災害復興支援の現場では、復興作業と並行して地域の子供たちと一緒にイベントを企画し、笑顔を取り戻すきっかけ作りをしています。
また、植林ツアーでは仮装や音楽などの要素を取り入れ、「ただ木を植える」だけでなく、「環境問題を楽しみながら学ぶ場」にしています。このようなアプローチによって、多様な年代の人々が関心を持ち、継続的に参加してくれることが強みです。活動においては、環境保全だけでなく「人のつながり」も重視し、一つの活動が別の支援へとつながる相乗効果を生み出しています。
活動・指導方針について教えてください。
活動の基本方針は、「微力は無力じゃない」という理念のもと、一人ひとりが動けば変わるという思いを持ち、行動に移してもらうことです。そのため、活動のスタイルはできる限りフレキシブルであり、子供から大人まで幅広い年齢層が参加しやすい形を取っています。
また、ボランティアという言葉をあえて使わず、「一緒に楽しむ場」として活動を提供することで、より自然な形で社会貢献に関わることができるようにしています。さらに、参加者一人ひとりを対等な立場として尊重し、互いに学び合える場を提供することを大切にしています。
今後の展望についてお聞かせください。
今後の展望としては、より多くの仲間を増やし、活動の基盤を強化することが重要だと考えています。特に、月額サポーターの増加を目指し、1000人のサポーターが集まることで、スタッフを5〜6人常駐させ、より迅速に災害支援へ対応できる体制を整えたいと考えています。
また、コロナ禍以降中断していた海外での植林ツアーの再開も目指しており、まずは南アフリカでのプロジェクトを2025年から開始する予定です。国内でも、より多くの地域で植林活動を実施し、持続可能な社会を支える取り組みを進めていきます。
さらに、国内外での環境教育プログラムを拡大し、学校や企業と連携しながら、環境意識を高めるためのワークショップや講演会を充実させていきます。
メッセージ
私たちは、最初の一歩を踏み出す人を応援しています。「何かしたいけど、何をすればいいか分からない」という方こそ、ぜひ一緒に活動しましょう。
また、災害支援では週に2回の休みを除き、常にボランティアを受け入れています。自然保護や環境活動に興味がある方も、ぜひ一度体験してみてください。
どうしても現地に行くことが難しい方は、「ハッピーサポーター」として支援していただく方法もあります。少しでも関心を持っていただけたら嬉しいです。