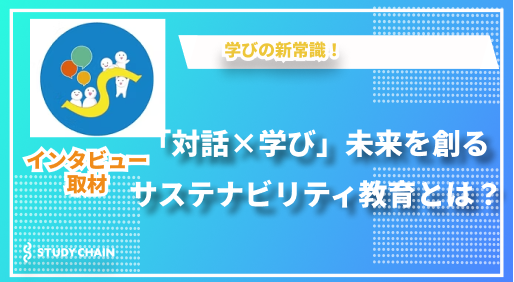未来を担う子どもたちに必要なのは、知識の詰め込みではなく、対話を通じた学び合い。サステナビリティ・ダイアログは、大人と子どもが対等に語り合いながら、持続可能な社会の在り方を考えるプログラムを提供しています。教育の新たな可能性を一緒に探求しませんか?
(語り手:宮崎汐里さん、反町恭一郎さん)
活動の概要について教えてください。
一般社団法人サステナビリティ・ダイアログは、サステナビリティと対話をテーマにした教育プログラムを提供する団体です。兼ねてから老若男女問わずプログラムを届けてきましたが、2021年からは、より力をいれて子どもたちとの学びの場づくりの実践にチャレンジしています。
対話型のESDワークショップ「宇宙船地球号ミッション!」を開発し、小学生以上(主に4年生以上)の子供たちを対象に、持続可能な社会の作り方を学ぶ場を提供しています。
ワークショップの基になっているのは、当団体代表の牧原ゆりえがスウェーデンのブレーキンゲ工科大学で学んだプログラム「サステナビリティのための戦略的リーダーシップを学ぶ修士課程(Master’s in strategic leadership towards sustainability)」です。世界中に実践者がいる学びのテーマを、日本の子どもたちが対話を通じて学べる環境を作っています。
このプログラムでは、答えのない課題に取り組むことを重視しています。「みんなが幸せに暮らせる社会」をどう作るかを、自分たちで考え、対話を通じてアイデアを共有し、学び合う内容です。プログラムの運営には、子どもだけでなく支援する大人も参加し、互いに学び合う関係を築いています。
立ち上げたきっかけについて教えてください。
サステナビリティ・ダイアログの法人設立の背景には、約20年前、代表の牧原が息子を授かった時、「この子の人生、この子の住む世界って、安心できるものだろうか」という問いに出会い、サスナビリティについて学ぶためスウェーデンに留学した大きなきっかけがあります。
牧原が出会った学びは、サステナビリティのことを「わかる」ことを目的とするのではなく「実践する」ことに重きが置かれています。
子どもも大人も、ビジネスマンも学生も、「個別の事情が分かり合えなくて協力出来ない」という状況に陥らずに、共通の基盤の上で、対等にどんどんやりとり出来るよう、とてもシンプルなフレームワークが提供されています。
こうした実践的な学びを日本に届けることで、よりよい未来に貢献しようとしたのが法人設立のきっかけでした。
私自身(宮崎さん)は2021年からこの法人に加わっています。それ以前は災害復興のプロジェクトに関わり、被災地域の持続可能な暮らしを取り戻すための活動を志していました。災害復興においては住民同士の対話が非常に重要で、その経験から対話の力に興味を持ちました。
しかし、独学で話し合いの場を各地でつくろうとしていた最中、場づくりのあり方に行き詰まりを感じるようになったのです。そんな時に参加したのがサステナビリティ・ダイアログが提供するプログラムでした。学びの場への参加をきっかけに、活動に深く関わるようになりました。
現在、法人に所属するメンバーは、私のように、もともとプログラムの参加者として関わっていた人ばかりで、学び・対話することの価値を実感して活動に携わっています。
特徴・強みについて教えてください。
私たちの活動の最大の特徴は、子どもたちとの関わり方にこだわった「場作り」です。つい、大人と子どもほど年齢が離れると、「年長者が年少者に知識を教える」というコミュニケーションになりがちですが、私たちは出来る限り「大人と子どもが対等に学び合う場」を作ることを大切にしています。
このプロジェクトが誕生した背景には、子どもに対する社会の関わり方に対する問題意識がありました。様々な場面で、子どもは「教えられる存在」として扱われ、彼らの持つ知識や意見が十分に尊重されていないと感じることがあります。
私たちは、そのような固定観念を取り払い、「子どもも大人も対等に意見を交換できる場」を作ることを目指しています。
こうした場をつくるために、私たちは大人が「見守る」姿勢で関わることを大切にしています。プロジェクトの運営に関わる大人は、何かを教えるのではなく、子どもたちの考えが聞かれやすい環境をつくり、対話の中で学びを深めるサポートをする存在としてあろうとします。
運営に関わる大人は全員「見守る」ための研修に参加し、「見守る」ことについての考えや思いを率直に語り合いながら学び、多様な意見に耳を傾ける準備を整えます。
実際に子ども達と学ぶ環境においては、少人数でのグループワークを中心とした学習体制を作り、「一人で考える時間」を設けながらワークを進めるなど、子ども達の声がゆっくり考えが聞かれやすい環境づくりを工夫しています。
私たちは、子どもたちの主体性を大事にするためには「見守る」というアプローチが必要不可欠なアプローチだと考えています。
活動・指導方針についてお聞かせください。
「見守る」というあり方には、ある種の誤解が生じることもあります。私たちの活動の様子を少し遠くから見て、「ここの大人は何もしていないのではないか?」という指摘を受けることもありますが、実際には、子どもたちが自由に考えられる環境を作るために、意図的に介入を控える場面が多々あります。
私たちが提供するのは、「答えを教える場」ではなく、「考える場」です。
また、「グラフィック・ハーベスティング」の技術を用いて、話の内容を描くことで子どもたちの声を丁寧に拾い、どんな小さな意見も尊重することも徹底しています。対話を通じて、多様な考え方を受け入れる力を育てることも、私たちの活動方針の重要なポイントです。
今後の展望についてお聞かせください。
現在、私たちは「サステナビリティの基本的な教育を、対話を通じて届ける」ことを活動の軸に据えています。現在は「ウェルビーイング(幸福)」や「自然の循環」をテーマとしたプログラムを展開していますが、今後は「社会の持続可能性」や「地域経済」、「エネルギー」など、新たなテーマを追加し、学びの幅を広げていきたいと考えています。
また、「見守る大人」という役割がまだ十分に理解されにくいため、その価値を社会に広めるための発信力を強化したいと考えています。さらに、学術研究機関や学校、地域の組織、サステナビリティに思いのある企業などと連携し、活動の規模を広げることも視野に入れています。
メッセージ
(反町さん)私たちの活動に興味を持ってくださる方にお伝えしたいのは、「教えることではなく、見守ることが、子どもたちの可能性を広げる」ということです。
大人はつい、子どもが間違えたと感じたときにすぐに「正解」を教えたくなります。しかし、それは子どもにとって「失敗から学ぶ機会」を奪うことにもなります。
私たちは、間違いを通じて試行錯誤し、自分で気づきを得ることこそが、子どもの主体的な学びにつながると考えています。そうした「見守る教育」の価値を、一緒に広めていきたいと考えています。
(宮崎さん)サステナビリティは、まだ誰も完璧に達成しきったことのない大きな夢です。いまを生きる子どもたちを、夢に向かって試行錯誤していく仲間として迎えるために、私たちは、いまこの瞬間から、一人一人の声を聴き合い学び合っていく場づくりを行っています。
ぜひ、私たちと共に、「皆が大事にされる場」を作る活動に参加してみませんか?